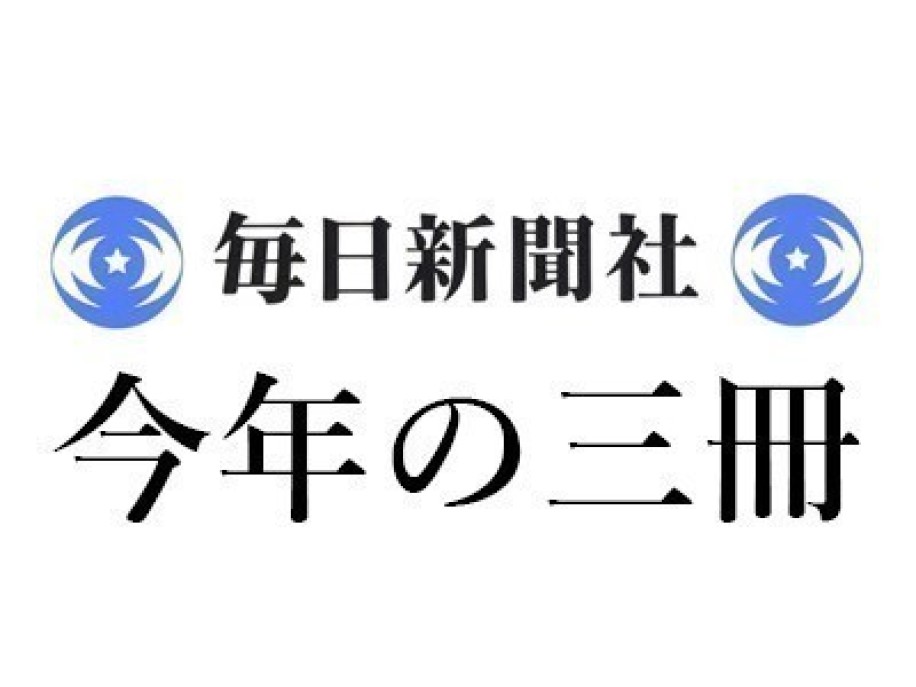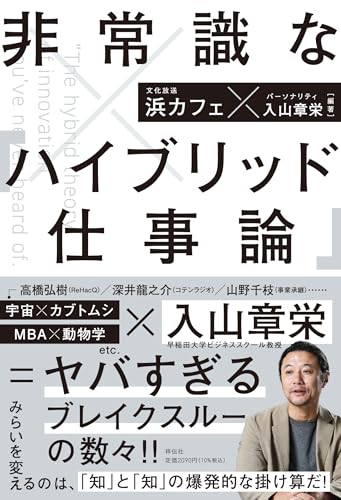書評
『日本の都市化: 刈谷の工業と政治』(丸善プラネット)
米国人が調査分析、経済成長の実情
本書は長らく「幻の本」であった。著者はゲリ・D・アリンソンという既に物故の米国人日本研究者。第二次大戦で敗れた日本が短期間で都市化と「高度成長」を遂げたのは世界を驚かせた。日本で何が起きているのか。地方に住み込んで調査分析したい。そう思った研究者が愛知県刈谷市にきた。2度にわたって刈谷の民家に住み、1872年から1972年までの100年にわたる城下町・刈谷の社会経済史を現地調査によって書き上げた。アリンソンはこの来日の間にスタンフォード大学大学院で日本史の博士号をえた。米国人のみた日本経済成長の現場での実証分析で、稀有な書物だが、日本語訳がなかった。外国人が珍しく、日本人が米国人に特に親切だった時代である。西村清という刈谷市民が調査に同行してアリンソンのインタビューを助けたが、この西村氏は晩年に、「歴史解説だけではなく、虫眼鏡でのぞくような事象のなりゆきや当時の人々の生きざまに焦点を絞った箇所もあるらしいから、一行一行の全文を日本語で読みたい!」と切望。翻訳者を刈谷市内で探した。同市出身の柴田みつ子さんという主婦が手を挙げた。柴田さんは11年間にわたって翻訳に取り組み、今回、見事に完訳を完成させた。
アリンソンが分析に刈谷を選んだのは、この町が「日本近代経済成長の縮図」だからだ。地理的にも日本中部で、城下町が工業都市になった中規模都市。しかも「トヨタ」系列の工場が多くある。既に早稲田大学チームが調査して、基礎資料は多くあった。アリンソンはそこへ入り込んで、日本で起きていることのディテールを見ようとした。
1870年当時、刈谷藩には335の侍世帯があり、侍とその家族1200人強がいた。その約20倍の領民がいて維新を迎えたが、旧庄屋や藩の重臣が「郡長」になる。著者は、日本は世襲制の強い性質をもつ点を見抜いている。また政治・経済両面での中央への地方の強い従属関係も指摘する。明治後期から大正期をさした叙述で「中央政府が…独占権を持つ。地方の市町村が根本的改革を独自に実施するのは不可能で、政府から割り当てられる資源に頼らざるをえない」とする。
また、労働者が横に連帯した労働組合が弱く、労働争議が稀であるとも。近代工業の繊維・織物労働者のかなりの部分が女性であり、無力な存在であった点を気の毒そうに書いている。政党や組合は弱く、1889年から1921年までの刈谷町の政界有力者は12家あり、侍子孫(士族)5家、豪商4家、大地主3家であった。町長と県会議員が全てこの12家の出身だった。
「学歴」の機能の見方も面白い。帝国大学進学などで将来の高級官僚と同窓生になり、中央とのパイプで地方政治に力を及ぼす姿をみる。転職でキャリアアップするアメリカと違い、日本の管理職は新卒入社後、退職まで組織内にいる昇進経路であった。そんな日本的な政治経済の細部の姿を刈谷の100年で鮮やかに描いている。この風土は、今日の日本の低成長と無関係ではなかろう。我々が先に進むため、乗り越えなくてはいけない古い丘の地図をはっきりと見せられたとの読後感をもった。
ALL REVIEWSをフォローする