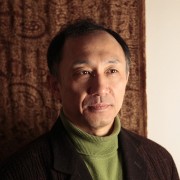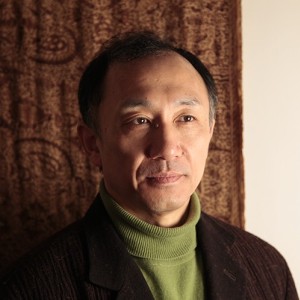書評
『地域社会圏主義 増補改訂版』(トゥーヴァージンズ)
個人と都市「閾」を備えた住宅群を
本書は2012年に刊行され、翌年刊行の増補版が昨年10月に再刊された。主著者である山本理顕(りけん)氏がこの3月に「建築界のノーベル賞」とも称されるプリツカー賞に選ばれたため紹介したい。注目点は別にもある。新年に能登が大地震に見舞われ、いまなお復興の遅れが懸念されている。これは私有の「持ち家」新築を誘導し、総需要のかさ上げに使ってきた戦後日本の住宅政策の限界を物語るのではないか。山本氏は事件や災害が起きるたびにセキュリティとプライバシーを高めてきた「1住宅=1家族」は地域コミュニティから「隔離」されるとし、本書では賃貸の公的住宅を提案している。今回の受賞理由は「建築を通じたコミュニティ創出」だった。
山本氏の「1住宅=1家族」批判には、15年の『権力の空間/空間の権力』(講談社選書メチエ)がある。ハンナ・アレントの『人間の条件』(ちくま学芸文庫他)に登場する私的でも公的でもない領域「no man′s land」を、「無人地帯」ではなく住宅における「閾(しきい)」と解釈、プラトンの「饗宴」でも使われたような部屋を古代ギリシアの間取りに見出している。アレントの意図が鮮烈にイメージできる読みである。
バラバラに建ち並ぶ戦後の住宅群に景観の秩序が備わらないのも、個人住宅が都市に通じる「閾」を欠いているからなのだ。本書はエネルギーや相互扶助をも地域社会で共有する「閾」を備えた住宅を提案している。
「イエ」は商店街のようにガラス張りで外部に開かれアトリエや勉強部屋、バー経営その他に使える「見世」と、閉じられた「寝間」から成る。2・4をモジュールとして何モジュールでも賃貸で増減でき、イエが集まるとレゴのように組み合わさって5―7人の「ベーシックグループ」となり、トイレ・シャワーやミニキッチン、太陽光発電を共有する。
ベーシックグループがつながれば120―150人規模でスパやランドリー、コモン収納、コジェネレーションシステム(発電機)を共有、500人規模となれば「生活コンビニ」と呼ばれる介護や育児スペースが備わり、地域社会圏となる。住民が有給バイトでサポートする仕組みだ。
仮想地域が2つ挙げられ、下町で緑の乏しい横浜市鶴見区の「郊外高密モデル」では6階建て(ha当たり750人)で緑溢れる公園を配し、中区不老町の横浜文化体育館の建替を想定する「都心超高密モデル」では高齢者を主に地上8階地下1階(同1500人)としている。地域の環境や丘の地形を崩さず2階、3階へはスロープを電動カート「コミュニティ・ビークル」で移動する。
突飛なアイデアと感じるかもしれないが、自然の通風を組み込む建築は大山崎の「聴竹居」、スロープを含んで各階がつながるのは高知県の「沢田マンション」、1階部に地域と住民が集まれる店を配するのは東京の「高円寺アパートメント」に実在すると評者は思う。トイレ共有もシェアハウスでは経験済みだ。三分の一が公的資金となると議会では拒絶反応が起きそうだが、商店街がシャッター通りで独居の高齢者が孤立する地方都市ではリアリティのある案ではないか。能登でも検討してはどうだろう。
ALL REVIEWSをフォローする