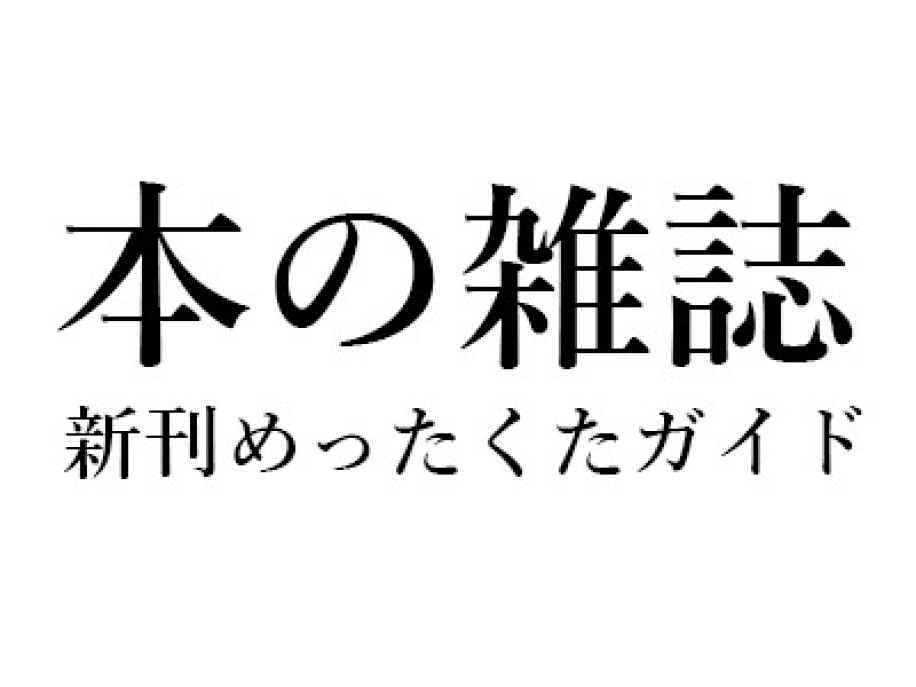書評
『アイドルについて葛藤しながら考えてみた ジェンダー/パーソナリティ/〈推し〉』(青弓社)
その主体性を奪っているのは誰か
10年ほど前、男性との交際が発覚した女性アイドルが丸坊主になって謝罪させられた映像が忘れられない。そもそも恋愛禁止というルールが人権侵害だと考えているが、ファンや同じグループのメンバーを裏切ったのだから当然だ、とする前提で事が進んでいく様子に戸惑ってしまった。本書は、「アイドルの文化実践として興味深い点は積極的に評価しながら、産業内の問題点にも目を向けて、揺れ動き、葛藤しながらアイドルについて複層的に考えていく」一冊。
主体性、という言葉が出てくる。アイドル産業を懐疑的に問う時、私も使ってきた言葉だ。果たしてそれは本人が望んでいることなのか、と問う。「『アイドルを生きる』なかで経験される『素』と『演技』の多重性」とある。理想のアイドルを演じながら、その一方で素の部分も求められる。しかし、どういった素であるべきかまで求められてしまう。これでは本来の自分が削られてしまう。
メイクが濃いとのコメントを受けたメンバーに「好きな色のリップを塗りなさい」と告げるリーダーがいたり、フェミニズムについての書籍を読んだことを伝えたりするアイドルも出てきている。ただ操られているだけではないというメッセージを発信し、それをファンが受け取る。この繰り返しによって、当人たちが抱える葛藤が表面化していく。
昨今、「推し活」がブームとなり、特定の存在に熱を上げる様子が方々で伝えられる。では、その熱視線を浴びる人たちの負荷はどうなのか。その言動に主体性はあるのか。ないとしたら、それを奪っているのは誰か。本書を読めば、論点がいくつも見つかる。なぜその論点が放置されてきたのか、から問いたい。
ALL REVIEWSをフォローする