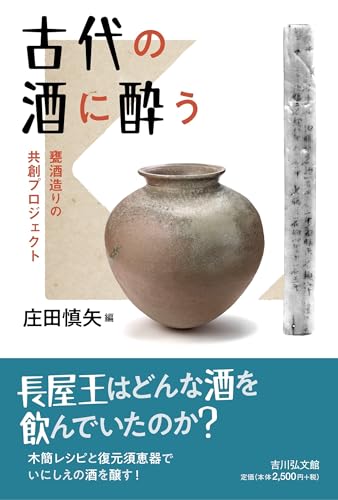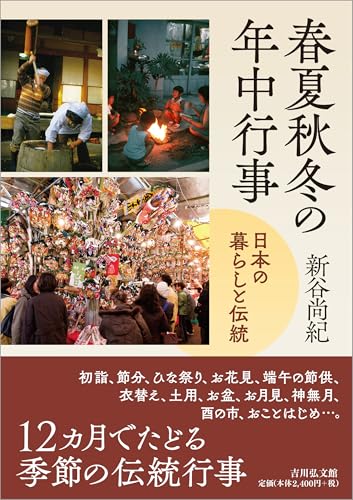本文抜粋
『古代の酒に酔う: 甕酒造りの共創プロジェクト』(吉川弘文館)
酒の考古学と甕酒造り
はじめに
本書は、甕(かめ)造りの酒、特に素焼きの焼き物で醸したアルコール飲料について、考古学、文献史学、調理学、醸造学、微生物学、文化人類学の研究者、あるいは醸造実践者の立場から、その特徴を多角的に検討するものである。ここではその前提として、そもそも酒造りに関して、筆者の専門とする考古学を中心に、これまでどのような学術的探索が行われ、またどのような取り組みが今後期待されるのかを簡単に考察したうえで、なぜ甕酒に注目するのかを明らかにしつつ、本書の位置づけを考えてみたい。これはまったく個人的な見解であるが、考古学者には、私を含め酒呑みが多い。それは、時に数週間にもおよぶ僻地(へきち)でのフィールドワークに出かけると、夜には酒を飲む以外に特にやることもなく、めいめいに杯を傾け夜な夜な語り合いながら、えも言われぬ連帯意識が醸成されるわけである。特に、キャンプをしながらの発掘調査では、日が暮れれば作業もままならないという格好の言い訳付きである。そして満天の星の美しさや焚き火の暖かさ、薪の弾ける音で演出される格別のセッティングは、飲酒と語らいの場をいっそう特別なものにしてくれる。これだけ呑兵衛の多い考古学業界であるから、酒の研究をしようという研究者が次から次へと出現して談論風発、百花繚乱となってもおかしくないはずであるが、実際は酒そのものを正面から扱った研究事例は驚くほど少ないのである。
この低調さの理由は無論、酒に対する関心の低さからではなく、実際に遺跡から出土しないものを研究対象とする難しさによる。酒とはエタノールが含まれた飲料の総称であるが、揮発性の高いエタノールがそのまま遺跡に残されていることはまず期待できない。後に述べるように、さまざまな状況証拠や図像・文字の情報に頼ることなしには、遺跡に残された酒そのものを研究対象とすることは難しい。ましてや、どのような酒をどのように醸していたのかを知ることなどは、雲をつかむような話にもなりかねないのである。
しかし一方で、これまで積み上げられてきた考古学的な研究成果や、近年の新しい潮流である考古生化学の研究を参照すると、今後酒造りの過去に関しての知識が新たに得られる期待感が高まっているのも事実である。旧稿においては、各所で「酒の考古科学的証拠」とされる研究事例の信頼度にはまだまだ課題が残っていることを紹介したが(庄田慎矢「“最古の酒”を疑う―古代の僧房酒を考える前提として―」『古代寺院の食を再現する』吉川弘文館2023年)、このような酒の歴史の探索の試み自体は手法を替えながら継続していく必要がある。ここでは、人類がいつから酒を飲み始めたのかをどのように知ることができるのかという問題から始め、酒にまつわる考古学的研究のいくつかの事例を簡単に紹介し、それをもとに甕に注目する理由が何かを述べることで、本書の位置づけを明確にする。
人類と酒の出会い
前世紀の半ばに出版されたエミール・ヴェルトの大著『農業文化の起源』には、「醸造の知識がほとんど地球全土に、そして人類のあらゆる経済集団、すなわち農民、牧畜遊牧民および狩猟民のところに存在しているのを見出す。したがって、酒はおそらく人類一般とともに古いものであろう」と書かれている(ヴェルト・エミール、藪内芳彦・飯沼二郎訳『農業文化の起源』岩波書店1968年)。これは卓見といえるが、実は近年の遺伝学的研究は、このヴェルトでさえも想像できなかった展開を見せている、ということから話を始めたい。米国フロリダ州にあるサンタフェ・カレッジのマシュー・キャリガン(Matthew A. Carrigan)らは、2015 年に米国科学アカデミー紀要(PNAS)に発表した論文の中で、既存の霊長類データベースおよび新たに採取した組織を分析して、霊長類でそれぞれの種が持つクラスIV アルコール脱水素酵素を比較し、ゴリラ~ヒトの系統では特にエタノールをより効率的に分解できるようになっていることを指摘した。クラスIV アルコール脱水素酵素とは、生体が口腔から摂取したアルコール飲料等が最初に通過する消化管内において、エタノールを代謝するアルコール脱水素酵素のことである。研究の結果、この酵素で突然変異がおこったのは約1000万年前のことであり、霊長類が陸上生活を始めた頃であることが明らかになった。つまり、それまで発酵度の高い果実が多い場所で生活していた霊長類が陸上生活を始めるにあたって、林床に落下した果実が発酵したものをエネルギー源として利用することができるという点で、エタノールを代謝する能力があったほうが生存に有利に働いた可能性があるとしたのである(Carrigan, M. A., et al.(2015). Hominids adapted to metabolize ethanol long before human-directed fermentation. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(2))。
すなわち、人類が文字通りの人類、つまりヒトとなる以前から、すでに遺伝的にはアルコールを摂取するのに適した体質を持ち合わせていたということになる。この話から、中国や日本に伝わる「猿酒」を思い浮かべる読者も多いであろう。猿酒とは、たまたま落下した糖分を多く含む果実が樹木や岩石の窪みに残され、そこで熟し、自然発酵したものを猿が食べ、千鳥足状態になることを描写していったものである。
これに対し、米国イェール大学のフイ・リー(Hui Li)らの研究によれば、現生人類においてアルコールを摂取できなくなる方向の進化が、東アジアを中心にして起こったことが知られる(Li, H., et al.(2009). Refined Geographic Distribution of the Oriental ALDH2*504Lys (nee 487Lys) Variant. Annals of Human Genetics 73( Pt 3))。ヒトがアルコール飲料を摂取できるかどうかにはアルコール脱水素酵素(ADH1B)とアルデヒド脱水素酵素(ALDH2)の二つの酵素が関わっていることが知られている。これを活性化させるものとそうでないものの間の遺伝的な変異が、一塩基多型(SNP)として捉えられていることを利用し、この変異の有無によってアルコールを摂取できたかどうかを判断できるというわけだ。つまり、お酒が飲めないという体質を獲得したことが、それぞれの地域で生存に有利に働いた可能性があるというのだ。
酒が「飲める」ということが「飲めない」よりも有利と考えるのではなく、実は酒が飲めないほうがある種の適応形態であるというのは、二日酔いに悩みがちな筆者には、示唆するところが大きい。また、上記研究などで指摘されているように、アルコール依存症にかかるリスクを減らせるという意味では確かに有利な特徴であろう。いずれにせよ、人類が解剖学的現生人類となったその当初から、アルコールを摂取することが可能であった個体が多く存在し、果実の熟成など自然におきるアルコール発酵の恩恵に預かっていた可能性は十分である。ただし、こうした偶発的なアルコールの摂取と、計画的な醸造によるアルコール飲料の製作とでは、その規模や社会的・文化的重要性の次元がまったく異なることは、言うまでもない。
[書き手] 庄田 慎矢(しょうだ しんや・奈良文化財研究所国際遺跡研究室長)
『青銅器時代の生産活動と社会』学研文化社2009年、『AMS年代と考古学』(共著)学生社2011年、『武器形石器の比較考古学』(共編書・訳)書景文化社2018年、『ミルクの考古学』同成社2024年
ALL REVIEWSをフォローする