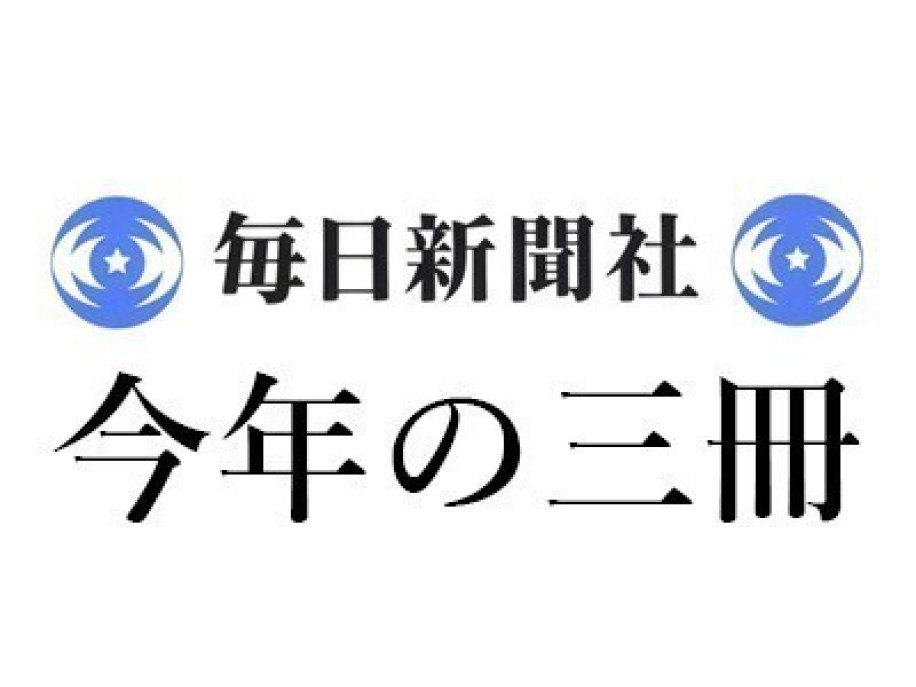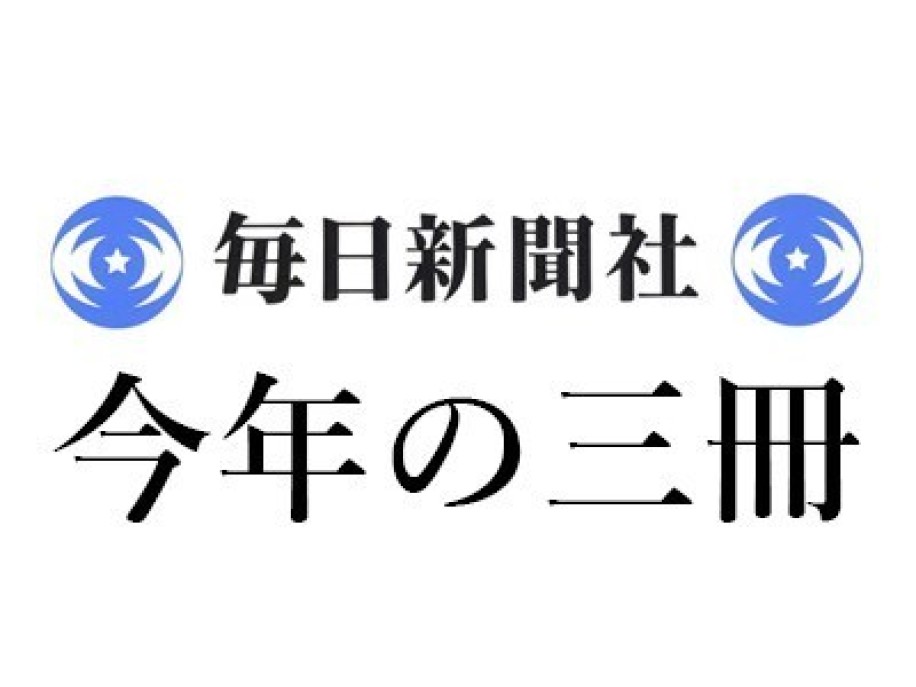書評
『タモリ論』(新潮社)
日本の日常の「空虚な中心」
タモリとは何か? 確かに、その存在の大きさに比して、真正面から語られなかった人物かもしれない。本書は「タモリ論」だが、著者は、インタビューや経歴、周囲の人物への聞き取りなどから人物像に迫るといったことはしない。それを期待する人は、読まない方がいい。多分怒る。本書いわく、タモリとは、調査の対象ではなく、あるとき急に「気付くもの」なのだと。
平日のお昼にテレビをつけると、30年間ずっとそこに必ず映っている彼のことを知らぬ者はいない。タモリは、日本人の生活、日常に深く刷り込まれているのだ。アプリオリ(自明)な存在過ぎて、見過ごしてしまう。そして、あるとき人は彼のすごさに気付く。それが日本人にとっての「通過儀礼」なのだという。
そうタモリとは日常である。逆に言えば、非日常とはタモリの不在を指す。著者は1985年の日航機墜落事故の翌日の「笑っていいとも!」が途中でニュースに変わったエピソードを思い出として語る。また東日本大震災後に、構成が変わったことも記憶に新しい。この国では、事件の大小は翌日の「いいとも!」の有無で示されるのだ。確かにそうだ。
終戦の年に生まれたタモリは、今年68歳。タモリが番組を降りる日を著者は「Xデー」と称する。さらにジョークとは言え、本書では、タモリがキリストになぞらえて論じられる。そして、直接言明こそされないが、天皇を論じるような語りもあるこの辺りの議論はもう少し踏み込んで欲しかった。著者は「後世に、タモリのことを何て伝えよう?」という提起をしているが「国民の統合の象徴みたいな存在?」という答えはどうだろう。平日のお昼0時という、一日の真ん中に空いている空虚な中心としてのタモリ……。タモリ語りを誘発させる本である。
朝日新聞 2013年8月25日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする