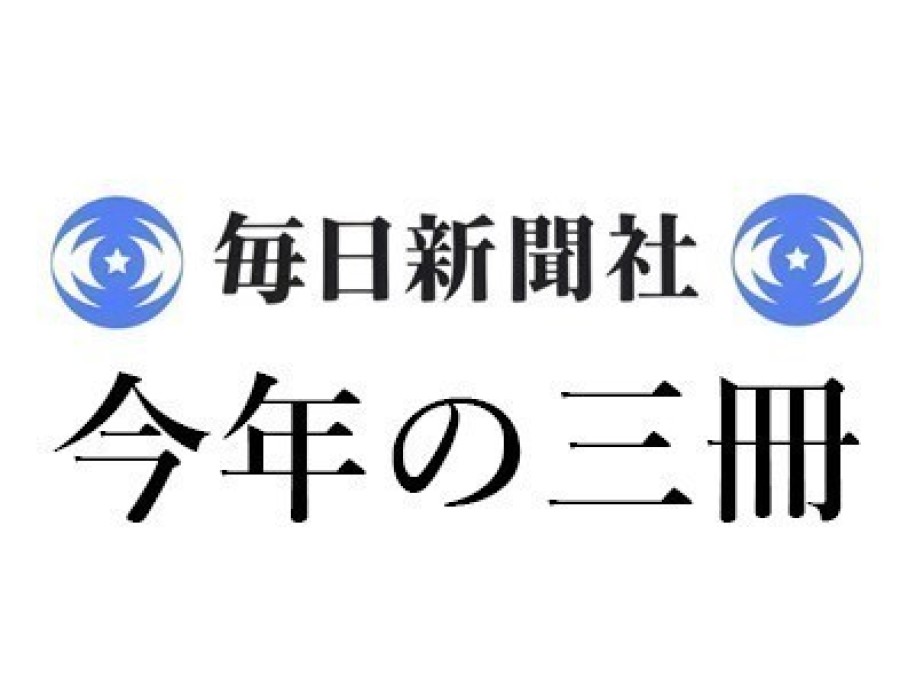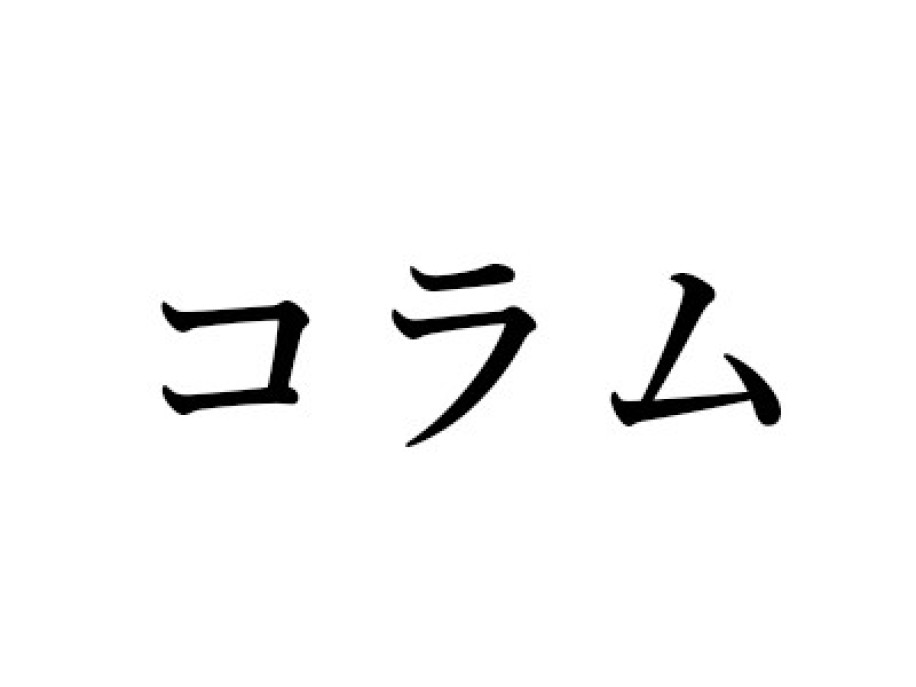書評
『母型論』(思潮社)
『マリ・クレール』ほかに連載された文章の集成。「母型論」から「原了解論」まで十三の論文が並ぶ。
本書の大きなモチーフは日本(ヤポネシア)の固有性を、周辺地域や地球大に拡がる人種系統・文化伝播の網の目のなかに置き直し、世界性に解消しようということ。起源を尋ねようとする強烈な意志が本書を貫いている。発生学、精神分析、言語学、文化人類学、遺伝子研究、古代歌謡の考察など様々な分析的手法によって、歴史以前に遡る日本人の集合的無意識が掘り下げられ、そこから、日本人が「アイヌ人」、「沖縄人」、「渡来者」とどのような交錯・分岐の関係にあるかのおぼろげなイメージが浮かびあがってくる。
本書が、吉本氏の『共同幻想論』、『心的現象論』をひき継ぐ仕事なのは明らかだ。そこで考えてみたいのは、いま起源にこだわることの意味は何か?
冷戦時代のマルクス主義・左翼思想は、未来に向かって日本を世界に開くという希望を広めた。それが退潮したあと、日本は単なる世界のなかの異質な文化となって孤立し、閉塞している。オウムのような、文化伝統や歴史をまったく踏まえない集団が現れたのも、そうした閉塞のなせるわざだった。そんななか吉本氏が、過去に向かって日本を世界に開こうとしているのは、九〇年代の緊急な課題という意味がある。
日本をその世界性においてとらえ直す。それは大切だ。ただしそれは「起源」(母型)でなければだめなのか? 《「母」系優位の初期社会が……男女の性交……と「母」の受胎、妊娠、出産との……関係……を認知できないところから由来している》(一一八頁)といった前世紀の人類学流の主張に、私はついて行けない。性交の否定は無知でなく、われわれの社会と同様に複雑な初期社会の「イデオロギー」の産物だと思うからである。
必ずしも「起源」にこだわらず、時間・空間のなかを多方向にたどることで、日本文化の世界性を新たに探り直していくこと。私は本書から、そんな課題を受け取った。
【この書評が収録されている書籍】
本書の大きなモチーフは日本(ヤポネシア)の固有性を、周辺地域や地球大に拡がる人種系統・文化伝播の網の目のなかに置き直し、世界性に解消しようということ。起源を尋ねようとする強烈な意志が本書を貫いている。発生学、精神分析、言語学、文化人類学、遺伝子研究、古代歌謡の考察など様々な分析的手法によって、歴史以前に遡る日本人の集合的無意識が掘り下げられ、そこから、日本人が「アイヌ人」、「沖縄人」、「渡来者」とどのような交錯・分岐の関係にあるかのおぼろげなイメージが浮かびあがってくる。
本書が、吉本氏の『共同幻想論』、『心的現象論』をひき継ぐ仕事なのは明らかだ。そこで考えてみたいのは、いま起源にこだわることの意味は何か?
冷戦時代のマルクス主義・左翼思想は、未来に向かって日本を世界に開くという希望を広めた。それが退潮したあと、日本は単なる世界のなかの異質な文化となって孤立し、閉塞している。オウムのような、文化伝統や歴史をまったく踏まえない集団が現れたのも、そうした閉塞のなせるわざだった。そんななか吉本氏が、過去に向かって日本を世界に開こうとしているのは、九〇年代の緊急な課題という意味がある。
日本をその世界性においてとらえ直す。それは大切だ。ただしそれは「起源」(母型)でなければだめなのか? 《「母」系優位の初期社会が……男女の性交……と「母」の受胎、妊娠、出産との……関係……を認知できないところから由来している》(一一八頁)といった前世紀の人類学流の主張に、私はついて行けない。性交の否定は無知でなく、われわれの社会と同様に複雑な初期社会の「イデオロギー」の産物だと思うからである。
必ずしも「起源」にこだわらず、時間・空間のなかを多方向にたどることで、日本文化の世界性を新たに探り直していくこと。私は本書から、そんな課題を受け取った。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする