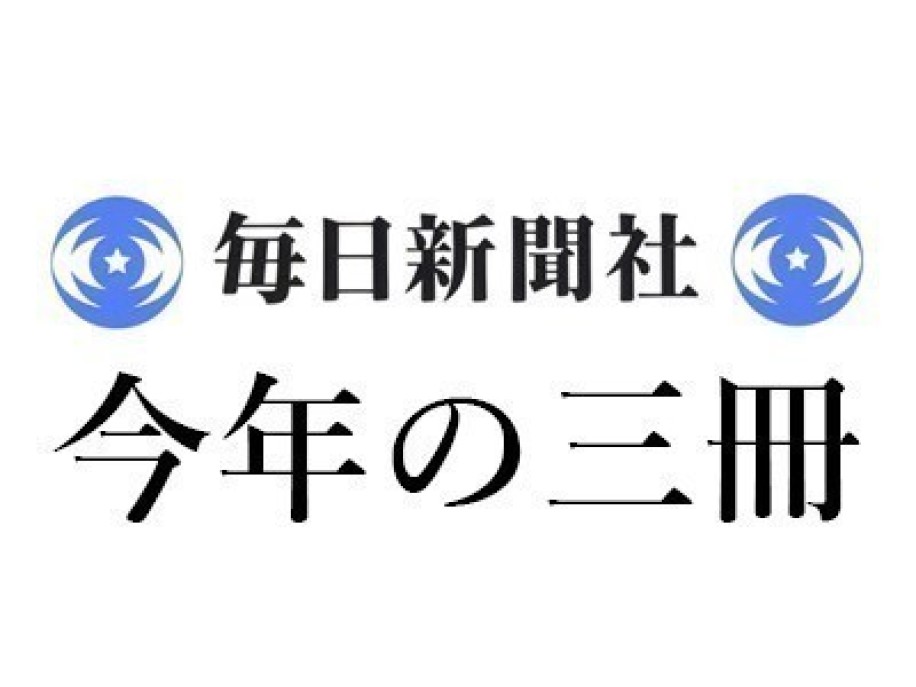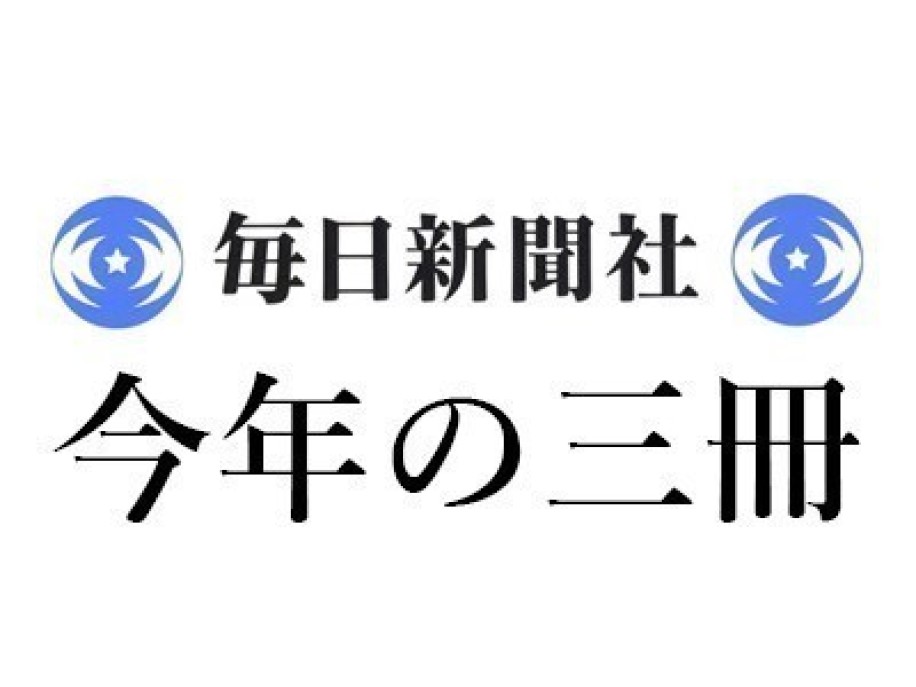コラム
オパーリン『生命の起源と生化学』(岩波書店)、ファラデー『ロウソクの科学』(岩波書店)、関川夏央『ソウルの練習問題』(新潮社)ほか
初めての書評委員会
町のご老人に本を借りると、中にその本の新聞書評がきちんとハサミで切って折りたたんだのがはさまっていることがある。すっかり褐色になっている。あ、きっとこの書評を見て、本屋に注文なさったのだな、とほんのり心が温かくなる。新聞の書評をはじめてから、「昔は『朝日』の書評に出ると千部は動くといわれたけどね」という話を何度聞いたことか。つまり本を読む人がかつてはいかに新聞書評を頼りにしていたか、ということだろう。亡くなった伯父もその一人だった。日曜日に祖父の家で会ったりすると、彼は最近の書評でどんな本が評判かを私に聞き、最後はかならず「では丸善に注文しよう」と頷くのだった。旧制高校出身の彼にとって本は、「丸善」でなければならなかった。理系の彼が私にすすめてくれたのはオパーリンの『生命の起源と生化学』とファラデーの『ろうそくの科学』である。
その影響で中学くらいから気になる書評を切りぬく癖があった私は、一九九〇年の春、「毎日新聞の書評委員になりませんか」と電話があったときはたまげてしまった(ALL REVIEWS事務局注:本コラム執筆時期は1993-4年頃)。その新聞で数年間、月一回くらい「本の紹介コラム」を書いていたけれど、書評委員とは。「私でつとまるのでしょうか」恐る恐る聞くと、O記者は「正直いってそういってる人も社内にいますが、僕はいままでの調子で書いてくれればいいと思ってます」とうけあってくれた。
一九八二年、私は仲間の女性たちと四人で『ほんのもり』という書評誌をはじめた。そこに、こんなことを書いている。
新聞書評に女の眼を
何ヵ月か前のこと、作家の津島佑子さんが『朝日』の書評委員になって、コラムにその辺の事情が書いてあった。女性の書評委員は十八年ぶりのことに津島さんも絶句、「せめてあと一人は」と要望されたとか。三大紙のあとの二紙も『毎日』は芸大の小島美(とみ)子さん一人、『読売』は高群逸枝研究などで知られる堀場清子さん一人といった調子で、あとは男性ばかりである。
そのせいか、とりあげられる本も、確かに話題作、名作にはちがいないが、家庭の主婦がとびつきたくなる本にはあまりお目にかかれない。家事、育児の本など、岩波新書の『母乳』といった権威あるもの以外、めったに登場しない。女は家庭欄のすみを見よといった感じ。この国では、とかく実用書をハウツウとかいって一段低く見る傾向があるようだ。でも、較べられるものではないけれど、画期的とはいえ、重箱の隅をほじくったような専門書より、人が生きていくのにどれほど役立つ実用書があるか知れない。
新聞の書評を読んでみると、これがまた、いかにもオトコが書いた、という文章。もちろんオンナも科学の先端分野や世界の大勢を知りたいのだが、はじめて聞くようなことを「周知の事実だが」「よく知られている」とやられると、それでもうおどかされて、本を読む気が失せてしまう。そして「得るところがあろう」「そうした問いを投げかけていると思われる」と書評文体とでもいった様式美。
近ごろ、書評って何だろう、としきりに考える。
学生のころ、何でも教養として身につけようと張り切っていたころは、こういう啓蒙的書評をありがたがっていた。でも、子供もいて時間の制約の多いいまとなっては、書評欄で本当に役に立つ一冊の本とめぐりあいたいと望むのは、ぜいたくなのだろうか。
本誌は、一読者の立場に立って、そういうお役に立ちたいと心がけているものである。
新聞にもそんな書評を書いてくれる、女性の評者の登場を待ちたい。でも、男のように考え、男のように行動するキャリア・ウーマンは願い下げ。お鍋の底のこげをこすったことのあるような人がいい。
いま読み返すと、なんとも気恥ずかしい文章ではある。これが毎日新聞の記者の目にとまって、私は数年間、出産・育児をはさんで「本の紹介コラム」を書きつづけ、紙面刷新にあたって書評委員になったのである。
最初の書評委員会の日はとにかく緊張してしまった。基本的には自分のやりたい本を選べばよいのだが、かいもく見当がつかない。まるで本の海に投げだされたようだった。これまた初めてで、緊張した面もちの(といったら怒るかな)関川夏央さんが隣りにいて、「毎回こんな中華料理のフルコースなんでしょうかね」「たまにはカレーライスが食いたいなア」などと冗談をいい合ったのを覚えている。大学の先生方の多いその場の厳粛な、やや暗い雰囲気に、私たち二人だけが場違いだ、という気がしたのだと思う。事実、関川さんはいつもの菜っぱ服というかコットンパンツにジャンパー、私はシャツにGパンで、あとの方はみなネクタイにスーツ姿だった。終わったときはほっとして、私はため息をついた。これからどうなることやら。ま、いいや、憧れの関川さんに会えたんだから。私は『ソウルの練習問題』(関川夏央、新潮文庫)の愛読者だった。
書評委員会も回を重ねるにつれ、怖そうな方々も話好きでやさしくて、愛妻家だったり、温泉や魚釣りが好きだったり、ワープロにまごついたりするフツーの人だと分かって私は楽しくなった。それから新聞社近くの高速道路の下にある屋台に移って二次会まで盛り上るようになった。私はこの何年かでどれほど多くのことをみなさんに教えていただいたかわからない。
最初の書評委員会の緊張とは、あれは本にはさまれ褐色に変色した書評への、私自身のフェティシズムであったにちがいない。
【このコラムが収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする