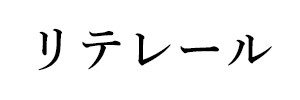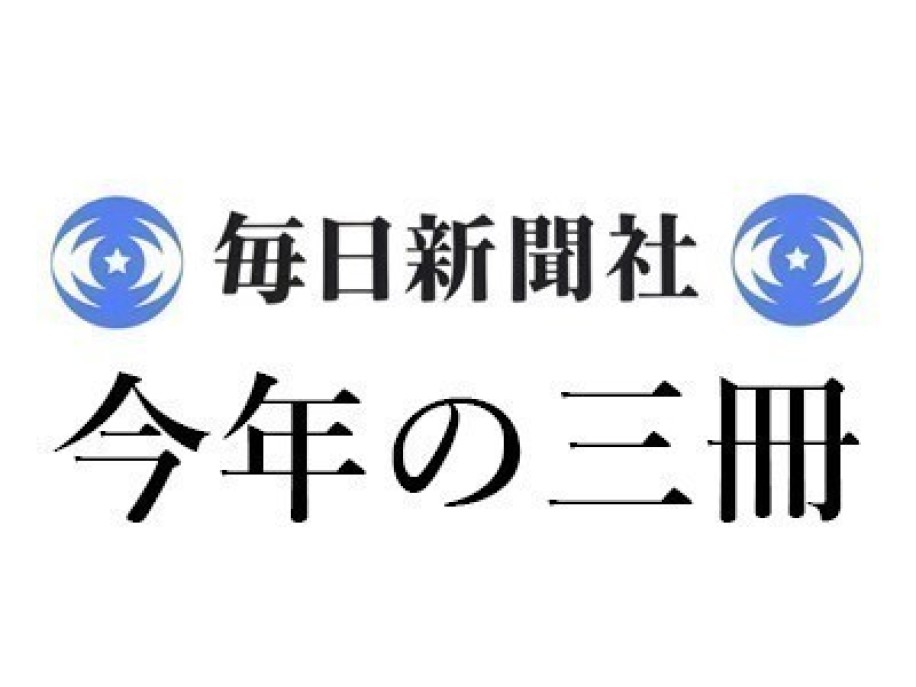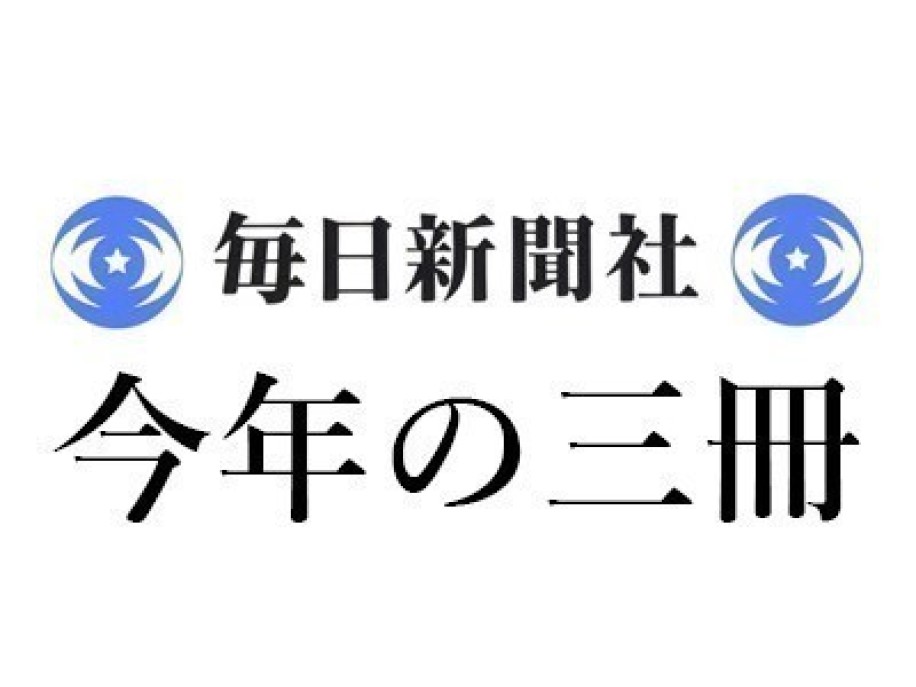コラム
ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論』(岩波書店)、カール・マルクス『ルイ・ボナパルトのブリュメール十八日』(岩波書店)ほか
私の書く本は書店泣かせだと出版社の人から聞かされたことがある。つまり、文学の棚でもなく、歴史の棚でもなく、どのコーナーに置いたらいいのか判らないというのだ。これを聞いて、なるほど売れない原因のひとつはそこにあるのかと思ったが、と同時に、これはかなりこちらの本質を言い当てているなとも感じた。なんとならば、文学の人間には「わたし歴史やっていますので」と言いながら、歴史の人間には、「もともと文学の人間なんで、歴史プロパーをやるつもりはないんです」とイソップ童話のコウモリさながらに、うまく責任逃れをしているからだ。
ただ、そうは言っても、別段こうした曖昧(あいまい)なスタンスに居心地の悪さを感じているわけではなく、むしろこのポジションを選んだことにそれなりの積極的な意義を見いだそうとしていたのだが、そうしたところへ、そんなどっちつかずの奴には天誅(てんちゅう)を加えるべしとばかり、『リテレール』編集部から、歴史にも首を突っ込んでいる以上、責任をもって歴史書を五十冊選んでみろときつい命令を受けてしまった。もっとも、編集部としても、私が正統的な歴史書を選べるわけはないと、はじめから見透かしているようなので、ここは、いっそ開き直って、曖昧なスタンスのままに、好き勝手な選択をさせていただくことにしたい。
とはいえ、選択には、私なりの基準というものを設定してみようかとは思っている。それは、例えていえば、ナポレオン三世とボードレールとメゾン・クローズ(淫売宿)に同じレベルの洞察力と感受性と好奇心をもってまなざしを投げかけることのできる本ということになる。このどれかが欠けてもいけない。というよりも、理想的なのは、ナポレオン三世を分析するような洞察力をもって、ボードレールとメゾン・クローズを見通し、ボードレールを読むような感受性をもって、ナポレオン三世とメゾン・クローズに接し、メゾン・クローズを調べるような好奇心をもってナポレオン三世とボードレールを探るということである。これがないと、退屈な政治史、ひとりよがりな文学論、皮相な社会史になってしまう。だが、たいていの本は、このレベルどまりなのだ。
たとえば、十九世紀フランスの歴史書を取り上げてみると、この条件をクリアしているものは、意外に数が少ない。ナポレオン三世を論じた本でも、もう少し文学的な感受性があればナポレオン三世という矛盾した怪人の内面に肉薄できるのに、また、メゾン・クローズのような下世話なものに対する好奇心があれば、ナポレオン三世のズボンを脱がせてみせることもできるのにと、ないものねだりならぬ、「あるべきもの」ねだりが口をついて出る。あるいはメゾン・クローズの社会史でも、死んだ遣り手ババアの残した財産目録を事細かに調べあげ、金だらい一つ、ショール三枚と、列挙するのも決して無駄だとはいわないが、こうしたトリビアルなものをナポレオン三世の政治体制と一挙に通底させてみるぐらいの洞察力や、軍楽隊に涙する『パリの憂愁』の老婆とアナロジーで結ぶくらいの感受性があってもいいと思う。要するにマクロをミクロの目で、ミクロをマクロの視点で眺めることのできぬ本は、けっして優れた歴史書とはいえないということである。そして、こうした制約を加えて選択を行うと、無限に思えた選択の幅はたちまち縮小し、まず、あのいわゆる退屈な政治史なるものをすべて捨象することができる。次いで、**の社会史、**の文化史という、単なる思いつきにすぎない駄弁を全部振り落とすことが可能になる。もちろん文学論にフーコー理論のイースト菌を人れて焼き上げたようなインチキ歴史物は論外である。
だが、ここまで選択基準を厳しくすると、今度は、該当する歴史書が極端に少なくなってしまう。もともと歴史家というものは、同業者の目をなによりも気にしているので、歴史からの逸脱だと言われまいとゴチゴチに自己規定をし、ひとこと言うごとにその典拠を示し、そのあげく、注の部分が本文の二倍というような、そして本文自体もカサカサに干からびた文学性ゼロの本を書き上げる(注は歴史家の免罪符だ!)。そして、歴史というのは、そういうものだとはなから思いこんでいるから、恬(てん)として恥じることもない。
ただ、こう言ったからといって誤解しないでいただきたいのだが、私はなにも、歴史の厳密さを無視した歴史読物の肩をもとうというのではない。それどころか、歴史読物に限らず、一次資料に当たらないで二次資料を適当にアレンジしただけの歴史書はまったくその価値を認めぬ立場に立っている。二次資料というのは、すでに相当な偏向がかかっているので、この歪(ゆが)みを矯正(きょうせい)できるほどの力がない限り、無批判に利用するのは禁物だからである。たとえ、二次資料同士を突き合わせてみても、偏向は元にはもどらない。
では一次資料に当たっていさえすればいいかといえば、けっしてそんなことはない。歴史書というのは言ってみれば地球空洞説のようなもので、いままで中身の詰まっていると思われた地球が、実は空洞でした、ということを証明してみせて、皆をアッと言わせることに醍醐味(だいごみ)があるのだが、それを証明するための開口部をどこに見いだすかは、ひとえに歴史家の感受性、というよりも、鉱山技師のカンに近い直感にかかっているのだ。つまり、センスのない鈍い奴は歴史家になるなということである。と、まあ言いたい放題のことを書いてしまったが、選んだものは、結局、アナール派的な文化史、それもヨーロッパ中心の文化史に落ち着いてしまった。アナール派でもつまらないものはいくらでもあるが、文学性豊かな人材はやはりその周辺に集まっているようである。
●ヴァルター・ベンヤミン/今村仁司・三島憲一他訳『パサージュ論』(岩波書店)
なんてったってベンヤミン。「ベンヤミン、天才。アドルノ、秀才。ブロッホ、鈍才」と十年前にいみじくも喝破した種村季弘氏の言葉を思い出す。いまや猫も杓子(しゃくし)もベンヤミンになびく御時世だが、それでもベンヤミンの凄(すご)さはまだまだ汲み尽くされてはいない。ベンヤミンの思想はすべてポエジーだから「感じて」わからなければ、いくら頭をひねってもだめなのだ。論文のためのノートにすぎないにもかかわらず、これほど刊行が待ち望まれた書物も珍しい。
●ヴァルター・ベンヤミン/川村二郎訳『ボードレール』(晶文社)
前記『パサージュ論』の序文「パリ——十九世紀の首都」を含むが、それと同程度に刮目(かつもく)すべきは、「ボードレールにおける第二帝政のパリ」である。そこで、ベンヤミンが与えている近代のイメージ、すなわち緑酒紅燈の巷(ちまた)に剣士のようにおりてゆくヒーローというのは、ありとあらゆる近代の定義の中で最高である。真に偉大な歴史家とは、たったひとつのイメージで時代を表象できる人のことを指す。
●エドゥアルト・フックス/安田徳太郎訳『風俗の歴史』(角川書店)
大学一年の時、ゾッキ本屋でたんなるエッチな好奇心で買いもとめ驚嘆。セックスというものがいかに相対的なものであり、歴史を最下部と最上部の両端で規定する、端倪すべからざるファクターであるかを理解した。あとでベンヤミンがフックスを先駆者として高く評価しているのを知って、自分の勘のよさを自分で誉(ほ)めた。なかでも「開拓者としてのフックスが収集家」になったというベンヤミンの言葉には泣かされた。
●カール・マルクス/伊藤新一・北条元一訳『ルイ・ボナパルトのブリュメール十八日』(岩波文庫)
このところ第二帝政にかんする本をいくつか読んだが、その洞察力の射程においてそれにかなう同時代の本はやはりなかった。ただ、遺憾とすべきは、「一度目は悲劇、二度目は茶番」という冒頭の言葉が、そこしか読まなかった読者に、ナポレオン三世はバカだ、という固定観念を植えつけてしまったことだろう。最後まで読めば、マルクスが、ナポレオン三世はゴロツキだ、とは言っているが、バカだとは決して言っていないことに気づくはずである。そして、慧眼(けいがん)なる読者は、ナポレオン三世に対するある種の愛情さえただよっていることを見抜くだろう。
●フリードリッヒ・エンゲルス/戸原四郎訳『家族・私有財産・国家の起源』(岩波文庫)
エンゲルスの歴史書は『ドイツ農民戦争』のように階級闘争史観の悪見本を作ってしまったものも多いが、モルガンの『古代社会』に拠ったこの本は、とくに近親相姦の禁止に関する考察で、否定しがたい説得力をもっている。私は、論理に込められたパワーというものにどうも弱い一面があるので、歴史書とはいえないが、あえて五十冊の中にいれておく。でも、エンゲルスって、意外と性格合うんだよな。
●マックス・ウェーバー/大塚久雄訳『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』(岩波文庫)
アナール派のいうマンタリテ(心性)の歴史の最高のモデルはすでに九十年前に書かれていた。何よりもまず、近代的資本主義は、ユダヤ人や中国人の利潤追求の貪欲(どんよく)な営利主義からではなく、利潤追求を罪悪視するプロテスタンティズムの禁欲的エートスから生まれたという逆説的な真理の発見がすばらしい。
●ソースタイン・ヴェブレン/小原敬士訳『有閑階級の理論』(岩波文庫)
バブルが、あと二年、はじけないで続いていたとしたら、ヴェブレンのこの本は、まちがいなくもっともトレンディな書物として奇跡のリヴァイヴァルを果たしていたことだろう。個人的には、「衒示的(げんじてき)消費」という新しい概念よりも、歴史的に古い「衒示的余暇」のほうに心ひかれる。なぜなら原稿書きに追い回される身としては、なにも生産せず、ただひたすら遊び暮らすという貴族の生活こそが理想郷として眼前に像を結ぶからである。
●オズワルト・シュペングラー/村松正俊訳『西洋の没落』(五月書房)
これをさきほど定義した私流の文化史にいれるのはおかしいではないかという声が聞こえてきそうだが、じつを言うと、歴史の流れに関するこの手の大ぼらというのが大好きなのである。「どの文化も、子供、青年、壮年、老年の時代を持っている」という文明寿命説は、さながらSF小説のように読める。そして実際、ハインラインやアシモフはシュペングラーに依拠して未来史を書いた。
●アーノルド・トインビー/長谷川松治訳『歴史の研究』(社会思想社)
我々が高校生の頃、トインビーは、今日のトフラーやガルブレイスのような「ホワイト・カラーのアイドル」だったが、いまでは、その大部の著作を読むものは、誰もいない。だが文明の成立を「挑戦と応戦」の法則によってとらえようとするその歴史観は、けっして捨てたものではない。リュシアン・フェーヴルが言っていたように、これに「生まれ、愛し、死ぬ」一人の人間への視線を加えれば、ブローデルになるのだから。
●エゴン・フリーデル/宮下啓三訳『近代文化史』(みすず書房)
人は自分にないものに憧(あこが)れるという定石どおり、ギムナジウムの伝統に育(はぐく)まれた、古典的教養こそ、私の憧れてやまぬものである。なによりも「調べて書いた」という恥ずかしい痕跡(こんせき)をいっさい消し去るフリーデルの廉恥心(れんちしん)が好ましい。「ペストで中世は終わった」とか「複式簿記の発明でルネッサンスが始まった」という奇抜な発想を惜しげもなくちりばめたこの文化史が連載コラムとして書かれたという事実を知ると、元気を出していいのやら、意気消沈していいのやら。
●ジークフリート・クラカウアー/平井正訳『天国と地獄——ジャック・オッフェンバックと第二帝政のパリ』(せりか書房・ちくま学芸文庫から再刊)
クラカウアーは『カリガリからヒットラーへ』(せりか書房)でも感動したが、この本はさらに熱中して読んだ。オッフェンバックという、二流であるが故に、その時代精神(ツァイト・ガイスト)をもっとも端的に示す人物に焦点をあわせ、時代そのものを描き出すという方法論にうなった。これを読んで、ようやく、十九世紀の社会史を本気でやろうと思うようになった。
●ヴォルフガング・シヴェルブシュ/加藤二郎訳『鉄道旅行の歴史』(法政大学出版局)
この十年間に読んだ文化史から一冊というのであれば、躊躇(ちゅうちょ)することなく、これをあげる。ヨーロッパの鉄道がコンパートメント・スタイルであるのに、アメリカの鉄道が中央通路方式なのはなぜかとか、読書という習慣は鉄道によって始まったとか、どこを読んでもメチャンコにおもしろい。タイトルの飾り気のなさでだいぶ損をしている。
●ヴォルフガング・シヴェルブシュ/小川さくえ訳『闇をひらく光』(法政大学出版局)
テクノロジーの進化が人間の心性に及ぼした影響を論じて、シヴェルブシュの右に出るものはいない。焚火(たきび)の炎から始まり、ローソク、ガス灯、電灯と進化していった照明技術の歴史を、闇(やみ)に対する恐怖と光のもたらす安心のせめぎあいという、心理の変容と重ね合わせるその語り口のうまさに脱帽。
●R・J・W・エヴァンズ/中野春夫訳『魔術の帝国——ルドルフ二世とその世界』(平凡社)
澁澤龍彥でおなじみのヴンダー・カマー(驚異の部屋)の皇帝ルドルフ二世は、単にあらゆる珍奇な事物や人間の収集家だっただけではなく、観念の収集家でもあった。プラハの宮廷に集められた芸術家、魔術師、哲学者、科学者などが織り成す観念の絵巻は、さながらアルチンボルドの絵のように、ルドルフ二世の魔術的肖像を描き出す。
●W・M・ジョンストン/井上修一・岩切正介・林部圭一訳『ウィーン精神——ハープスブルク帝国の思想と社会 1848-1938』(みすず書房)
ビーダーマイアーの君主フランツ・ヨーゼフの下、「シュランペライによって緩和された絶対王政」という、ある意味では、学問芸術にとって最適の環境で花開いた、十九世紀の徒花(あだばな)ウィーン文化。「検閲と目こぼし」や「死への願望」というフロイトのキー・ワード、あるいは、没政治的なユーゲントシュティールは、すべて、崩壊を待つだけの無為無策なハープスブルク体制から生まれた。
●ピーター・ゲイ/亀嶋庸一訳『ワイマール文化』(みすず書房)
戦勝国の理不尽な賠償請求の中で難産の末に生まれたワイマール共和国はフランクフルト研究所、ベルリン精神分析研究所、ワールブルク研究所、バウハウスなど多くの理想の「知性共同体」を生み出しながら、結局、誰ひとり強力な擁護者を見いだすことができずに、哀れ、ナチに扼殺(やくさつ)されていく。以前はひどい訳だったが、数年前に新しい訳者によって改訳され、面目を一新した。
●モードリエス・エクスタインズ/金利光訳『春の祭典——第一次世界大戦とモダン・エイジの誕生』(TBSブリタニカ)
アール・デコのグラフィックを調べていると、二十世紀というモダン・エイジを開いたのはロシア・バレエだったという確信を強くするが、エクスタインズによれば、このロシア・バレエの「春の祭典」で啓示された自由とスピードへの希求が、モダニズム国家ドイツに受け継がれ、第一次世界大戦と、ナチズムへとつながったという。第一次世界大戦を文化の戦争と見る観点はやや独断的にすぎるが、文化のターニング・ポイントがここにあったのはまちがいない。
●ホイジンガ/堀越孝一訳『中世の秋』(中央公論社)
なによりも、十五世紀をルネッサンスの始まりではなく、中世の終わり、すなわち「秋」としてとらえようとするその視点がすばらしい。三島由紀夫がこの本を激讃したのは、おそらく古代と同様、中世にも爛熟(らんじゅく)の「秋」があったというこのデカダンな発想だったのだろう。とりわけ、後半がおもしろい。
●マルク・ブロック/新村猛・森岡敬一郎・大高順雄・神沢栄三訳『封建社会』(みすず書房)
ホイジンガの『中世の秋』が、中世の終わりに力点を置いたのに対し、こちらは、マジャール人やヴァイキングの侵入を契機として中世封建社会がどのような物質的基盤とメンタリティーの上に成立していったかを分析する。「歴史書は探求することへの渇望をおこさせなければならない」というアナール史学の開祖の言葉は、歴史学を見事に要約している。
●フェルナン・ブローデル/浜名優美訳『地中海』(藤原書店)
歴史家になるためには、まず一流の文人でなければならないというフランスの伝統をあらためて思い起こさせてくれるのがこの本である。地中海を語るのに、まず山岳地方のはるか上方に視点を定め、次いで、ゆっくりと海辺へと降りてゆくというその鳥瞰(ちょうかん)的方法に、ユゴーの『諸世紀の伝説』の蘇(よみがえ)りを感じたのは、私だけだろうか。
●フェルナン・ブローデル/村上光彦他訳『物質文明・経済・資本主義』(みすず書房)
ブローデルは現在、『地中海』のみが話題になっているが、アナール派の方法論を知るにはこちらのほうがいいかもしれない。地域を地中海から世界に拡大し、人口統計学、古気象学等々の最新科学の成果を取り入れながら、資本主義の成立を、ウェーバーとはまったく異なる観点から説明しつくし、最後には、歴史の主人公は、食べて、着て、住むために働き、愛し、そして死ぬ、どこにでもいる一人の人間であることをいやおうなしに納得させてくれる。
●フィリップ・アリエス/杉山光信・杉山恵美子訳『〈子供〉の誕生』(みすず書房)
十六世紀まで子供は小さな大人だったという発見は、日本でもずいぶん大きな影響を及ぼした。この「日曜歴史家」を最初に発見したのが、トム・ソーヤの国アメリカだったというのがおもしろい。引き合いにだされるのはなぜか第一部「子供期へのまなざし」だけだが、第二部「学校での生活」はヨーロッパの文学をやる人間にとっては必読の文献である。
●バダンテール/鈴木晶訳『母性という神話』(筑摩書房)
女性が本能的に母性愛をもっているというのは本当か。バダンテールは歴史をさかのぼり、バルザックの時代には、貴族も民衆も子供は生んだとたん乳母に預け、母性愛などまったく感じるひまもなかったことを証明する。つまり、母性愛もまた近代の発明だったのだ。アリエスの『〈子供〉の誕生』(みすず書房)にしろ、この本にしろ、ルソーのあたえた影響が甚大だったことがよくわかる。
●ジョルジュ・デュビー/篠田勝英訳『中世の結婚——騎士・女性・司祭』(新評論)
考えてみれば、性欲を肯定しないキリスト教が結婚を祝福しているのは、不思議なことである。ローマ教会は、初め、悪はすべて性欲に起因すると考え、男女とも結婚せずに純潔のままに死ぬことを最善の道としていたが、やがて世俗の制度である結婚を、教会の秘蹟(ひせき)として制度化していくことになる。そのとき、世俗のモラルと教会のモラルはどのように絡み合っていくのか。性欲の抑圧こそがキリスト教文明の最も重大な問題であることを認識させられる。
●エマニュエル・ル・ロワ・ラデュリ/井上幸治・渡邊昌美・波木居純一訳『モンタイユー、ピレネーの村 1294-1324』(刀水書房)
カタリ派の異端を暴き出す情熱に燃えた一人の司教が、十四世紀のピレネーの一寒村の全住民を審問して作成した事細かな調書。法王庁に秘蔵されていたこの資料の解読から、村の若い女をすべて手ごめにする好色な司祭の行動を始めとする中世農村の日常生活や精神生活のすべてがあきらかになる。歴史とは覗き見の情熱と見つけたり。
●リュシアン・フェーヴル、アンリ=ジャン・マルタン/関根素子・長谷川輝夫・宮下志朗・月村辰雄訳『書物の出現』(筑摩書房)
書物を成り立たせるための前提条件、すなわち、紙、活字、挿絵、印刷技術、職工、それに、著者、出版業者、読者などのあらゆるファクターを、アナール派的な方法によって検証し、書物の発明の偉大なる影響を浮き彫りにした名著。かつて羊皮紙本は大きな財産だったというが、もし活字文化がこのまま解体しつづければ、出版部数の少ない本をもっていることはいずれ比類のない財産になるかもしれない。
●アラン・コルバン/山田登世子・鹿島茂訳『においの歴史——嗅覚と社会的想像力』(新評論。藤原書店より再刊)
自分が訳したからと言うわけではないが、アナール派の呼びかけるマンタリテ(心性)の歴史に、もっともブリリアントな答を出したのがこれである。悪臭と芳香の弁証法のうちに近代的なブルジョワ的感性の誕生を見抜くその手際の鮮やかさ。社会的(集団的)想像力の領野を歴史に取り込んだ意義は大きい。
●アラン・コルバン/福井和美訳『浜辺の誕生』(藤原書店)
『においの歴史』を訳しているときから感じていたのだが、これを読んで遂に判った。コルバンは、二十世紀のミシュレだったのだ。海と浜辺が、恐怖と嫌悪の対象から、ブルジョワの安楽の夢想を育むリゾート空間へと変わる変貌(へんぼう)の過程を文学作品や医学書のモザイクから浮き彫りにしていく手法は一層磨きがかけられ、歴史書というよりも、ほとんど文学作品になっている。
●フィリップ・ペロー/大矢タカヤス訳『衣服のアルケオロジー』(文化出版局)
フィリップ・ペローは、フランス社会史の最左翼に位置する新鋭で、衣服の供給と需要を社会・歴史的観点から眺めることにより、思いもかけぬ視野を切り開いてゆく。十九世紀後半における既製服の登場が、衣の歴史にコペルニクス的転換をもたらしたことを考慮すれば、この本はもっと注目されてよい。
●ミシェル・フーコー/田村俶訳『狂気の歴史』(新潮社)
結局、二十一世紀になって、二十世紀最大の歴史家は誰かと問いかけたら、やはり、フーコーしかいないということになるのではないか。ただ、この本や『監獄の誕生』を読むと、やたらにフーコーの方法論を振り回したくなってくるのが難点。『言葉と物』(いずれも新潮社)がどうしても理解できないとお嘆きの向きは、まずこれから入ることをお勧めする。
●ジャン=ポール・アロン『Essai sur la sensibilité alimentaire à Paris au 19e siècle』(Arman Colin)
レイモン・アロンの甥(おい)であるジャン=ポール・アロンの文体は饒舌(じょうぜつ)、ディレッタンティスム、ミスティフィカシオンなどの点で、フランス的知性の典型といえる。代表作にMangeur du 19e siècle(直訳すると『十九世紀の食べる人』、邦訳『食べるフランス史』人文書院)があるが、歴史的方法論の先駆性という点でこちらを取りたい。我々が今日フランス的な食習慣と思い込んでいるほとんどのものが、十九世紀に生まれたにすぎないことが見事に証明されている。
●ルイ・シュヴァリエ/喜安朗、木下賢一、相良匡俊訳『労働階級と危険な階級』(みすず書房)
人口統計学を歴史に応用し、若くしてコレージュ・ド・フランスの教授となった、ルイ・シュヴァリエ一世一代の大傑作。人口爆発で都市機能の危機に見舞われた十九世紀のパリを警察文書、公衆衛生学などの資料の解読や、バルザック、ユゴー、シューなどの作品に現れた都市の潜在的恐怖の分析を通して、ヴィヴィッドに描きだす。
●シオドア・ゼルディン『France 1848-1945』(Oxford University Press)
全十七巻の十九世紀ラルースを丸暗記しているといわれるイギリス人の歴史家ゼルディンが精根こめて書き上げた代表作。とりたてて独創的な歴史観が示されているわけではないが、とにかく近代フランスに関してはどんなささいなファクターも過不足なく取り上げられ、簡にして要を得た分析が加えられている。筆者の座右の書。翻訳に取り組む勇気のある出版社の出現を望む。
●ルイ=セバスチャン・メルシエ/原宏訳『パリの生活情景』(岩波文庫)
厳密に言えば、歴史書ではなく、一次資料だが、イギリスに遊学して相対性というものを身につけたメルシエは明らかに「現代の歴史家」と自らを位置づけて筆をとっている。つまりノン・フィクションやルポルタージュの走りなのだが、マスコミが発達してしまった現代は逆にこうした「現代の歴史家」の出現をさまたげてしまっているのではなかろうか。いずれにしろ、これなくしてはパリの社会史は成立しえぬ第一級の資料である。
●アンリ・マルレ絵、ベルティエ・ド・ソヴィニー文/鹿島茂訳『タブロー・ド・パリ』(新評論。藤原書店より再刊)
パリの国立図書館に眠っていた、王政復古期のパリを描いた石版画連作七十二枚をベルティエ・ド・ソヴィニーが発見して蘇らせた。オスマンの破壊する以前の街並を背景にして、働き、娯楽に興じる庶民の姿が、スナップショットのように捕えられている。自分で訳したからいうのではないが、この石版画連作は『モンタイユー』にも匹敵する発見である。
●バルザック/鹿島茂他訳「バルザック『人間喜劇』セレクション」(藤原書店)
十九世紀前半の歴史を知るにはバルザックを読むのが一番と言ったのは、マルクスだったかエンゲルスだったか。モノグラフィーであると同時に全体史であるという、アナール派的歴史書の定義を完璧(かんぺき)に満たしているのは、古今東西を通じてバルザックの総合的宇宙であるこの「人間喜劇」をおいてほかにない。いまや、新しい角度からバルザックを読み直す機運がたかまりつつある。
●ゾラ「ルーゴン=マッカール双書」(ほとんどが未訳)
十九世紀後半のフランスは、娼婦からナポレオン三世まで、デパートからパリの地上げまで、要するに、何から何までこの「ルーゴン=マッカール双書」の中にある。ゾラは、執筆に際しては、現場に赴き、綿密なノートを作成したので、史料的価値はきわめて高い。いずれ、本格的な紹介をするつもりである。〔後記。ゾラの没後百年を記念して、「双書」のほとんどが邦訳された〕
●オールティック/小池滋監訳『ロンドンの見世物』(国書刊行会)
まずは、このような驚くべき書物が翻訳されて、日本語で読めることに感謝すべきだろう。「見世物」という制度を、中世の聖遺物から万国博覧会まで、あらいざらい点検したこの本を読んでいると、びっくりするようなものを見てみたいという好奇心こそが、人間を人間たらしめている根源的な力ではないかという気がしてくる。
●スティーヴン・マーカス/金塚貞文訳『もう一つのヴィクトリア時代——性と享楽の英国裏面史』(中央公論社)
稀代(きたい)の奇書『我が秘密の生涯』の読解を中心に、金銭と精液の貯蓄を励行したヴィクトリア朝道徳の裏面を容赦(ようしゃ)なく暴き出す筆の冴えが何といっても痛快。ポルノグラフィーを分析する際のスタンスの取り方も絶妙で、ポルノと偽善的性道徳を通底させ、時代の共通したオブセッションをあぶり出してゆく。
●ダニエル・J・ブアスティン/新川健三郎・木原武一訳『アメリカ人——大量消費社会の生活と文化』(河出書房新社)
カウボーイやガンマンは、いかなる経済的要請によって生まれたのかとか、ラスベガスが離婚産業をもとに誕生したなど、現代アメリカの消費社会をその発生の必然性において捕えようとする試みは、はなはだ刺激的。こんなに面白い本が絶版になっているのはどうしたことか。早期の文庫化を望みたい。
●ディー・ブラウン/鈴木主説訳『わが魂を聖地に埋めよ』(草思社)
前出、ブアスティンの『アメリカ人』で、無人の荒野であるかのごとくに描かれた西部には、当然ながら、独自の文化を築いている先住民がいた。ディー・ブラウンは白人との条約会議で記録されたインディアンたちの発言を掘り起こし、残忍な野蛮人として害虫のように絶滅させられた、インディアンの高潔な魂の叫びを蘇らせる。『アメリカ人』と併せて読むこと。
●ワルター・クリヴィッキー/根岸隆夫訳『スターリン時代』(みすず書房)
この本を開いたときの衝撃を忘れることはできない。ジノヴィエフやカーメネフを「君がスパイだと自白すれば、それは社会主義の前進に役立つのだ」という倒錯した論理で落としたという箇所を読んだとき、書かれていることはすべて真実だ、と直感した。実際、ペレストロイカでクリヴィッキーの証言は百二十パーセント真実だったことが証明された。初版が翻訳された当時、偽書だと言うデマが公然と叫ばれ、日本のスターリニストたちによる圧力が出版社に加わって再版に三十年近い年月を要した。今後、スターリニズムの悪を暴く研究書は続々と刊行されるだろうが、スターリンの粛正が猛威をふるっていた一九三〇年代に書かれた本書をあえて五十冊に加えたい。
●ジョージ・オーウェル/橋口稔訳『カタロニア讃歌』(筑摩書房)
ファシストと戦うと同時に、スターリニストとも戦わなければならぬという絶望的状況がスペイン内戦の本質だった。したがって、六〇年代後半に、この本は、日本の大学のバリケードの中で、まさに我がことのように読まれていた。スペイン内戦は、ひとりオーウェルという証人を持っただけでも幸せである。
●バーネット・ボロテン/渡利三郎訳『スペイン革命——全歴史』(晶文社)
ヒュー・トマスの『スペイン市民戦争』に物足りなさを感じていた者にとって待ちに待った決定版研究書の翻訳である。これを読むと、スペインはファシスト化される選択肢と東欧諸国のようにスターリン化される選択肢のどちらを選ぶのが幸福だったのか、究極の設問をしたくなってくる。ここでも、クリヴィッキーの証言の正しさが証明されている。
●アミン・マアルーフ/牟田口義郎・新川雅子訳『アラブが見た十字軍』(リブロポート)
「明け方にフランク軍が到着した。たちまち大虐殺である」。聖地エルサレムを奪還するための十字軍も、アラブの側から見れば、金髪の蛮族「フランク」の理由なき侵略と虐殺でしかない。著者の記述は、いたずらに被害者意識を強調するのではなく、冷静にアラブ側の混乱を見据えている。湾岸戦争も、いずれこうした扱いをされるのかもしれない。
●エドワード・W・サイード/板垣雄三・杉田英明監修・今沢紀子訳『オリエンタリズム』(平凡社)
ヨーロッパ文化が十九世紀に、ロマン主義という形で蘇ったとするなら、そのカンフル剤のひとつは、まちがいなくオリエンタリズムであった。だが、オリエントの豊饒(ほうじょう)な富と文化は、それを理解できる西欧によってしか価値あるものにならないとするオリエンタリズムは、オリエントを永遠の隷属状態におくことになった。フーコーのディスクール理論を援用するサイードの議論は強引だが、いわんとするところは痛いほどよくわかる。
●岡田英弘『世界史の誕生』(筑摩書房)
水と油のように異質な地中海文明と中国文明を初めて一つのコンテクストで論ずることを可能にするもの、それは中央ユーラシアの遊牧民が行った定住地帯への進入の歴史であるとする著者は、モンゴル帝国を機軸にした世界史の構築を訴える。日本人には珍しい歴史の流れの読み替えを主張するその議論はまことに刺激的。
●阿部謹也『ハーメルンの笛吹き男』(平凡社)
ハーメルンの笛吹き男が連れ去った子供たちはどこへ行ってしまったのか。有名な民間伝承をめぐる様々な仮説を検討するうちに中世都市の下層民衆の生活がおのずと浮かび出てくるという巧みな構成が心にくい。暗い北ドイツから、さらに北へ植民を試みた中世賤民の苦しみが掬(すく)いとられ、読む者の心を打つ。
●宮下志朗『本の都市リヨン』(晶文社)
フランスの過去について考えるとき、我々が一番だまされてしまうのはいつの時代もパリが文化の中心だったわけではないということである。十五世紀から十六世紀にかけて、文化は出版・印刷・金融を中心としてリヨンから発信されていた。一次資料を駆使して、リヨン・ルネッサンスを、印刷・出版の観点から照射した力作。『書物の誕生』と併読すべし。
●角山栄・村岡健次・川北稔『産業革命と民衆——生活の世界歴史10』(河出書房新社)
いまでこそ**の社会史、**の文化史の花盛りだが、この本の書かれた一九七五年には、好事家的でない十九世紀生活史はまったくなかった。これを読んで目から鱗(うろこ)の落ちる思いがした人も多いだろう。同じ著者に名著『路地裏の大英帝国』があるが、日本におけるパイオニアということで、本書を取りたい。
パリの全歴史に関する本を一冊というのであれば、少し意外な選択かもしれぬが、このミシュラン・グリーンガイドを推す。とにかく、この小さなガイドブックに盛られたパリの歴史情報は並大抵のものではない。市販されているパリガイドのほとんどはこの本からの剽窃(ひょうせつ)でなりたっている。
●ジョン・マクドナルド/松村赳監訳・秦新二訳『戦場の歴史——コンピュータ・マップによる戦術の研究』(河出書房新社)
歴史は下部構造で動くとはいえ、戦場での勝敗が文明の運命を決するのもまた事実である。ところで、戦場での勝利は、つねに高地を制したほうへと傾く。とするなら、いくら平面図で戦場を研究しても埒(らち)はあかぬわけだが、ここに凸凹を自由自在に表現できるコンピュータ・マップという、まことに便利なものが登場した。ハンニバルのカンナエの戦いからディエン・ビエン・フーまで、自分が将軍になったような気持ちで「……たら」を連発し、パラレル・ワールドを夢想するのは楽しい。
【このコラムが収録されている書籍】
ただ、そうは言っても、別段こうした曖昧(あいまい)なスタンスに居心地の悪さを感じているわけではなく、むしろこのポジションを選んだことにそれなりの積極的な意義を見いだそうとしていたのだが、そうしたところへ、そんなどっちつかずの奴には天誅(てんちゅう)を加えるべしとばかり、『リテレール』編集部から、歴史にも首を突っ込んでいる以上、責任をもって歴史書を五十冊選んでみろときつい命令を受けてしまった。もっとも、編集部としても、私が正統的な歴史書を選べるわけはないと、はじめから見透かしているようなので、ここは、いっそ開き直って、曖昧なスタンスのままに、好き勝手な選択をさせていただくことにしたい。
とはいえ、選択には、私なりの基準というものを設定してみようかとは思っている。それは、例えていえば、ナポレオン三世とボードレールとメゾン・クローズ(淫売宿)に同じレベルの洞察力と感受性と好奇心をもってまなざしを投げかけることのできる本ということになる。このどれかが欠けてもいけない。というよりも、理想的なのは、ナポレオン三世を分析するような洞察力をもって、ボードレールとメゾン・クローズを見通し、ボードレールを読むような感受性をもって、ナポレオン三世とメゾン・クローズに接し、メゾン・クローズを調べるような好奇心をもってナポレオン三世とボードレールを探るということである。これがないと、退屈な政治史、ひとりよがりな文学論、皮相な社会史になってしまう。だが、たいていの本は、このレベルどまりなのだ。
たとえば、十九世紀フランスの歴史書を取り上げてみると、この条件をクリアしているものは、意外に数が少ない。ナポレオン三世を論じた本でも、もう少し文学的な感受性があればナポレオン三世という矛盾した怪人の内面に肉薄できるのに、また、メゾン・クローズのような下世話なものに対する好奇心があれば、ナポレオン三世のズボンを脱がせてみせることもできるのにと、ないものねだりならぬ、「あるべきもの」ねだりが口をついて出る。あるいはメゾン・クローズの社会史でも、死んだ遣り手ババアの残した財産目録を事細かに調べあげ、金だらい一つ、ショール三枚と、列挙するのも決して無駄だとはいわないが、こうしたトリビアルなものをナポレオン三世の政治体制と一挙に通底させてみるぐらいの洞察力や、軍楽隊に涙する『パリの憂愁』の老婆とアナロジーで結ぶくらいの感受性があってもいいと思う。要するにマクロをミクロの目で、ミクロをマクロの視点で眺めることのできぬ本は、けっして優れた歴史書とはいえないということである。そして、こうした制約を加えて選択を行うと、無限に思えた選択の幅はたちまち縮小し、まず、あのいわゆる退屈な政治史なるものをすべて捨象することができる。次いで、**の社会史、**の文化史という、単なる思いつきにすぎない駄弁を全部振り落とすことが可能になる。もちろん文学論にフーコー理論のイースト菌を人れて焼き上げたようなインチキ歴史物は論外である。
だが、ここまで選択基準を厳しくすると、今度は、該当する歴史書が極端に少なくなってしまう。もともと歴史家というものは、同業者の目をなによりも気にしているので、歴史からの逸脱だと言われまいとゴチゴチに自己規定をし、ひとこと言うごとにその典拠を示し、そのあげく、注の部分が本文の二倍というような、そして本文自体もカサカサに干からびた文学性ゼロの本を書き上げる(注は歴史家の免罪符だ!)。そして、歴史というのは、そういうものだとはなから思いこんでいるから、恬(てん)として恥じることもない。
ただ、こう言ったからといって誤解しないでいただきたいのだが、私はなにも、歴史の厳密さを無視した歴史読物の肩をもとうというのではない。それどころか、歴史読物に限らず、一次資料に当たらないで二次資料を適当にアレンジしただけの歴史書はまったくその価値を認めぬ立場に立っている。二次資料というのは、すでに相当な偏向がかかっているので、この歪(ゆが)みを矯正(きょうせい)できるほどの力がない限り、無批判に利用するのは禁物だからである。たとえ、二次資料同士を突き合わせてみても、偏向は元にはもどらない。
では一次資料に当たっていさえすればいいかといえば、けっしてそんなことはない。歴史書というのは言ってみれば地球空洞説のようなもので、いままで中身の詰まっていると思われた地球が、実は空洞でした、ということを証明してみせて、皆をアッと言わせることに醍醐味(だいごみ)があるのだが、それを証明するための開口部をどこに見いだすかは、ひとえに歴史家の感受性、というよりも、鉱山技師のカンに近い直感にかかっているのだ。つまり、センスのない鈍い奴は歴史家になるなということである。と、まあ言いたい放題のことを書いてしまったが、選んだものは、結局、アナール派的な文化史、それもヨーロッパ中心の文化史に落ち着いてしまった。アナール派でもつまらないものはいくらでもあるが、文学性豊かな人材はやはりその周辺に集まっているようである。
●ヴァルター・ベンヤミン/今村仁司・三島憲一他訳『パサージュ論』(岩波書店)
なんてったってベンヤミン。「ベンヤミン、天才。アドルノ、秀才。ブロッホ、鈍才」と十年前にいみじくも喝破した種村季弘氏の言葉を思い出す。いまや猫も杓子(しゃくし)もベンヤミンになびく御時世だが、それでもベンヤミンの凄(すご)さはまだまだ汲み尽くされてはいない。ベンヤミンの思想はすべてポエジーだから「感じて」わからなければ、いくら頭をひねってもだめなのだ。論文のためのノートにすぎないにもかかわらず、これほど刊行が待ち望まれた書物も珍しい。
●ヴァルター・ベンヤミン/川村二郎訳『ボードレール』(晶文社)
前記『パサージュ論』の序文「パリ——十九世紀の首都」を含むが、それと同程度に刮目(かつもく)すべきは、「ボードレールにおける第二帝政のパリ」である。そこで、ベンヤミンが与えている近代のイメージ、すなわち緑酒紅燈の巷(ちまた)に剣士のようにおりてゆくヒーローというのは、ありとあらゆる近代の定義の中で最高である。真に偉大な歴史家とは、たったひとつのイメージで時代を表象できる人のことを指す。
●エドゥアルト・フックス/安田徳太郎訳『風俗の歴史』(角川書店)
大学一年の時、ゾッキ本屋でたんなるエッチな好奇心で買いもとめ驚嘆。セックスというものがいかに相対的なものであり、歴史を最下部と最上部の両端で規定する、端倪すべからざるファクターであるかを理解した。あとでベンヤミンがフックスを先駆者として高く評価しているのを知って、自分の勘のよさを自分で誉(ほ)めた。なかでも「開拓者としてのフックスが収集家」になったというベンヤミンの言葉には泣かされた。
●カール・マルクス/伊藤新一・北条元一訳『ルイ・ボナパルトのブリュメール十八日』(岩波文庫)
このところ第二帝政にかんする本をいくつか読んだが、その洞察力の射程においてそれにかなう同時代の本はやはりなかった。ただ、遺憾とすべきは、「一度目は悲劇、二度目は茶番」という冒頭の言葉が、そこしか読まなかった読者に、ナポレオン三世はバカだ、という固定観念を植えつけてしまったことだろう。最後まで読めば、マルクスが、ナポレオン三世はゴロツキだ、とは言っているが、バカだとは決して言っていないことに気づくはずである。そして、慧眼(けいがん)なる読者は、ナポレオン三世に対するある種の愛情さえただよっていることを見抜くだろう。
●フリードリッヒ・エンゲルス/戸原四郎訳『家族・私有財産・国家の起源』(岩波文庫)
エンゲルスの歴史書は『ドイツ農民戦争』のように階級闘争史観の悪見本を作ってしまったものも多いが、モルガンの『古代社会』に拠ったこの本は、とくに近親相姦の禁止に関する考察で、否定しがたい説得力をもっている。私は、論理に込められたパワーというものにどうも弱い一面があるので、歴史書とはいえないが、あえて五十冊の中にいれておく。でも、エンゲルスって、意外と性格合うんだよな。
●マックス・ウェーバー/大塚久雄訳『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』(岩波文庫)
アナール派のいうマンタリテ(心性)の歴史の最高のモデルはすでに九十年前に書かれていた。何よりもまず、近代的資本主義は、ユダヤ人や中国人の利潤追求の貪欲(どんよく)な営利主義からではなく、利潤追求を罪悪視するプロテスタンティズムの禁欲的エートスから生まれたという逆説的な真理の発見がすばらしい。
●ソースタイン・ヴェブレン/小原敬士訳『有閑階級の理論』(岩波文庫)
バブルが、あと二年、はじけないで続いていたとしたら、ヴェブレンのこの本は、まちがいなくもっともトレンディな書物として奇跡のリヴァイヴァルを果たしていたことだろう。個人的には、「衒示的(げんじてき)消費」という新しい概念よりも、歴史的に古い「衒示的余暇」のほうに心ひかれる。なぜなら原稿書きに追い回される身としては、なにも生産せず、ただひたすら遊び暮らすという貴族の生活こそが理想郷として眼前に像を結ぶからである。
●オズワルト・シュペングラー/村松正俊訳『西洋の没落』(五月書房)
これをさきほど定義した私流の文化史にいれるのはおかしいではないかという声が聞こえてきそうだが、じつを言うと、歴史の流れに関するこの手の大ぼらというのが大好きなのである。「どの文化も、子供、青年、壮年、老年の時代を持っている」という文明寿命説は、さながらSF小説のように読める。そして実際、ハインラインやアシモフはシュペングラーに依拠して未来史を書いた。
●アーノルド・トインビー/長谷川松治訳『歴史の研究』(社会思想社)
我々が高校生の頃、トインビーは、今日のトフラーやガルブレイスのような「ホワイト・カラーのアイドル」だったが、いまでは、その大部の著作を読むものは、誰もいない。だが文明の成立を「挑戦と応戦」の法則によってとらえようとするその歴史観は、けっして捨てたものではない。リュシアン・フェーヴルが言っていたように、これに「生まれ、愛し、死ぬ」一人の人間への視線を加えれば、ブローデルになるのだから。
●エゴン・フリーデル/宮下啓三訳『近代文化史』(みすず書房)
人は自分にないものに憧(あこが)れるという定石どおり、ギムナジウムの伝統に育(はぐく)まれた、古典的教養こそ、私の憧れてやまぬものである。なによりも「調べて書いた」という恥ずかしい痕跡(こんせき)をいっさい消し去るフリーデルの廉恥心(れんちしん)が好ましい。「ペストで中世は終わった」とか「複式簿記の発明でルネッサンスが始まった」という奇抜な発想を惜しげもなくちりばめたこの文化史が連載コラムとして書かれたという事実を知ると、元気を出していいのやら、意気消沈していいのやら。
●ジークフリート・クラカウアー/平井正訳『天国と地獄——ジャック・オッフェンバックと第二帝政のパリ』(せりか書房・ちくま学芸文庫から再刊)
クラカウアーは『カリガリからヒットラーへ』(せりか書房)でも感動したが、この本はさらに熱中して読んだ。オッフェンバックという、二流であるが故に、その時代精神(ツァイト・ガイスト)をもっとも端的に示す人物に焦点をあわせ、時代そのものを描き出すという方法論にうなった。これを読んで、ようやく、十九世紀の社会史を本気でやろうと思うようになった。
●ヴォルフガング・シヴェルブシュ/加藤二郎訳『鉄道旅行の歴史』(法政大学出版局)
この十年間に読んだ文化史から一冊というのであれば、躊躇(ちゅうちょ)することなく、これをあげる。ヨーロッパの鉄道がコンパートメント・スタイルであるのに、アメリカの鉄道が中央通路方式なのはなぜかとか、読書という習慣は鉄道によって始まったとか、どこを読んでもメチャンコにおもしろい。タイトルの飾り気のなさでだいぶ損をしている。
●ヴォルフガング・シヴェルブシュ/小川さくえ訳『闇をひらく光』(法政大学出版局)
テクノロジーの進化が人間の心性に及ぼした影響を論じて、シヴェルブシュの右に出るものはいない。焚火(たきび)の炎から始まり、ローソク、ガス灯、電灯と進化していった照明技術の歴史を、闇(やみ)に対する恐怖と光のもたらす安心のせめぎあいという、心理の変容と重ね合わせるその語り口のうまさに脱帽。
●R・J・W・エヴァンズ/中野春夫訳『魔術の帝国——ルドルフ二世とその世界』(平凡社)
澁澤龍彥でおなじみのヴンダー・カマー(驚異の部屋)の皇帝ルドルフ二世は、単にあらゆる珍奇な事物や人間の収集家だっただけではなく、観念の収集家でもあった。プラハの宮廷に集められた芸術家、魔術師、哲学者、科学者などが織り成す観念の絵巻は、さながらアルチンボルドの絵のように、ルドルフ二世の魔術的肖像を描き出す。
●W・M・ジョンストン/井上修一・岩切正介・林部圭一訳『ウィーン精神——ハープスブルク帝国の思想と社会 1848-1938』(みすず書房)
ビーダーマイアーの君主フランツ・ヨーゼフの下、「シュランペライによって緩和された絶対王政」という、ある意味では、学問芸術にとって最適の環境で花開いた、十九世紀の徒花(あだばな)ウィーン文化。「検閲と目こぼし」や「死への願望」というフロイトのキー・ワード、あるいは、没政治的なユーゲントシュティールは、すべて、崩壊を待つだけの無為無策なハープスブルク体制から生まれた。
●ピーター・ゲイ/亀嶋庸一訳『ワイマール文化』(みすず書房)
戦勝国の理不尽な賠償請求の中で難産の末に生まれたワイマール共和国はフランクフルト研究所、ベルリン精神分析研究所、ワールブルク研究所、バウハウスなど多くの理想の「知性共同体」を生み出しながら、結局、誰ひとり強力な擁護者を見いだすことができずに、哀れ、ナチに扼殺(やくさつ)されていく。以前はひどい訳だったが、数年前に新しい訳者によって改訳され、面目を一新した。
●モードリエス・エクスタインズ/金利光訳『春の祭典——第一次世界大戦とモダン・エイジの誕生』(TBSブリタニカ)
アール・デコのグラフィックを調べていると、二十世紀というモダン・エイジを開いたのはロシア・バレエだったという確信を強くするが、エクスタインズによれば、このロシア・バレエの「春の祭典」で啓示された自由とスピードへの希求が、モダニズム国家ドイツに受け継がれ、第一次世界大戦と、ナチズムへとつながったという。第一次世界大戦を文化の戦争と見る観点はやや独断的にすぎるが、文化のターニング・ポイントがここにあったのはまちがいない。
●ホイジンガ/堀越孝一訳『中世の秋』(中央公論社)
なによりも、十五世紀をルネッサンスの始まりではなく、中世の終わり、すなわち「秋」としてとらえようとするその視点がすばらしい。三島由紀夫がこの本を激讃したのは、おそらく古代と同様、中世にも爛熟(らんじゅく)の「秋」があったというこのデカダンな発想だったのだろう。とりわけ、後半がおもしろい。
●マルク・ブロック/新村猛・森岡敬一郎・大高順雄・神沢栄三訳『封建社会』(みすず書房)
ホイジンガの『中世の秋』が、中世の終わりに力点を置いたのに対し、こちらは、マジャール人やヴァイキングの侵入を契機として中世封建社会がどのような物質的基盤とメンタリティーの上に成立していったかを分析する。「歴史書は探求することへの渇望をおこさせなければならない」というアナール史学の開祖の言葉は、歴史学を見事に要約している。
●フェルナン・ブローデル/浜名優美訳『地中海』(藤原書店)
歴史家になるためには、まず一流の文人でなければならないというフランスの伝統をあらためて思い起こさせてくれるのがこの本である。地中海を語るのに、まず山岳地方のはるか上方に視点を定め、次いで、ゆっくりと海辺へと降りてゆくというその鳥瞰(ちょうかん)的方法に、ユゴーの『諸世紀の伝説』の蘇(よみがえ)りを感じたのは、私だけだろうか。
●フェルナン・ブローデル/村上光彦他訳『物質文明・経済・資本主義』(みすず書房)
ブローデルは現在、『地中海』のみが話題になっているが、アナール派の方法論を知るにはこちらのほうがいいかもしれない。地域を地中海から世界に拡大し、人口統計学、古気象学等々の最新科学の成果を取り入れながら、資本主義の成立を、ウェーバーとはまったく異なる観点から説明しつくし、最後には、歴史の主人公は、食べて、着て、住むために働き、愛し、そして死ぬ、どこにでもいる一人の人間であることをいやおうなしに納得させてくれる。
●フィリップ・アリエス/杉山光信・杉山恵美子訳『〈子供〉の誕生』(みすず書房)
十六世紀まで子供は小さな大人だったという発見は、日本でもずいぶん大きな影響を及ぼした。この「日曜歴史家」を最初に発見したのが、トム・ソーヤの国アメリカだったというのがおもしろい。引き合いにだされるのはなぜか第一部「子供期へのまなざし」だけだが、第二部「学校での生活」はヨーロッパの文学をやる人間にとっては必読の文献である。
●バダンテール/鈴木晶訳『母性という神話』(筑摩書房)
女性が本能的に母性愛をもっているというのは本当か。バダンテールは歴史をさかのぼり、バルザックの時代には、貴族も民衆も子供は生んだとたん乳母に預け、母性愛などまったく感じるひまもなかったことを証明する。つまり、母性愛もまた近代の発明だったのだ。アリエスの『〈子供〉の誕生』(みすず書房)にしろ、この本にしろ、ルソーのあたえた影響が甚大だったことがよくわかる。
●ジョルジュ・デュビー/篠田勝英訳『中世の結婚——騎士・女性・司祭』(新評論)
考えてみれば、性欲を肯定しないキリスト教が結婚を祝福しているのは、不思議なことである。ローマ教会は、初め、悪はすべて性欲に起因すると考え、男女とも結婚せずに純潔のままに死ぬことを最善の道としていたが、やがて世俗の制度である結婚を、教会の秘蹟(ひせき)として制度化していくことになる。そのとき、世俗のモラルと教会のモラルはどのように絡み合っていくのか。性欲の抑圧こそがキリスト教文明の最も重大な問題であることを認識させられる。
●エマニュエル・ル・ロワ・ラデュリ/井上幸治・渡邊昌美・波木居純一訳『モンタイユー、ピレネーの村 1294-1324』(刀水書房)
カタリ派の異端を暴き出す情熱に燃えた一人の司教が、十四世紀のピレネーの一寒村の全住民を審問して作成した事細かな調書。法王庁に秘蔵されていたこの資料の解読から、村の若い女をすべて手ごめにする好色な司祭の行動を始めとする中世農村の日常生活や精神生活のすべてがあきらかになる。歴史とは覗き見の情熱と見つけたり。
●リュシアン・フェーヴル、アンリ=ジャン・マルタン/関根素子・長谷川輝夫・宮下志朗・月村辰雄訳『書物の出現』(筑摩書房)
書物を成り立たせるための前提条件、すなわち、紙、活字、挿絵、印刷技術、職工、それに、著者、出版業者、読者などのあらゆるファクターを、アナール派的な方法によって検証し、書物の発明の偉大なる影響を浮き彫りにした名著。かつて羊皮紙本は大きな財産だったというが、もし活字文化がこのまま解体しつづければ、出版部数の少ない本をもっていることはいずれ比類のない財産になるかもしれない。
●アラン・コルバン/山田登世子・鹿島茂訳『においの歴史——嗅覚と社会的想像力』(新評論。藤原書店より再刊)
自分が訳したからと言うわけではないが、アナール派の呼びかけるマンタリテ(心性)の歴史に、もっともブリリアントな答を出したのがこれである。悪臭と芳香の弁証法のうちに近代的なブルジョワ的感性の誕生を見抜くその手際の鮮やかさ。社会的(集団的)想像力の領野を歴史に取り込んだ意義は大きい。
●アラン・コルバン/福井和美訳『浜辺の誕生』(藤原書店)
『においの歴史』を訳しているときから感じていたのだが、これを読んで遂に判った。コルバンは、二十世紀のミシュレだったのだ。海と浜辺が、恐怖と嫌悪の対象から、ブルジョワの安楽の夢想を育むリゾート空間へと変わる変貌(へんぼう)の過程を文学作品や医学書のモザイクから浮き彫りにしていく手法は一層磨きがかけられ、歴史書というよりも、ほとんど文学作品になっている。
●フィリップ・ペロー/大矢タカヤス訳『衣服のアルケオロジー』(文化出版局)
フィリップ・ペローは、フランス社会史の最左翼に位置する新鋭で、衣服の供給と需要を社会・歴史的観点から眺めることにより、思いもかけぬ視野を切り開いてゆく。十九世紀後半における既製服の登場が、衣の歴史にコペルニクス的転換をもたらしたことを考慮すれば、この本はもっと注目されてよい。
●ミシェル・フーコー/田村俶訳『狂気の歴史』(新潮社)
結局、二十一世紀になって、二十世紀最大の歴史家は誰かと問いかけたら、やはり、フーコーしかいないということになるのではないか。ただ、この本や『監獄の誕生』を読むと、やたらにフーコーの方法論を振り回したくなってくるのが難点。『言葉と物』(いずれも新潮社)がどうしても理解できないとお嘆きの向きは、まずこれから入ることをお勧めする。
●ジャン=ポール・アロン『Essai sur la sensibilité alimentaire à Paris au 19e siècle』(Arman Colin)
レイモン・アロンの甥(おい)であるジャン=ポール・アロンの文体は饒舌(じょうぜつ)、ディレッタンティスム、ミスティフィカシオンなどの点で、フランス的知性の典型といえる。代表作にMangeur du 19e siècle(直訳すると『十九世紀の食べる人』、邦訳『食べるフランス史』人文書院)があるが、歴史的方法論の先駆性という点でこちらを取りたい。我々が今日フランス的な食習慣と思い込んでいるほとんどのものが、十九世紀に生まれたにすぎないことが見事に証明されている。
●ルイ・シュヴァリエ/喜安朗、木下賢一、相良匡俊訳『労働階級と危険な階級』(みすず書房)
人口統計学を歴史に応用し、若くしてコレージュ・ド・フランスの教授となった、ルイ・シュヴァリエ一世一代の大傑作。人口爆発で都市機能の危機に見舞われた十九世紀のパリを警察文書、公衆衛生学などの資料の解読や、バルザック、ユゴー、シューなどの作品に現れた都市の潜在的恐怖の分析を通して、ヴィヴィッドに描きだす。
●シオドア・ゼルディン『France 1848-1945』(Oxford University Press)
全十七巻の十九世紀ラルースを丸暗記しているといわれるイギリス人の歴史家ゼルディンが精根こめて書き上げた代表作。とりたてて独創的な歴史観が示されているわけではないが、とにかく近代フランスに関してはどんなささいなファクターも過不足なく取り上げられ、簡にして要を得た分析が加えられている。筆者の座右の書。翻訳に取り組む勇気のある出版社の出現を望む。
●ルイ=セバスチャン・メルシエ/原宏訳『パリの生活情景』(岩波文庫)
厳密に言えば、歴史書ではなく、一次資料だが、イギリスに遊学して相対性というものを身につけたメルシエは明らかに「現代の歴史家」と自らを位置づけて筆をとっている。つまりノン・フィクションやルポルタージュの走りなのだが、マスコミが発達してしまった現代は逆にこうした「現代の歴史家」の出現をさまたげてしまっているのではなかろうか。いずれにしろ、これなくしてはパリの社会史は成立しえぬ第一級の資料である。
●アンリ・マルレ絵、ベルティエ・ド・ソヴィニー文/鹿島茂訳『タブロー・ド・パリ』(新評論。藤原書店より再刊)
パリの国立図書館に眠っていた、王政復古期のパリを描いた石版画連作七十二枚をベルティエ・ド・ソヴィニーが発見して蘇らせた。オスマンの破壊する以前の街並を背景にして、働き、娯楽に興じる庶民の姿が、スナップショットのように捕えられている。自分で訳したからいうのではないが、この石版画連作は『モンタイユー』にも匹敵する発見である。
●バルザック/鹿島茂他訳「バルザック『人間喜劇』セレクション」(藤原書店)
十九世紀前半の歴史を知るにはバルザックを読むのが一番と言ったのは、マルクスだったかエンゲルスだったか。モノグラフィーであると同時に全体史であるという、アナール派的歴史書の定義を完璧(かんぺき)に満たしているのは、古今東西を通じてバルザックの総合的宇宙であるこの「人間喜劇」をおいてほかにない。いまや、新しい角度からバルザックを読み直す機運がたかまりつつある。
●ゾラ「ルーゴン=マッカール双書」(ほとんどが未訳)
十九世紀後半のフランスは、娼婦からナポレオン三世まで、デパートからパリの地上げまで、要するに、何から何までこの「ルーゴン=マッカール双書」の中にある。ゾラは、執筆に際しては、現場に赴き、綿密なノートを作成したので、史料的価値はきわめて高い。いずれ、本格的な紹介をするつもりである。〔後記。ゾラの没後百年を記念して、「双書」のほとんどが邦訳された〕
●オールティック/小池滋監訳『ロンドンの見世物』(国書刊行会)
まずは、このような驚くべき書物が翻訳されて、日本語で読めることに感謝すべきだろう。「見世物」という制度を、中世の聖遺物から万国博覧会まで、あらいざらい点検したこの本を読んでいると、びっくりするようなものを見てみたいという好奇心こそが、人間を人間たらしめている根源的な力ではないかという気がしてくる。
●スティーヴン・マーカス/金塚貞文訳『もう一つのヴィクトリア時代——性と享楽の英国裏面史』(中央公論社)
稀代(きたい)の奇書『我が秘密の生涯』の読解を中心に、金銭と精液の貯蓄を励行したヴィクトリア朝道徳の裏面を容赦(ようしゃ)なく暴き出す筆の冴えが何といっても痛快。ポルノグラフィーを分析する際のスタンスの取り方も絶妙で、ポルノと偽善的性道徳を通底させ、時代の共通したオブセッションをあぶり出してゆく。
●ダニエル・J・ブアスティン/新川健三郎・木原武一訳『アメリカ人——大量消費社会の生活と文化』(河出書房新社)
カウボーイやガンマンは、いかなる経済的要請によって生まれたのかとか、ラスベガスが離婚産業をもとに誕生したなど、現代アメリカの消費社会をその発生の必然性において捕えようとする試みは、はなはだ刺激的。こんなに面白い本が絶版になっているのはどうしたことか。早期の文庫化を望みたい。
●ディー・ブラウン/鈴木主説訳『わが魂を聖地に埋めよ』(草思社)
前出、ブアスティンの『アメリカ人』で、無人の荒野であるかのごとくに描かれた西部には、当然ながら、独自の文化を築いている先住民がいた。ディー・ブラウンは白人との条約会議で記録されたインディアンたちの発言を掘り起こし、残忍な野蛮人として害虫のように絶滅させられた、インディアンの高潔な魂の叫びを蘇らせる。『アメリカ人』と併せて読むこと。
●ワルター・クリヴィッキー/根岸隆夫訳『スターリン時代』(みすず書房)
この本を開いたときの衝撃を忘れることはできない。ジノヴィエフやカーメネフを「君がスパイだと自白すれば、それは社会主義の前進に役立つのだ」という倒錯した論理で落としたという箇所を読んだとき、書かれていることはすべて真実だ、と直感した。実際、ペレストロイカでクリヴィッキーの証言は百二十パーセント真実だったことが証明された。初版が翻訳された当時、偽書だと言うデマが公然と叫ばれ、日本のスターリニストたちによる圧力が出版社に加わって再版に三十年近い年月を要した。今後、スターリニズムの悪を暴く研究書は続々と刊行されるだろうが、スターリンの粛正が猛威をふるっていた一九三〇年代に書かれた本書をあえて五十冊に加えたい。
●ジョージ・オーウェル/橋口稔訳『カタロニア讃歌』(筑摩書房)
ファシストと戦うと同時に、スターリニストとも戦わなければならぬという絶望的状況がスペイン内戦の本質だった。したがって、六〇年代後半に、この本は、日本の大学のバリケードの中で、まさに我がことのように読まれていた。スペイン内戦は、ひとりオーウェルという証人を持っただけでも幸せである。
●バーネット・ボロテン/渡利三郎訳『スペイン革命——全歴史』(晶文社)
ヒュー・トマスの『スペイン市民戦争』に物足りなさを感じていた者にとって待ちに待った決定版研究書の翻訳である。これを読むと、スペインはファシスト化される選択肢と東欧諸国のようにスターリン化される選択肢のどちらを選ぶのが幸福だったのか、究極の設問をしたくなってくる。ここでも、クリヴィッキーの証言の正しさが証明されている。
●アミン・マアルーフ/牟田口義郎・新川雅子訳『アラブが見た十字軍』(リブロポート)
「明け方にフランク軍が到着した。たちまち大虐殺である」。聖地エルサレムを奪還するための十字軍も、アラブの側から見れば、金髪の蛮族「フランク」の理由なき侵略と虐殺でしかない。著者の記述は、いたずらに被害者意識を強調するのではなく、冷静にアラブ側の混乱を見据えている。湾岸戦争も、いずれこうした扱いをされるのかもしれない。
●エドワード・W・サイード/板垣雄三・杉田英明監修・今沢紀子訳『オリエンタリズム』(平凡社)
ヨーロッパ文化が十九世紀に、ロマン主義という形で蘇ったとするなら、そのカンフル剤のひとつは、まちがいなくオリエンタリズムであった。だが、オリエントの豊饒(ほうじょう)な富と文化は、それを理解できる西欧によってしか価値あるものにならないとするオリエンタリズムは、オリエントを永遠の隷属状態におくことになった。フーコーのディスクール理論を援用するサイードの議論は強引だが、いわんとするところは痛いほどよくわかる。
●岡田英弘『世界史の誕生』(筑摩書房)
水と油のように異質な地中海文明と中国文明を初めて一つのコンテクストで論ずることを可能にするもの、それは中央ユーラシアの遊牧民が行った定住地帯への進入の歴史であるとする著者は、モンゴル帝国を機軸にした世界史の構築を訴える。日本人には珍しい歴史の流れの読み替えを主張するその議論はまことに刺激的。
●阿部謹也『ハーメルンの笛吹き男』(平凡社)
ハーメルンの笛吹き男が連れ去った子供たちはどこへ行ってしまったのか。有名な民間伝承をめぐる様々な仮説を検討するうちに中世都市の下層民衆の生活がおのずと浮かび出てくるという巧みな構成が心にくい。暗い北ドイツから、さらに北へ植民を試みた中世賤民の苦しみが掬(すく)いとられ、読む者の心を打つ。
●宮下志朗『本の都市リヨン』(晶文社)
フランスの過去について考えるとき、我々が一番だまされてしまうのはいつの時代もパリが文化の中心だったわけではないということである。十五世紀から十六世紀にかけて、文化は出版・印刷・金融を中心としてリヨンから発信されていた。一次資料を駆使して、リヨン・ルネッサンスを、印刷・出版の観点から照射した力作。『書物の誕生』と併読すべし。
●角山栄・村岡健次・川北稔『産業革命と民衆——生活の世界歴史10』(河出書房新社)
いまでこそ**の社会史、**の文化史の花盛りだが、この本の書かれた一九七五年には、好事家的でない十九世紀生活史はまったくなかった。これを読んで目から鱗(うろこ)の落ちる思いがした人も多いだろう。同じ著者に名著『路地裏の大英帝国』があるが、日本におけるパイオニアということで、本書を取りたい。
番外
●『パリ——ミシュラン・グリーンガイド』(実業之日本社)パリの全歴史に関する本を一冊というのであれば、少し意外な選択かもしれぬが、このミシュラン・グリーンガイドを推す。とにかく、この小さなガイドブックに盛られたパリの歴史情報は並大抵のものではない。市販されているパリガイドのほとんどはこの本からの剽窃(ひょうせつ)でなりたっている。
●ジョン・マクドナルド/松村赳監訳・秦新二訳『戦場の歴史——コンピュータ・マップによる戦術の研究』(河出書房新社)
歴史は下部構造で動くとはいえ、戦場での勝敗が文明の運命を決するのもまた事実である。ところで、戦場での勝利は、つねに高地を制したほうへと傾く。とするなら、いくら平面図で戦場を研究しても埒(らち)はあかぬわけだが、ここに凸凹を自由自在に表現できるコンピュータ・マップという、まことに便利なものが登場した。ハンニバルのカンナエの戦いからディエン・ビエン・フーまで、自分が将軍になったような気持ちで「……たら」を連発し、パラレル・ワールドを夢想するのは楽しい。
【このコラムが収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする
初出メディア