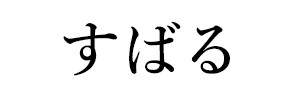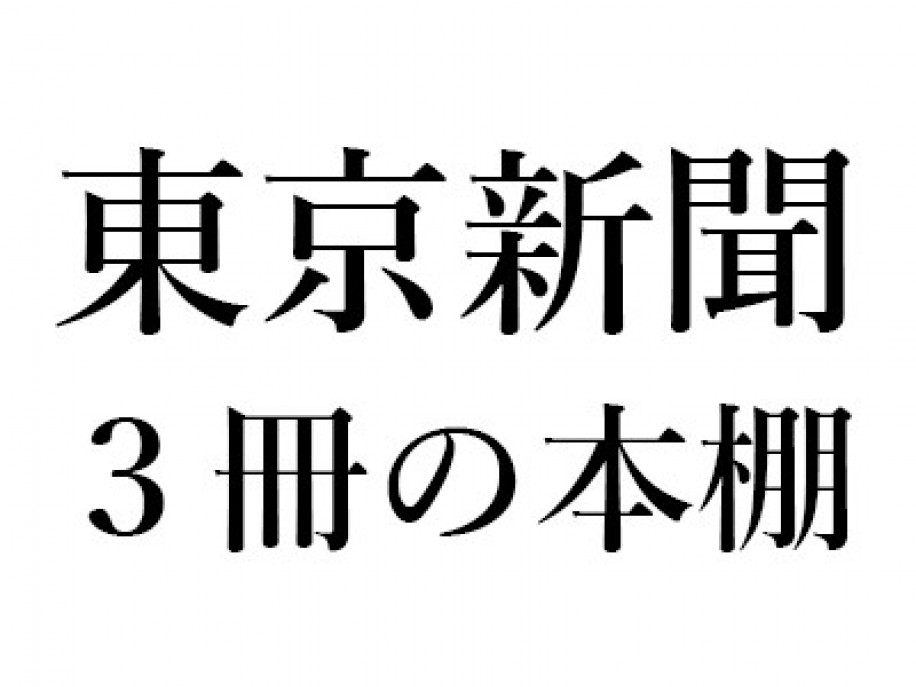読書日記
マックス・ブルックス『WORLD WAR Z』(文藝春秋)、オルダス・ハクスリー『すばらしい新世界』(光文社)、アガサ・クリスティー 『ナイルに死す』(早川書房)
読書日録
某月某日
豊洲のシネコンで映画『ワールド・ウォーZ』を観た足で、モール内の書店で原作小説『WORLD WAR Z』を購入。映画はブラッド・ピットが八面六臂の大活躍で世界をゾンビから救うが、原作は別物。英雄めいた主人公が登場しない群像劇である。中国の移植用臓器の国際販売や違法移民によって死体が生き返る感染症が広まり、世界は同時多発的なパニック=「Z(ゾンビ)戦争」に襲われる。
イスラエルは、防御のために都合のいいパレスチナ難民を受け入れる。イランとパキスタンは、これを機に核戦争に発展。韓国は北朝鮮の動向を過剰に警戒し、軍隊を国境沿いから動かせない。ゾンビパニックは、その国が抱える政治状況をあぶり出す鏡なのだ。
パニック後、人ロの多くを失った人類は、以前と違う世界を生きることになる。基軸通貨はキューバペソがドルに取って代わった。日本人は政府の指示を待つうちに事態が悪化、国土を放棄してカムチャツカに移住している。
人類は、この厄災を天罰や戒めと考える。戦争が絶えない人類への罰、または行き過ぎた消費社会への戒めとしても受け止める。ある登場人物は、BMWのZ4のボンネット上でセックスをするポルノビデオを観て思う。「もうこんな車、二度とつくれねえだろうなあ」
物語は無事ゾンビに対処した人類が、新しい世界をつくろうというところで終わる。ただし、ハッピーエンドなのかどうかは微妙だ。Z戦争後の世界を支配するのは宗教である。ロシアは宗教を主体に新体制を築き、旧帝国時代の領土を回復しようとする。日本では、盲目の武道家がつくるスピリチュアルな自営集団「盾の会」が支持を集めている。この厄災で人類は心を一つにした。だが、それが生むものは、ユートピアとは限らない。映画とは真逆の恐ろしい小説だ。
某月某日
地方出張のホテル及び移動の飛行機で新訳版のオルダス・ハクスリー『すばらしい新世界』を読む。エーコ『薔薇の名前』同様、何度も挫折した本だが新訳のおかげで初めて完読できた。T型フォード誕生を紀元とするフォード暦632年(西暦2540年)。この世界の子どもは人工授精により、試験管で「大量生産」され、国家によって育てられる。この制度の下では、親は存在しない。翻って親から受ける愛情の差もなければ虐待もない。さらには家族も存在しないし一夫一婦制も恋人もこの世界では歓迎されない。なぜならそれらは排他的だから。人類は、誰かを独占してはいけない。完全に平等な世界。しかし、階級は存在する。この世界では、下級の工場労働者は、あらかじめ能力が劣るように操作されて生まれてくる。さらに、赤ん坊の頃から本に近づくと、サイレンが鳴る部屋で教育を受ける。本を読むことは、「共同体にとって時間の無駄」だからだ。不平等な階級社会に見えるが、彼らは自分の階級に不満を持たないよう「睡眠教育」を施されている。
こういった階級の決定を担当する役所が「社会階級決定室」。ここには、88立方メートルの索引カード部屋がある。本作が書かれたのは1932年。IBM製のパンチカードによる情報管理システムはあれど、まだコンピューターが登場する以前の時代。観光も発展しつつある。この物語の登場人物たちは、ニューメキシコの「野蛮人居留地」に旅行に出かける。
彼らが利用する乗り物はロケット。他にもヘリコプターが登場する。これらの離発着は、高層ビルの屋上。1932年は、まだ飛行船が飛び交っていた時代。ヘリコプターは、実用前だった。
「継ぎはぎするより次々捨てよう」というのは、本書に何度も登場するこの世界の標語。大量生産・大量消費の理念が、宗教となり社会を駆動する社会。
某月某日
アガサ・クリスティーの1937年の作品『ナイルに死す』を読む。時代背景は大恐慌後の世界。イギリスの貴族階級は没落し、邸宅をアメリ力の新興の金持ちに奪われつつある。クリスティーは貴族ではないが資産家の娘。幼少時代、彼女の一家も屋敷をアメリカ人に貸して生活していた。
小説の舞台は、大観光ブームで賑わうエジプトはナイル河の客船。この船には、新婚旅行中の若い資産家の娘とその夫、富豪の老貴婦人、その付き添い看護婦、女流作家とその娘、英国特務機関員、そして探偵のポアロらが乗っている。そして、もちろん殺人が起こる。
再々々読目くらいの本作をいまさら読んだのは、『すばらしい新世界』との比較のためだ。クリスティーとハクスリーは同じ時代の同じ英国の作家である。通常、比較されるような作家ではないが。
比較すべきは、階級社会の在り方と観光ブーム。『ナイルに死す』のナイル河観光船は、一等、二等と階級に合わせて部屋割りがされ、観光者と従者の差が明確に描かれる。こうした格差の在り方に異を唱える共産主義者の若者も登場するが、クリスティーは彼を若気の至りとして冷ややかに描写する辺りが興味深い。
両作の上流階級がこぞって観光に出かけるのは、1930年代という時代背景あってのものだ。航空機や大観光船といった乗り物が発展し、富裕層は未開の第三世界に出かけていったのだ。そして、その自分たちだけが享受できる賛沢を味わうのだが、同時に後ろめたさも少しだけ顔を覗かせる。
奇しくも今夏公開のゾンビ映画と、風刺SFの古典が、グローバリゼーションと消費と宗教という主題で結びついてしまった。三四半世紀経っても、人類の課題はそうは変わってないということか。
ALL REVIEWSをフォローする