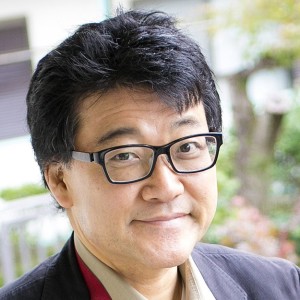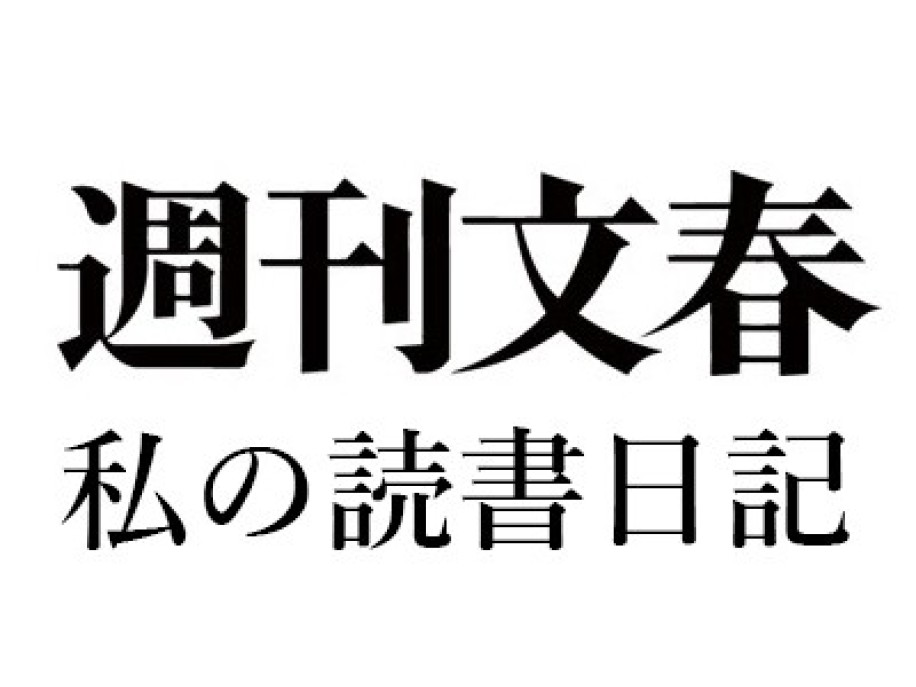前書き
『世界文学ワンダーランド』(本の雑誌社)
さて、右((ALL REVIEWS事務局注:前ページ)で述べたように、「文学は最高のエンターテインメント」「文学はなんでもあり、読みかたも自由」というのが、ぼくの考えである。しかし、世の中には「文学なんてつまらない」と思っている人が、あんがい多い。小説好きのなかにさえ「文学はどうもね……」という人がいる。
なぜだろう。どうして、多くの人が文学に、良くないイメージを抱いているのか。
答は簡単だ。面白い文学と出会っていないからである。「論より証拠」というが、証拠が見つからないので、論だけで「文学はつまらない」と決めつけてしまう。さらに原因を突きつめれば、論がネガティブへとむかうのを助長する風潮がある。ぼくのように「文学は面白いぞ」とハシャギまわるお調子者がもっといればいいのだけど、なぜか眉間に皺をよせて文学を語ったりする人が多い。それじゃダメだ。
具体的に犯人を示そう。「文学をつまらなくしている三悪人」である。
①国語担当の石頭教師
②ここ掘れワンワンの研究者
③半可通の文学ジジイ
こういう連中のおかげで、文学嫌いが増えてしまう。社会的な犯罪といってよかろう。
それぞれの罪状をみていこう。
①の教師。学校の教師というのは、人柄こそ悪くないのだが(悪いヤツもいますが)、頭がカタいというのが相場だ。自分が学校でおベンキョーしてきたことしか教えられないから、いまだにヘッセとかツルゲーネフとかを生徒に読ませようとする。読書感想文の課題図書で『車輪の下』を読まされて文学嫌いになった人間がどれだけいることか。まあ、ぼくは夏休みの宿題なんてサボってばかりだったので、『車輪の下』も読んじゃいないんですが。だいたい、国語の先生の役割は、あくまで国語(読み書き)を教えることである。だから、文学のことなんて聞きかじり程度しかわかっていない。これが美術の先生ならば、ピカソやデュシャンを知らないということは、まずなかろう。音楽の先生がジョン・ケージやスティーヴ・ライヒを知らないということも、ちょっと考えられない。しかし、ジョイスを読んでいない国語教師、ボルヘスを知らない国語教師、そんなのはごろごろいる。それ自体は、ちょっと恥ずかしいことだとしても、べつに責められるようなことではない。ただ、そのくらいの人たちが身のほども知らずに、若い世代にむけて文学を語っているとすれば問題だろう。あまつさえ、「この作者が伝えたいことは?」なんて問題を出している。ま、そういうおベンキョーが無益だとは言いませんが。社会に出ると、上司がごにょごにょ語るなかから真意を汲みとったり、クライアントが垂れながす繰り言を掻きわけてニーズを把握したりという、ノイズ除去のスキルが要求される。学生時代に「伝えたいこと」を理解する訓練をしておくのは、意味があることなのだ。しかし、そんなことは文学とはなんの関係もない。伝言ゲームじゃないんだからね。
②の研究者。おベンキョーが大好き人種で、世間的には「頭がいい」と思われていけれど、たいていはセンスが悪い。真面目ひとすじというならまだ救いがあるが、本人は面白い冗談を言っているつもりでまわりを白けさせているというのは、手の施しようがない。お笑いのセンスだけではなく、コモン・センスにも欠けている。典型的な勘違いは、文学研究の世界での価値が、そのまま世の中に通用すると思っているところだろう。この連中にとって文学を扱うのはお仕事なので、作品全体を楽しむことよりも、細部を掘りかえすことが大切だ。解釈や分析ってやつですね。彼らにとっては難解な作品のほうがありがたい。他人が容易に見つけられないものを自分が掘りだせば手柄になるからだ。ジョイスやカフカの作品なんて、まるで宝の山である。無我夢中のここ掘れワンワン状態で、ときには作者が埋めたはずがないものさえ掘りだしてみせる。たとえば、カフカはカバラ的な意味があるなんて言いだしたり。それはキミが自分で埋めたんじゃないの? しかし、これが考古学ならば大問題になるが、文学研究は発掘品の真贋はあまり問われない。自作自演であっても新奇なものが掘りだせれば、それが芸として認められるのだ。まあ、アカデミズムの閉じた世界で楽しくやっているぶんには害がない。ぼくたちが興味本位で、どんな発掘品が出ているかのぞきにいくのも暇つぶしにはなる。しかし、こういう人たちが文学作品の解説などで、ここ掘れワンワン根性丸だしで、偉そうに講釈を垂れていると、読者は引いてしまう。「深く掘らなければ(=解釈しなければ)文学は理解できない」なんて思うと、読むのがおっくうになってしまう。そんなことはぜんぜんないのに。
③の文学ジジイ。床屋で髪を切ってもらいながら、政治や世相について知ったかぶりで話している親爺ってよくいるでしょ。本人は「あえて苦言を呈す」とか「俺は一家言あるぞ」とか思っているのかもしれないけれど、端から見ると「きっと家じゃ相手されなくて、こういうところで憂さ晴らししているんだろうな」って御仁。話の内容も、テレビのコメンテイターが言っていることの引きうつしだったりして。文学ジジイってのは、その文学版だと思えばいい。ただ、さすがに床屋で文学の話をするわけにもいかない。文学ジジイのおもな棲息地は、やはり文学とか出版の世界になる。といっても、なにか役立つことをしているわけではなく、寄生しているだけだけど。むかしは、どの新聞社や雑誌編集部にも、こうした文学ジジイがいて、ちょっと目立つ小説や新しいタイプの小説にいちいちケチをつけていた。自分で短評を書いたり、かつての同人誌仲間に書かせたりで、まあ、文学青年くずれだから表現だけはもってまわっているんだけれど、ケチのつけどころは「人間が描けていない」の一辺倒。この連中が奉っているのは、太宰治とか志賀直哉とかそのあたりで、懊悩とか魂の彷徨とかが大好きなんだ。太宰や志賀が悪いとは言わないけれど(そもそもぼくはろくに読んじゃいない)、そんな竹槍みたいな価値観をふりまわされてもねえ。文学ジジイの発想「人間のほかに重要なものがあるのか?」は、床屋談義オヤジの「わが国が外国から攻撃されたらどうするんだ?」というのとおなじで、勢いだけは有無を言わさぬものがあるけれど、けっきょくは「重要だから重要だ」「大切なものは大切だ」というトートロジーである。まあ、頭が悪いだけならば可哀想ですむが、文学ジジイは性格も最悪だから度しがたい。他人が楽しそうにしているのがよほど気にくわないのか、SFやミステリを目の敵にする。「あんなものは文学じゃない」なんて、わざわざ文学に囲いをつくりたがる。ぼくは二十一世紀のいま、さすがに文学ジジイはもう絶滅危惧種だろうと思っていたのだが、大森望/豊崎由美『文学賞メッタ斬り!』を読むと、そうでもないらしい。文学賞選考委員のなか、しかも発言力が大きな人たちが、てんとして恥じず「人間が描けていない」的な発言を繰りかえしているのである。日本の文壇というのは、いまだに文学ジジイが偉そうにはびこり、ぽんこつの文学観が権威として通用させているのだ。そのマイナスのオーラが発散しているため、文学というのはジメジメした閉鎖的な世界だと思われてしまう。いやはや。
しかし、本書で紹介した作品を読んでもらえれば、国語教師、研究者、文学ジジイの言うことなど、いささかも気にすることがないことがおわかりになるだろう。むしろ、彼らを反面教師にするといい。「作者はなにかを伝えたがっている」「作品には隠された意味がある」「文学は人間を描くものだ」――こういう偏頗な読みかたに陥ってはいけない。
あわててつけくわえておくと、すべての国語教師が頭がカタいわけではなく、すべての研究者が犬だというわけではない。柔軟な思考ができる先生もいるし、文学を楽しむセンスにすぐれた教授もいる。もっとも、文学ジジイだけは、その存在性そのものが邪悪なので、例外はありえない。良い文学ジジイは死んだ文学ジジイだけだ。
ということなので、文学にネガティブなイメージを抱いている方は、それをリセットしていただきたい。キャベツになめくじがついていたからといって、キャベツを嫌いになることはないのだ。
(次ページに続く)
ALL REVIEWSをフォローする