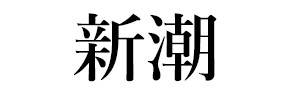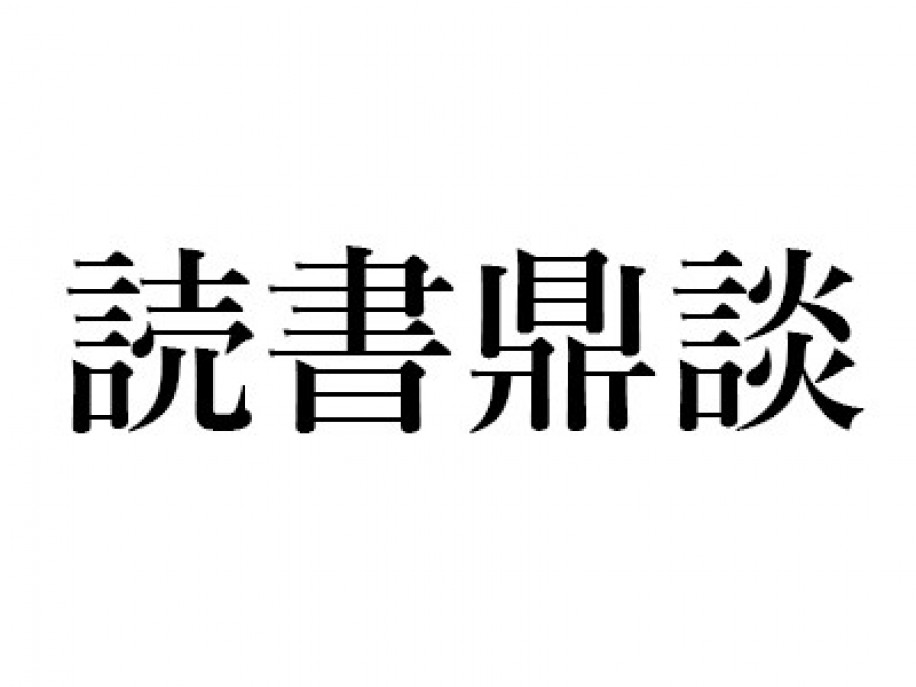書評
『ジャスミンを銃口に―重信房子歌集』(幻冬舎)
病人は俳句をよくし、囚人は短歌に秀でると、なかば冗談めかして教えられたことがあった。
闘病生活を続けていると、健康時にはなかなか気づかなかった四季の変化が、病室の窓から観察できるものである。おのずからそこに感興が生じ、季語を織りこんだ俳句が出来る。この世界には偉大なる原型的人物が存在している。いわずと知れた子規のことだ。それに比べて獄舎のなかにある者は、外界から遮断されているため、四季の趣を鑑賞することができない。加えて心中は孤独と悔恨、さらに冤罪から来る憤りなどで溢れきっている。その過剰な感情を盛りこむには、俳句では簡潔すぎて物足りない。やはりここは五七五の後に七七の余韻をもった短歌でなければならない。
俳句が目の前の光景をスナップショットのように切り取るとすれば、俳句よりも下句の分だけ長い短歌は、そこに喪われしものの映像と内面的な註釈とを加えることができる。ありえたかもしれないこと、もう永久に手の届かなくなってしまったことを表現するのに、この短詩形式は優れた機能をもっている。思い出してみれば、政治的志とその挫折を歌い上げることは、『万葉集』に収録された大津皇子以来、日本文学の伝統ではなかったか。重信房子の歌集『ジャスミンを銃口に』を読みながら、わたしはそのようなことを漠然と考えていた。
重信房子は1971年にベイルートに渡り、一時日本大使館で働いていたが、やがて日本赤軍の兵士としてパレスチナ解放闘争に身を投じた。当時の同志たちの多くはイスラエル軍に射殺されたり、ヨルダン官憲の拷問によって殺害された。彼女はやがて「国際テロ組織」の指導者として国際指名手配となり、2000年に日本に潜伏していたとき逮捕された。現在は東京拘置所にありなから、裁判闘争のさなかにある。検察側は1974年のオランダでの大使館占拠事件に共謀したという罪状で彼女を起訴しているが、当時の関係者のほとんどが死去しており、被告も証人も記憶が定かでないために、裁判は遅遅として進行していない。当時、重信の同志であり「ハイジャックの女王」として知られたライラ・ハリドは、裁判のためわざわざパレスチナから東京に赴き、証人として発言した。ライラは今ではパレスチナ国民議会(日本でいう国会)の議員であり、裁判長にむかって、重信にふさわしいのは刑罰ではなく褒賞であると宣言した。
わたしが重信の歌集をここで評価するのは、彼女が携わってきた「日本赤軍」というヴォランティア運動の政治理念に共鳴したからでも、反対したからでもない。また2004年にパレスチナの占領地を踏破して、イスラエル軍の住民への蛮行を目の当たりにしたからでもない。わたしの関心は純粋に美学的なものである。それはひとたび日本という国家から訣別を誓い、インターナショナリズムに挺身した人間が、それでも究極の心情を託すときに、律令時代に定型化された日本の韻律を採用したという事実を、韻律とは無縁の散文に生きる者として考えておきたかったからだ。ちなみに日本赤軍の同志であった足立正生もまた2005年、回想記を出版したが、こちらはピカレスク・ロマンを思わせる獄中記であった。
『ジャスミンを銃口に』は巧みに編集された歌集である。ベイルートに初めて到着し、恋人と廻(めぐ)りあったときの心の衝跳(ときめき)。戦いのさなかに次々と倒れてゆく同志たちへの挽歌。帰国後の獄中生活と、法廷で何十年ぶりかでなされた旧友たちとの再会。そしてベイルート以前の、東京でのバリケード闘争の回想などが、走馬灯のように現われては甘やかな余韻を残して消えてゆく。けっして骨太の、自信と決断に満ちた歌ではない。むしろ表題にあるように、ジャスミンの華奢な蔓のように幾重にも撓(しな)りながら、見果てぬ空に向けて触手を伸ばしてゆくような、爽快な植物的想像力のあり方が印象に残った。
初々しい感情と躍動感に満ちた恋歌である。重信は案外、俵万智の隣人なのかもしれない、だが幸福もつかの間、1982年にイスラエル軍がベイルートを急襲し、作者とその同志たちは抵抗も虚しくこの都を撤退しなければならなくなる。
「蕾のまま」に終ったのは、ベイルートに蒔いたコスモスばかりではない、作者がひとたび信じえた革命も、パレスチナ解放闘争も、いや彼女の人生そのものが、コスモス同様に「蕾のまま」に留まってしまったのかもしれないのだ。コスモスとはその後悔と無念さの象徴であるが、同時に亡き父親との信頼関係を確認する花でもあった。
ジェニンは2002年にイスラエル軍が侵攻し、パレスチナ側の発表では500人以上が虐殺されたと伝えられる、ヨルダン河西岸の町である。わたしが2年後に訪れたとき、難民キャンプの跡はすっかり更地となり、見渡すかぎり画一的な集合住宅が建築中であった。空はかぎりなく高い。というのもすべての建築が破壊されてしまったからである。
本来は大和の称号であるべき「まほろば」が、ここでは異邦パレスチナのために用いられている。なぜヤマトタケルの辞世の歌の記憶が、ここで参照されなければならないのか。パレスチナは大和なのか。『ジャスミンを銃口に』を日本語の歌集として成立させている重要な、つまり危機的な一点は、まさにここにある。それを思考することは、もはや重信の政治意識といった次元を越えて、日本文学における短歌的なるものの起源に関わっていることのように、わたしには思われる。
【この書評が収録されている書籍】
闘病生活を続けていると、健康時にはなかなか気づかなかった四季の変化が、病室の窓から観察できるものである。おのずからそこに感興が生じ、季語を織りこんだ俳句が出来る。この世界には偉大なる原型的人物が存在している。いわずと知れた子規のことだ。それに比べて獄舎のなかにある者は、外界から遮断されているため、四季の趣を鑑賞することができない。加えて心中は孤独と悔恨、さらに冤罪から来る憤りなどで溢れきっている。その過剰な感情を盛りこむには、俳句では簡潔すぎて物足りない。やはりここは五七五の後に七七の余韻をもった短歌でなければならない。
俳句が目の前の光景をスナップショットのように切り取るとすれば、俳句よりも下句の分だけ長い短歌は、そこに喪われしものの映像と内面的な註釈とを加えることができる。ありえたかもしれないこと、もう永久に手の届かなくなってしまったことを表現するのに、この短詩形式は優れた機能をもっている。思い出してみれば、政治的志とその挫折を歌い上げることは、『万葉集』に収録された大津皇子以来、日本文学の伝統ではなかったか。重信房子の歌集『ジャスミンを銃口に』を読みながら、わたしはそのようなことを漠然と考えていた。
重信房子は1971年にベイルートに渡り、一時日本大使館で働いていたが、やがて日本赤軍の兵士としてパレスチナ解放闘争に身を投じた。当時の同志たちの多くはイスラエル軍に射殺されたり、ヨルダン官憲の拷問によって殺害された。彼女はやがて「国際テロ組織」の指導者として国際指名手配となり、2000年に日本に潜伏していたとき逮捕された。現在は東京拘置所にありなから、裁判闘争のさなかにある。検察側は1974年のオランダでの大使館占拠事件に共謀したという罪状で彼女を起訴しているが、当時の関係者のほとんどが死去しており、被告も証人も記憶が定かでないために、裁判は遅遅として進行していない。当時、重信の同志であり「ハイジャックの女王」として知られたライラ・ハリドは、裁判のためわざわざパレスチナから東京に赴き、証人として発言した。ライラは今ではパレスチナ国民議会(日本でいう国会)の議員であり、裁判長にむかって、重信にふさわしいのは刑罰ではなく褒賞であると宣言した。
わたしが重信の歌集をここで評価するのは、彼女が携わってきた「日本赤軍」というヴォランティア運動の政治理念に共鳴したからでも、反対したからでもない。また2004年にパレスチナの占領地を踏破して、イスラエル軍の住民への蛮行を目の当たりにしたからでもない。わたしの関心は純粋に美学的なものである。それはひとたび日本という国家から訣別を誓い、インターナショナリズムに挺身した人間が、それでも究極の心情を託すときに、律令時代に定型化された日本の韻律を採用したという事実を、韻律とは無縁の散文に生きる者として考えておきたかったからだ。ちなみに日本赤軍の同志であった足立正生もまた2005年、回想記を出版したが、こちらはピカレスク・ロマンを思わせる獄中記であった。
『ジャスミンを銃口に』は巧みに編集された歌集である。ベイルートに初めて到着し、恋人と廻(めぐ)りあったときの心の衝跳(ときめき)。戦いのさなかに次々と倒れてゆく同志たちへの挽歌。帰国後の獄中生活と、法廷で何十年ぶりかでなされた旧友たちとの再会。そしてベイルート以前の、東京でのバリケード闘争の回想などが、走馬灯のように現われては甘やかな余韻を残して消えてゆく。けっして骨太の、自信と決断に満ちた歌ではない。むしろ表題にあるように、ジャスミンの華奢な蔓のように幾重にも撓(しな)りながら、見果てぬ空に向けて触手を伸ばしてゆくような、爽快な植物的想像力のあり方が印象に残った。
咲きのぼるブーゲンビリアの緋の塀を曲がればいつも君に出会った
ジャンプして高々と挙げた指先で椀(も)いだオレンジ私に投げた
初々しい感情と躍動感に満ちた恋歌である。重信は案外、俵万智の隣人なのかもしれない、だが幸福もつかの間、1982年にイスラエル軍がベイルートを急襲し、作者とその同志たちは抵抗も虚しくこの都を撤退しなければならなくなる。
戦場に蒔いたコスモス夢にゆれ蕾のままに離れた街よ
「蕾のまま」に終ったのは、ベイルートに蒔いたコスモスばかりではない、作者がひとたび信じえた革命も、パレスチナ解放闘争も、いや彼女の人生そのものが、コスモス同様に「蕾のまま」に留まってしまったのかもしれないのだ。コスモスとはその後悔と無念さの象徴であるが、同時に亡き父親との信頼関係を確認する花でもあった。
パレスチナわがまほろばの崩れゆく空のみ高しジェニンの町よ
ジェニンは2002年にイスラエル軍が侵攻し、パレスチナ側の発表では500人以上が虐殺されたと伝えられる、ヨルダン河西岸の町である。わたしが2年後に訪れたとき、難民キャンプの跡はすっかり更地となり、見渡すかぎり画一的な集合住宅が建築中であった。空はかぎりなく高い。というのもすべての建築が破壊されてしまったからである。
本来は大和の称号であるべき「まほろば」が、ここでは異邦パレスチナのために用いられている。なぜヤマトタケルの辞世の歌の記憶が、ここで参照されなければならないのか。パレスチナは大和なのか。『ジャスミンを銃口に』を日本語の歌集として成立させている重要な、つまり危機的な一点は、まさにここにある。それを思考することは、もはや重信の政治意識といった次元を越えて、日本文学における短歌的なるものの起源に関わっていることのように、わたしには思われる。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする