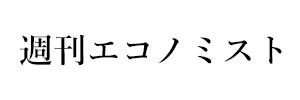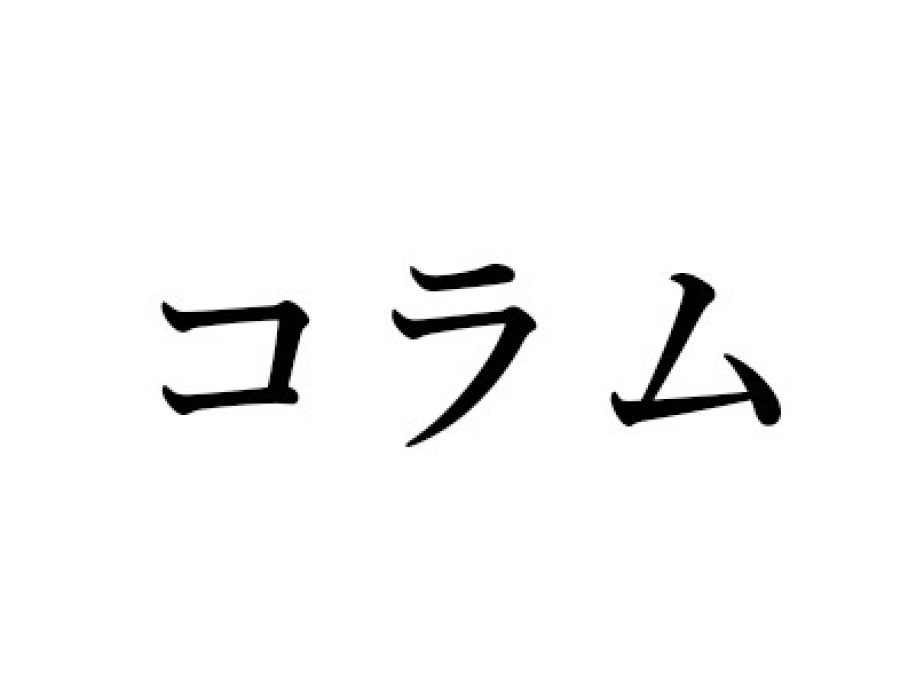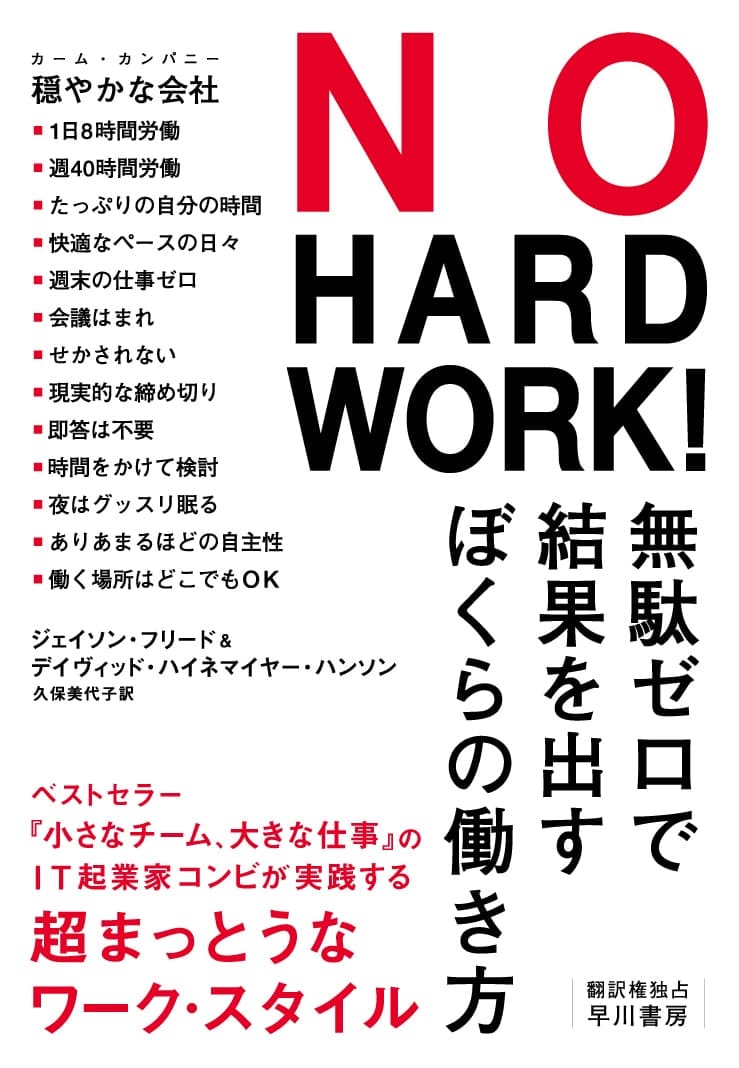書評
『売る力 心をつかむ仕事術』(文藝春秋)
カリスマ経営者が明かす不動点としての「論理」
タイトルにあるように、売上規模9兆円のセブン&アイ・ホールディングスの舵取りをする著者が「ビジネスの秘訣」を開陳する。しかし、それは表面に過ぎない。表面だけをみて飛びつくとけがをする。本書は徹頭徹尾「論理の書」である。なぜ論理が大切なのか。それが「変わらないもの」だからだ。商売を取り巻く現象や環境は刻々と変化する。「おいしいものほどすぐ飽きる」「真の競争相手は競合他社ではなく、絶えず変化する顧客ニーズ」と言い切る著者にとってはとりわけそうだ。しかし、だからこそ、不動の軸足としての論理が必要になる。論理は「視点」といってもよい。視点を固定せずに変化し続ける現象を追いかけてしまえば、目が回るだけだ。有効なアクションは打てない。
著者は「視点」と「ネタ」という言葉を使って説明する。その年の流行語になるような「ギャグ」を生み出しても、それはひとつの「ネタ」でしかない。すぐに飽きられる。なぜビートたけしが飽きられないのか。その時点で話題になっていることを「ネタ」にするにしても、ビートたけしは必ずそれを自分の「視点」を通して表現する。本当に面白いのは彼の「視点」で「ネタ」ではない。だから、飽きられない。
著者の経営の根幹にある論理を一言でいえば、「すべてをお客様の立場で考える」、これに尽きる。本書を一読して気づくのは、40年前のセブン-イレブンの設立以来、著者がこのこと「だけ」をやってきた、ということだ。そこに凄みを感じる。
顧客の立場で考える。言葉にすれば当たり前の話だ。ところが、これがやたらに難しい。売り手の視点と顧客の視点は往々にして正反対になる。売り手の立場で「合理性」を追求すればするほど、顧客の視点から離れることになる。
例えば、「完売」。商品が完売すると、売り手は自分たちに「売る力」があると考える。しかし、顧客の立場に立てば、完売は「欠品」。売り手の立場に立てば、とりあえず廃棄ロスをなくそうとするのが人情だ。これに対して、著者は機会ロスを小さくすることこそが顧客視点の経営だと考える。この論理が「単品管理」「仮説検証型発注」を生み出し、セブン-イレブン成長の原動力となった。
論理あっての「ネタ」なので、本書に盛り込まれた「ビジネスの秘訣」をそのまま取り入れても成功するとは限らない。しかし、論理の大切さはいやというほどよくわかる。自分の仕事を貫く不動点としての論理は何か。自問自答しながら読むことをお勧めする。
ALL REVIEWSをフォローする