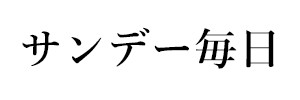書評
『いつかぼくが帰る場所』(早川書房)
いつか終わりがくる だからこそ美しい
血液感染の病気が世界に蔓延(まんえん)し、人類のほとんどが滅びてから九年。主人公のヒッグは、小さな飛行場で古いセスナ機と愛犬を友として多くの襲撃戦を生き延びてきた。それは、超一流の射撃の腕を持つユーモアを解さない気難しい隣人バングリーのおかげだった。食糧の確保、菜園作り、釣りや狩りの遠出、忍び寄る略奪者を発見するための飛行などには、頼りになる愛犬を必ず伴い、話しかけ続けていた。過去の人生と、人類が危機に陥った未来のない現在を心の中で行き来しながら、自分がなんのために生きているのかとヒッグは自問する。しかし、人のいない広大で美しい空間を空から眺めれば、この世界にいることの喜びを感じる。ある日、ヒッグの無線に管制官らしい者の声が届く。どこかの空港に人がいるというメッセージだった。地球の終末を描いたコーマック・マッカーシーの『ザ・ロード』と似ているが、灰色に塗り固められて色が消えていた『ザ・ロード』とは違い、ヘラーの描く世界には豊かな色彩と自然の美しさが際立つ。それは、そこに人がいないということの美しさでもあり、それが文明へのかすかな批判とも受け取れる。
登場人物がわずかなのに、ヒッグの一人称による語りから成るこの物語が読み手の心を掴(つか)んで離さないのは、鳥のように舞い上がって観察する目から描かれる世界と、ヒッグの揺れ動く心の風景が絶妙な調和を生み出しているためである。無線の「声」の主を求めて飛行場を出てからの展開は、手に汗握るどころの話ではない。
生き延びるために人間は神のルールさえ破る逞(たくま)しさと痛ましさを持つ。それでも人間の崇高な部分は失われない。この世界は滅びる運命であるが故に美しいことを、本書は訴えている。
ALL REVIEWSをフォローする