書評
『インディヴィジュアル・プロジェクション』(新潮社)
インディヴィジュアルは「個人的な」という意味でいいとしても、プロジェクションには様々な意味がある。「計画」であると同時に、心理学の世界では「主観の客観化」を意味し、また映画用語としては映像技師のことをプロジェクショニストというくらいだから「映写」という意味になる。そして、本書の語り部オヌマはまさしく映写技師であり、物語はオヌマの日記(つまり主観を客観化するための装置)という形で進行していくのだ。なかなか凝ったタイトルではないか。そして、ストーリーもまた。
映画学校の卒業制作のため、仲間と共に高踏塾というスパイを養成する私塾を取材したオヌマ。しかし、オヌマたちはやがて当初の目的から離れて、塾生として訓練を受けるようになる。その後、ある事件をきっかけに塾を出て、渋谷の古い映画館で映写技師の職を得たオヌマだが、塾での訓練を忘れず、いつでも戦闘可能状態にある。というのも、彼とその仲間は塾生時代にプルトニウムに関する謎を共有しており、いつそれをめぐって重大かつ深刻な事件が起こるかわからないからだ。やがて、オヌマの身にも危機的状況が訪れ――。
が、物語の後半に至って突然世界に歪みが生じるのである。語り部であるオヌマの現実認識と、彼の外部にあるリアルにどうもズレが生じているようなのだ。とすると、この日記の信憑性自体が疑わしいものに思われ、読者は現実(あるいは真実)と信じきっていた世界が実は虚構だったのかもしれないという目眩(めまい)にも似た感覚に襲われる。しかし、その目眩にも似た感覚こそが、わたしや、多分あなたも折にふれては感じている、情報過多によって生じる何が本当で何がウソなのか判然としないといった認識の揺らぎそのものを示唆してはいないだろうか。
と同時に、暴力的な現実がオヌマの正常な思考能力に齟齬(そご)を与えたのだとすれば、この小説はまさしく現代という時代に膿(う)む病根そのものを照射した作品ですらあるといえる(そういえばプロジェクションには「投影画」という意味も)。これほどまでにニッポンの現在と真っ直ぐ向き合い、しかも現代文学にとって必要不可欠な仕掛けを凝らした作品が近年あったろうか。若い世代にとりわけ読んでもらいたい一冊だ。自分が日々感じているやり場のない苛立ちの意味がわかるはずだから。
【この書評が収録されている書籍】
映画学校の卒業制作のため、仲間と共に高踏塾というスパイを養成する私塾を取材したオヌマ。しかし、オヌマたちはやがて当初の目的から離れて、塾生として訓練を受けるようになる。その後、ある事件をきっかけに塾を出て、渋谷の古い映画館で映写技師の職を得たオヌマだが、塾での訓練を忘れず、いつでも戦闘可能状態にある。というのも、彼とその仲間は塾生時代にプルトニウムに関する謎を共有しており、いつそれをめぐって重大かつ深刻な事件が起こるかわからないからだ。やがて、オヌマの身にも危機的状況が訪れ――。
が、物語の後半に至って突然世界に歪みが生じるのである。語り部であるオヌマの現実認識と、彼の外部にあるリアルにどうもズレが生じているようなのだ。とすると、この日記の信憑性自体が疑わしいものに思われ、読者は現実(あるいは真実)と信じきっていた世界が実は虚構だったのかもしれないという目眩(めまい)にも似た感覚に襲われる。しかし、その目眩にも似た感覚こそが、わたしや、多分あなたも折にふれては感じている、情報過多によって生じる何が本当で何がウソなのか判然としないといった認識の揺らぎそのものを示唆してはいないだろうか。
と同時に、暴力的な現実がオヌマの正常な思考能力に齟齬(そご)を与えたのだとすれば、この小説はまさしく現代という時代に膿(う)む病根そのものを照射した作品ですらあるといえる(そういえばプロジェクションには「投影画」という意味も)。これほどまでにニッポンの現在と真っ直ぐ向き合い、しかも現代文学にとって必要不可欠な仕掛けを凝らした作品が近年あったろうか。若い世代にとりわけ読んでもらいたい一冊だ。自分が日々感じているやり場のない苛立ちの意味がわかるはずだから。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
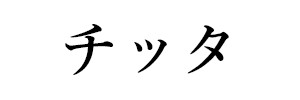
チッタ(終刊) 1997年10月
ALL REVIEWSをフォローする







































