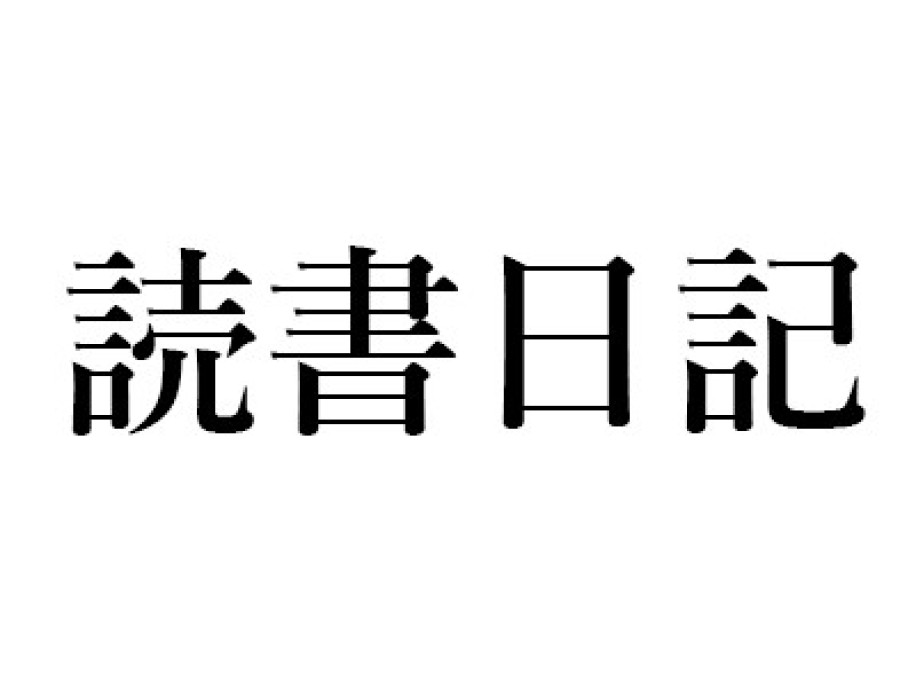書評
『私説東京放浪記』(筑摩書房)
東京グラフィティ
東京中の新奇なモノを集めた本も、文学の記憶をちりばめた本も、知識は与えられてありがたいと思うけど、感性をゆすぶられた経験はあまりない。が、これは……あっさりした仕立てながら、のっけから涙が出そうになった。著者自身が建て替えるはずの家の建築費が二割増しになってしまったのだ。がーん。
当時、ぼくは『環状七号道路の内側をすべて高層建築にする』という中曽根談話を読み、胆を冷やしていた。地方から出てきた、東京を〈出世の場〉としか考えていない人間でなければできない発想である。中曽根は、上北沢にある広大な長嶋茂雄邸を仮の住まいにしていた。
よくぞ言ってくれました。本書は一九八〇年代の地上げ=バブルによってがたがたにされた東京の姿を、自分の時間軸にそった放浪にからませてまとめている。現在の多くの東京論に欠けているのは、このまっとうな怒りと危機意識ではないだろうか。
比較したら悪いけど、サイデンステッカー氏の『立ちあがる東京』は震災以降の東京の文化史として労作ではあるし下町の衰退への哀惜もにじむ。が原宿で踊り狂う若者を「今の踊りは、むしろ平和と繁栄のもたらす倦怠、毎日の仕事や家庭の退屈にたいする反抗であるかもしれない」程度では、あまりに第三者的で皮相だと思う。こんな隔靴掻痒の日本論より、小林さんのきちんと足で歩いた、ワサビの効いた内在的な東京論の方が、よほど腹の足しになる。
いやいや、そんな固くるしい本ではありません。
日本橋の「コーヒーの快生軒の近くには、谷崎潤一郎生誕の碑がある」から見落とさないように、とか渋谷のビデオ屋〈SUMIYA〉は商品知識の点でおすすめ、など浴衣がけの気楽な文体で語った実用東京案内でもある。
東京では現在、中曽根民活=バブルによる〈町殺し〉とそれゆえ人々が〈下町幻想〉をもって走るレトロブームの二つの事態が同時進行中である。むろん、ことの重大さは比率として百対一くらいのものですが。小林さんは、その中でどう町が変わり、記号化されたか、盛り場の栄枯盛衰も長いスパンで見ている。たとえば――
東京ディズニーランド――五十年前の浅草松屋の〈ミッキー横丁〉と通ずるかなしさ。そこにいる間だけ憂さを忘れられるという点で。
赤坂――お座敷中華、ギンギンの本場焼肉屋のある不屈のオヤジ城。
新宿――のべつ工事中の町。赤線と映画の町、東口からオフィスの西口副都心へを完成させた愚挙が都庁。
上野――下手にいじるとよけいひどくなる。
こうしてダイジェストしてみると、イロニーも感じられるし、なにより正確だ。これ以前、高度成長が東京をいかに破壊したかを反語的タイトルでつづった『私説東京繁昌記』(写真・荒木経惟)も同じ出版社から新版が出た。
東京について書く文章は、怒りと喜びに彩られる。東京の現在を考えると、怒りがこみ上げる。未来を考えると絶望し、はるかな過去を想い出すと、喜びを覚える。
じつに共感するが、私はもう、絶望することに絶望したい。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする