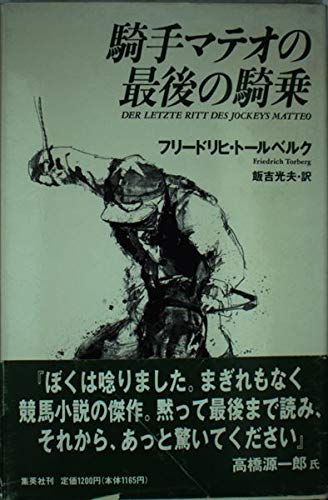書評
『四人の交差点』(新潮社)
フィンランドのベストセラー。秘密と企みに満ちた百年の物語
十月下旬、東京・下北沢の書店「B&B」で、来日中の著者とのトークイベントの機会をもった。本作『四人の交差点』は、フィンランドで刊行されるなり、ベストセラーランキングで十三週連続第一位を記録、多くの文学賞を受賞した話題のデビュー作である。トンミ・キンヌネン氏は1973年、フィンランド北東部生まれ。穏やかで謙虚なお人柄で、初対面にもかかわらず、肝胆相照らす対話をさせていただいたことに感謝が募ったが、収穫は、それだけではなかった。
キンヌネン氏の言葉は誠実そのものだが、ときおり微妙に謎めく気配が感じられ、私はおおいに納得を覚えた。ある秘密を押し隠しながらフィンランドに生きる家族の百年を描き出す本作には、巧緻な仕掛けがほどこされている。いよいよ終盤、すべてが白日の下に晒(さら)されるとき、想像さえ許されなかった衝撃的な展開に息をのみ、と同時に、読者は「小説を読む喜び」に打ち震える。驚くべき手法によって符合する、男女の深い孤独と密(ひそ)かな悦(よろこ)び。よほど企(たくら)みに充ちた作家でなければ、到底叶(かな)わない構想である。
ひとつの「家」に関わる四人の男女が三世代にわたって登場、それぞれの視点によって物語が語られる。助産師マリア、その娘の写真技師ラハヤ、ラハヤの息子の妻カーリナ、ラハヤの夫オンニ。助産師マリアは、二十世紀の初め、未婚のまま娘を生み、女手ひとつで育てながら家長として家を守る。ときに暴力的とも映る激しさを見せながらフィンランドの激動の時代をくぐり抜けるマリアの姿は、百年を貫く生のエネルギーの化身であるかのようだ。登場する三人の女たちは、母、娘、嫁としておのおのの立場は違いこそすれ、懸命に自分の人生を生きようと格闘し、破壊と再生の物語を紡いでゆく。いっぽう、唯一の男性であるオンニは、受難の十字架をみずから背負い、懸命に運命を生きようとするのだが――。
四人の視点によって語られる四つの物語は、複雑なずれと重層感を生みだし、不穏な響き合いを生む。彼らは、それぞれの感情や心の傷を秘密裏にしまいこむので、物語はやすやすと輪郭を表してはくれない。語れば語るほど何かがくぐもってゆくのは、フィンランドの人々の気質でもあるのだろうか。閉じられたぶ厚い木の扉の向こうから、悲痛を帯びたかすかな叫び声が洩(も)れ聞こえてくる。しかし、奇妙なことに、その声はどこかほの温かく、血の通ったぬくもりを感じさせ、読者を惹(ひ)きつけてやまない。
本作の主題は「家」である。「家」という存在は血縁のシンボルなのだろうか。キンヌネン氏に問うと、そうではなく、あくまでも生活を営む場としての“建物”であるとのことだった。また、自分は「家」という歴史のなかの一部分でありたい、とも。木と釘(くぎ)によって築かれた堅牢(けんろう)な建物は、強靱(きょうじん)な意志をもって生きようとするフィンランドの人々の舞台でもあるだろう。
百年の物語について、キンヌネン氏のこの言葉がとりわけ耳に残った。
人は、語られる限り死なない。語られることで人は生き続けるのだと思います
物語を紡ぐことの本質を捉える大切な言葉だと思った。
ALL REVIEWSをフォローする