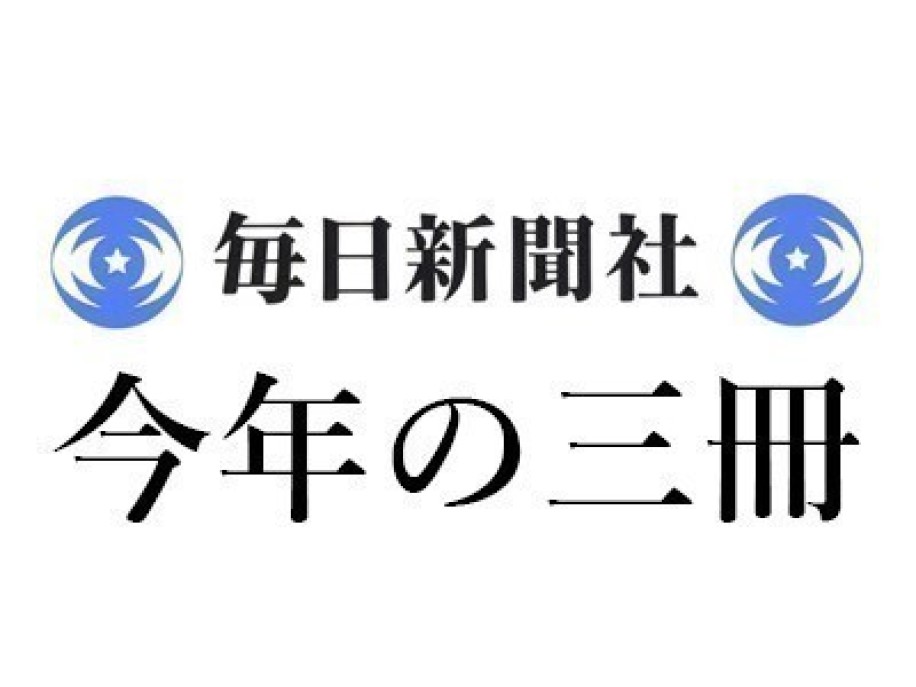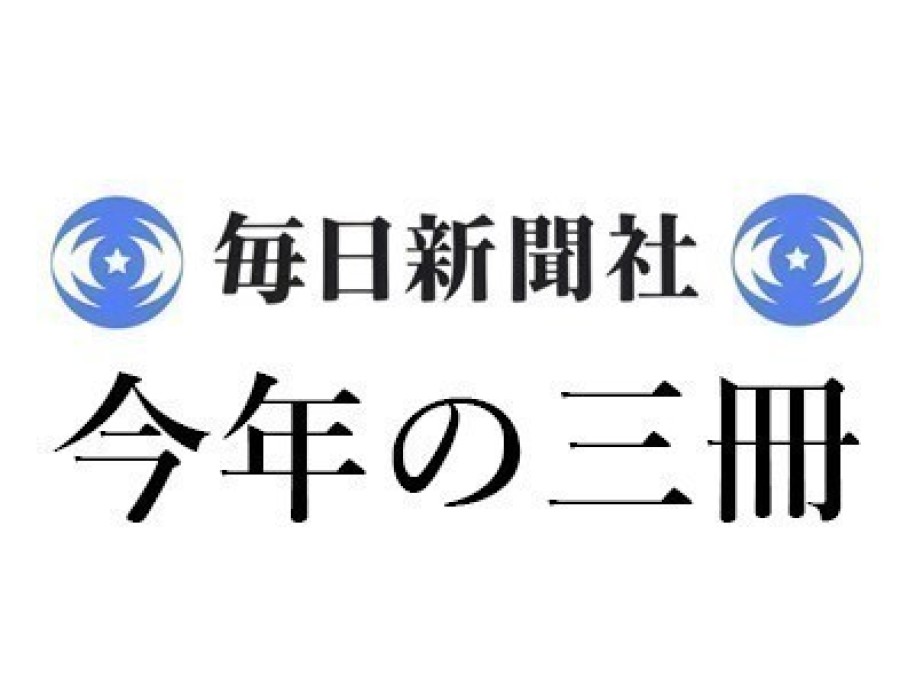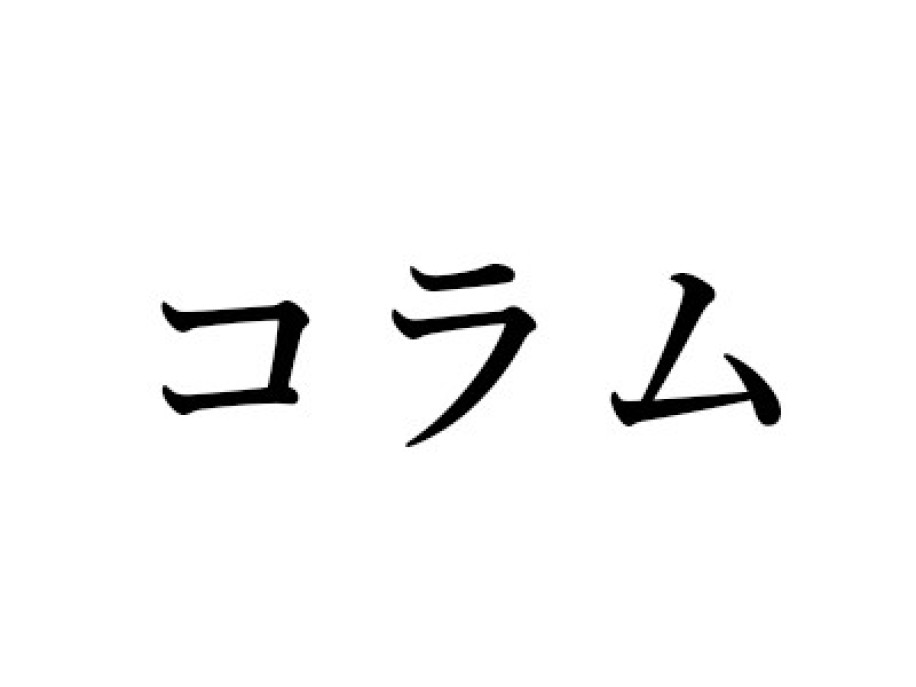書評
『日時計の影』(みすず書房)
中井久夫の本を読むと、いつも不思議に引き込まれてしまう。ほんらい専門がまったく違うし、精神医学は自分の個人生活からもほど遠い。だが、その本に接すると、思いもかけないことを教えられ、はっとさせられることがしばしばある。
この最新のエッセー集は多彩な内容からなる。精神医学に関する文章あり、人物の回想と過去の追憶あり、日々の随想や文学論あり、さらには訳詩も収録されている。扱う内容は一見ばらばらのようだが、意外にも互いに照応していて、巧く調和が取れている。精神科医としての仕事や文筆活動の幅広さを示すと同時に、若い頃からの思索の道程を振り返る構成にもなっている。ただ、それは時系列ではなく、過去と現在を自由に往還するなかで、その医療思想がどのように醸成されたかが示されている。
精神医学のことについて語りながら、文章のいたるところに哲学的思考がきらめいている。統合失調症、心的外傷後ストレス障害から認知症にいたるまで、精神的な不調や疾患を孤立した事象として見るのではない。人間の精神と身体を一つの統一体としてとらえ、他者との関係性において観察する。健常と異常をはっきりした一線で区分するのではなく、両者のあいだの連続性もつねに視野に入れている。
その仕事ぶりを見ると、何となく東洋の学問を想起する。江戸時代の日本でも、清代以前の中国でも医者は同時に儒者でもある。中井久夫も医者であると同時に、翻訳家であり文筆家でもある。狭い専門知識にとらわれず、より広い目、優しい目で人間を見る姿勢は人文学の厚い素養と寛容な精神に裏打ちされたものであろう。
中国には「病いを治すには先(ま)ず心を治すべし」(治病先治心)ということわざがある。心の治療とは患者の信頼を得ることであり、自信と希望を持たせることである。「患者の自尊心」や「自然の治癒力」を重視する中井久夫の学説はまさにそれを理論化したものと言える、精神科にかぎらず、医療全般にとって必要な知見だと思う。
おそらく情の厚い方であろう。認知症についての、「『知』がおおまかになっても『情』と『意』は残る。『情』がいちばん最後まで残る」というくだりを読んで感動すら覚えた。近代医学では誰も注意を払わなかったが、中井久夫の医療思想の特徴として「情」に対する注目が挙げられる。
「建物は正面だけでよいか」という文章のなかで、教育における「情」の大切さを指摘した。国数理社英の五教科が建物の正面とすれば、家庭科と図工など「情」を表現する「実技教育」は建物の側面である、正面ばかりの家は立っておれまい、と喝破したところはいかにも中井久夫らしい。
そういえば、知人や友人の回想録が情感に富んでいるのは、「情」を大切にする心のあらわれなのであろう。その文明批評が肯綮(こうけい)に中(あた)り、非常に説得力があるのも、文章の奥底に細やかな「情」の水脈が静かに流れているからである。
文学好きの一人として、ギリシャ詩人オディッセアス・エリティスの訳詩「アルバニア戦線に倒れた少尉にささげる英雄詩」に出会えたのはうれしい。エーゲ海の日射しを思わせるような激情が典雅な日本語で巧みに再現されている。「ヴァレリーとわたし」は甲南高校の時代にさかのぼって、このフランス詩人との出会いを語って面白い。ポール・ヴァレリーの訳詩とともに著者の精神世界の一端を知る手がかりになっている。
【この書評が収録されている書籍】
この最新のエッセー集は多彩な内容からなる。精神医学に関する文章あり、人物の回想と過去の追憶あり、日々の随想や文学論あり、さらには訳詩も収録されている。扱う内容は一見ばらばらのようだが、意外にも互いに照応していて、巧く調和が取れている。精神科医としての仕事や文筆活動の幅広さを示すと同時に、若い頃からの思索の道程を振り返る構成にもなっている。ただ、それは時系列ではなく、過去と現在を自由に往還するなかで、その医療思想がどのように醸成されたかが示されている。
精神医学のことについて語りながら、文章のいたるところに哲学的思考がきらめいている。統合失調症、心的外傷後ストレス障害から認知症にいたるまで、精神的な不調や疾患を孤立した事象として見るのではない。人間の精神と身体を一つの統一体としてとらえ、他者との関係性において観察する。健常と異常をはっきりした一線で区分するのではなく、両者のあいだの連続性もつねに視野に入れている。
その仕事ぶりを見ると、何となく東洋の学問を想起する。江戸時代の日本でも、清代以前の中国でも医者は同時に儒者でもある。中井久夫も医者であると同時に、翻訳家であり文筆家でもある。狭い専門知識にとらわれず、より広い目、優しい目で人間を見る姿勢は人文学の厚い素養と寛容な精神に裏打ちされたものであろう。
中国には「病いを治すには先(ま)ず心を治すべし」(治病先治心)ということわざがある。心の治療とは患者の信頼を得ることであり、自信と希望を持たせることである。「患者の自尊心」や「自然の治癒力」を重視する中井久夫の学説はまさにそれを理論化したものと言える、精神科にかぎらず、医療全般にとって必要な知見だと思う。
おそらく情の厚い方であろう。認知症についての、「『知』がおおまかになっても『情』と『意』は残る。『情』がいちばん最後まで残る」というくだりを読んで感動すら覚えた。近代医学では誰も注意を払わなかったが、中井久夫の医療思想の特徴として「情」に対する注目が挙げられる。
「建物は正面だけでよいか」という文章のなかで、教育における「情」の大切さを指摘した。国数理社英の五教科が建物の正面とすれば、家庭科と図工など「情」を表現する「実技教育」は建物の側面である、正面ばかりの家は立っておれまい、と喝破したところはいかにも中井久夫らしい。
そういえば、知人や友人の回想録が情感に富んでいるのは、「情」を大切にする心のあらわれなのであろう。その文明批評が肯綮(こうけい)に中(あた)り、非常に説得力があるのも、文章の奥底に細やかな「情」の水脈が静かに流れているからである。
文学好きの一人として、ギリシャ詩人オディッセアス・エリティスの訳詩「アルバニア戦線に倒れた少尉にささげる英雄詩」に出会えたのはうれしい。エーゲ海の日射しを思わせるような激情が典雅な日本語で巧みに再現されている。「ヴァレリーとわたし」は甲南高校の時代にさかのぼって、このフランス詩人との出会いを語って面白い。ポール・ヴァレリーの訳詩とともに著者の精神世界の一端を知る手がかりになっている。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする