書評
『1995年1月・神戸――「阪神大震災」下の精神科医たち』(みすず書房)
阪神大震災の記録
『1995年1月・神戸――「阪神大震災」下の精神科医たち』(みすず書房)は、あの未曾有の災厄のあと、最初の充実した本だと思う。とりわけ被災者の心理的ケアという、これから長くつづく問題を専門家たちが深く描いている(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1995年)。冒頭の中井久夫氏の「災害がほんとうに襲った時」は稀代の名文家による阪神大震災の記録という点でも、その類まれな客観性においても、精神科医という職業的自覚による活動と自己分析の記録という点でも、類を見ないものである。心に残ったフレーズを抄録することが許されるだろうか。
……睡眠薬をのんでいたためもあってあの二〇秒はグリセリンの中で強制的にトランポリンをさせられている感じであった。……この被害のなさは後に「申し訳ない」という罪悪感を私の中に生むことになる……私は東京経由で事態を知った……公衆電話優先や回数の間引きは、それだけの骨を折る気のない、動機の弱い通話を淘汰する巧みな方法であった……エネルギーを蓄え、「頭をぶらぶらにしておく」ことがまず必要であった。……被災ナースは百人を越えた。……樹の倒壊は実に一本も目撃していない。……近くに見える山と海とは私に大きな精神的な安定感を与えた。……
著者は酸鼻な光景を見ることは、指揮に当たる者の判断を情緒的にすると町には出なかった。地上の苦悩を知らぬげに飛び回るマスコミのヘリコプターが憎悪の対象となった。暖房の切れた病院に、作家で精神科医である来援者、加賀乙彦氏の運んだ花束がいかに「温かさ」をもたらしたか。避難民からは突き上げられ、行政の支援は薄く、授業再開がプレッシャーとなっている避難先の校長や先生方の心理的危機をどうするかということ。何より、不眠不休で働く医師やナースの多くも被災者なのである。私は手に汗を握りながら読みつづけた。ところどころで不覚にも涙がこぼれた。
続く四十人近くの来援医はじめ関係者の手記も感動的である。避難所で「他の人に悪口をいわれている」と集団で自殺を図ったケースがあるかと思えば、ケアに来た医者にコーヒーを出し、果物やお菓子を持っていけ、という被災民もいた。「抱え環境」である家に潰され、家を失った人びと。
初期に人びとはやや退行し、やさしくなり、あるいは英雄的になったという。日常にない共同体感情が生まれた。そうした「ハネムーン状態」が終わるころ、人びとの幸不幸の格差は目立ちはじめ、嫉妬やうつが始まる。震災という外傷体験は心の奥に生涯残る。「悲しみに本当に共感できる心身の状態がどれほど自分に残っているのだろう」という小林俊三医師の問いは、全国の人びとへの問いでもある。
【再編集版】
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
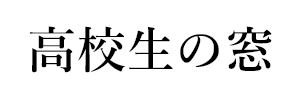
高校生の窓(休刊) 1993年~1996年
ALL REVIEWSをフォローする












































