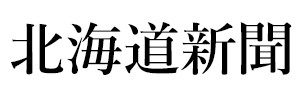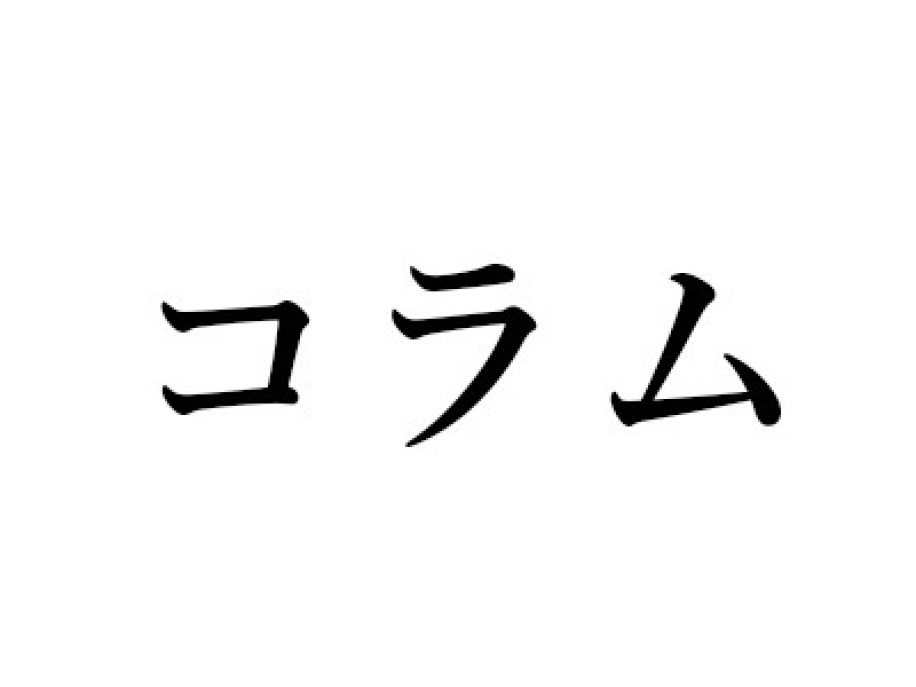書評
『母の声、川の匂い―ある幼時と未生以前をめぐる断想』(筑摩書房)
「故郷は語ることなし」と安吾はいった。若くして異郷で知的修練を積んだ者にとって、自分が後にしてきた出自が、できることなら忘れてしまいたいと思わせる両義的な場所であることを、この警句は端的に示している。本書の著者にしても同様であった。川田順造は東京下町は高橋(たかばし)に、江戸時代より八代続いた米問屋の息子として生を享けたが、山の手にある大学に学び、さらにパリで文化人類学を修めると、西アフリカのサバンナで長い研究生活を送った。あえて故郷を語らないと決意し、遠い異国の文化の勉強に身を捧げてきたのである。
ところがある時に和解が生じる。「潮が引いてこれまで隠れていた岩が再び姿を現すように」、自分が後にしてきた世界の記憶が蘇ってくる。江戸時代に設けられた運河に面してあった家の記憶。運河を渡ってゆく達磨船から流れる、肥料用の腸樽(わただる)の匂い。幼い頃から娘義太夫に夢中だった母親の思い出と、[ひ」を「し」と発音してしまう人々の言葉遣い。知性による認知に先立って、自分のなかにあたかも内臓感覚のように横たわっている記憶を辿るうちに、著者はそこに水を媒介とした豊かな文化が広がっていることに気がつく。かつてアフリカの無文字社会での儀礼伝承のあり方を『聲』という美しい書物に纏めたこの人類学者は、今度は幼少時に知った町角を闊歩する「順ちゃん」として、母親の同世代の女性たちの声に耳を傾ける。それはイタリアの思想家グラムシの言葉を借りるならば、「文化の腐植土」を測定する作業である。
いなせ。きおい。でんぽう。いさみ。おきゃん。気風のよさ。相次ぐ大火と高潮のせいで不安定な生活を強いられてはいたが、水路を通して関東一帯のさまざまな地域と頻繁に往来のあった下町は、上方の「みやび」とは異なった気分を醸成してきた。鳶と川並みという職業をめぐる記述は圧巻であり、本書をあまたある東京論のなかでも独自にものにしている。
【この書評が収録されている書籍】
ところがある時に和解が生じる。「潮が引いてこれまで隠れていた岩が再び姿を現すように」、自分が後にしてきた世界の記憶が蘇ってくる。江戸時代に設けられた運河に面してあった家の記憶。運河を渡ってゆく達磨船から流れる、肥料用の腸樽(わただる)の匂い。幼い頃から娘義太夫に夢中だった母親の思い出と、[ひ」を「し」と発音してしまう人々の言葉遣い。知性による認知に先立って、自分のなかにあたかも内臓感覚のように横たわっている記憶を辿るうちに、著者はそこに水を媒介とした豊かな文化が広がっていることに気がつく。かつてアフリカの無文字社会での儀礼伝承のあり方を『聲』という美しい書物に纏めたこの人類学者は、今度は幼少時に知った町角を闊歩する「順ちゃん」として、母親の同世代の女性たちの声に耳を傾ける。それはイタリアの思想家グラムシの言葉を借りるならば、「文化の腐植土」を測定する作業である。
いなせ。きおい。でんぽう。いさみ。おきゃん。気風のよさ。相次ぐ大火と高潮のせいで不安定な生活を強いられてはいたが、水路を通して関東一帯のさまざまな地域と頻繁に往来のあった下町は、上方の「みやび」とは異なった気分を醸成してきた。鳶と川並みという職業をめぐる記述は圧巻であり、本書をあまたある東京論のなかでも独自にものにしている。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする