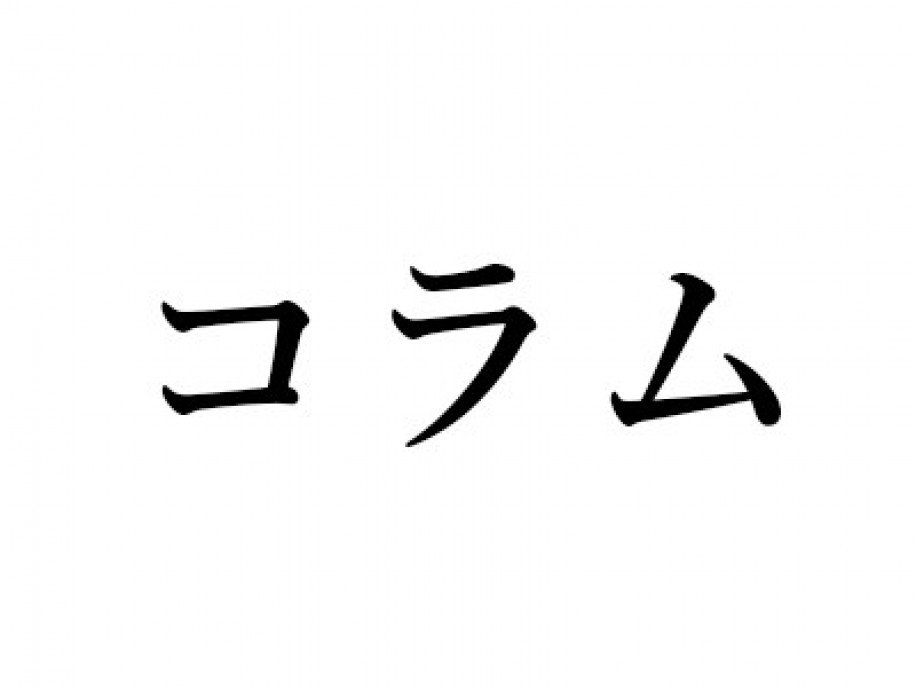書評
『延安―革命聖地への旅』(岩波書店)
東洋に惹かれて、遙かアメリカから日本に渡ってきた一人の作家がたどりついたのは、「革命の聖地」として知られる延安であった。地理的にも文化的にも文字通り周辺の地であり、中国では忘れられがちな過去の象徴だ。著者は一九九六年に一度訪ねたが、本書は十年ぶりの再訪を記したものである。
なぜ延安なのか、直接的には語られていない。エドガー・スノー『中国の赤い星』を意識しているのはまちがいない。このジャーナリストの思想的傾向はかつて物議を醸したことがあるが、いわゆる解放区をはじめその他の実情を西洋に報道した功績は否めない。彼が目にした風景はいまどう変わったのか、また彼が理想としていた体制が変質した後、農民たちの生活状況はどうなっているのか。そのことを著者は自分の目で確かめようとした。
十年前に比べて、延安の町にも高層ビルが建ち並ぶようになった。消費文化は工業化という過程を飛び越えて、怒濤のように「前近代的な」生活を一気に押し流した。しかし、都市部を一歩出ると、山腹に点在する洞窟式の住居に人々は以前と変わらない生活を営んでいる。エドガー・スノーが見た飢饉の惨状はさすがになくなった。しかし貧富の差はむしろ拡大している。巨万の富を築いた人たちが農民の困窮をよそに、贅沢三昧の生活をしているという、「同国人同士のむごい関係性」も苛烈な風土とともに存続している。
「あの『共産主義』が、とっくに、終わった」と著者は感嘆した。皮肉にも中国はマルクス主義を経由して、資本主義による再生という百年の夢を実現させようとしている。中国の指導者のなかに共産主義を本当に信奉する指導者がいたのだろうか。苛烈な近代史と過酷な風土を生き抜くために、彼らには手段を選ぶ余裕がなかったのかもしれない。「革命の聖地」を資本にして日銭をせっせと稼ぐ元農民たちも同じ心性であろう。
しかしこの紀行文学の意味は七十年ぶりの最新報告にとどまらない。より重要なのはエドガー・スノーの眼差しに対する批判が込められている点だ。レイモンド・ドーソン『ヨーロッパの中国文明観』によると、西欧における中国イメージは過剰に美化されるものか、不必要に貶(けな)されるもののどちらかだという。エドガー・スノーについて考えるときも、その点を考慮に入れるべきであろう。
アメリカ出身の日本語作家にとって、「アジア」について書くとき、二重の落とし穴が待ち受けている。オリエンタリズムの誘惑と、日本からアジアの後進国を見下ろすときの疎外感である。
仮に東京はポストモダンを過ぎて、「アジア」らしさをあまり感じさせないならば、延安の農民たちの生活は正反対の意味で「東洋的な魅力」に欠ける。だが、著者はあえて東京でも最も「非東洋的」である新宿に居を構え、延安という文化の辺境について日本語で綴る。オリエンタリズムから距離を置くための必要な戦術であろう。そのためか本書は、西洋人の手になる「アジア」見聞録とはひと味もふた味も違う。欧米のジャーナリストは原始的な生活を営む「アジア」を手放しで褒め称えるが、「アジア人」が少しでも尊厳のある暮らしを手に入れると、ケチをつける癖がある。だが、著者はそのような紋切型の視線を「アジア」に向けなかったし、中国という迷宮の幻像に惑溺することもない。「本質的にはわからない、把握しきれない風景」をわからないままにしておくところが、エドガー・スノーを凌駕している。
【この書評が収録されている書籍】
なぜ延安なのか、直接的には語られていない。エドガー・スノー『中国の赤い星』を意識しているのはまちがいない。このジャーナリストの思想的傾向はかつて物議を醸したことがあるが、いわゆる解放区をはじめその他の実情を西洋に報道した功績は否めない。彼が目にした風景はいまどう変わったのか、また彼が理想としていた体制が変質した後、農民たちの生活状況はどうなっているのか。そのことを著者は自分の目で確かめようとした。
十年前に比べて、延安の町にも高層ビルが建ち並ぶようになった。消費文化は工業化という過程を飛び越えて、怒濤のように「前近代的な」生活を一気に押し流した。しかし、都市部を一歩出ると、山腹に点在する洞窟式の住居に人々は以前と変わらない生活を営んでいる。エドガー・スノーが見た飢饉の惨状はさすがになくなった。しかし貧富の差はむしろ拡大している。巨万の富を築いた人たちが農民の困窮をよそに、贅沢三昧の生活をしているという、「同国人同士のむごい関係性」も苛烈な風土とともに存続している。
「あの『共産主義』が、とっくに、終わった」と著者は感嘆した。皮肉にも中国はマルクス主義を経由して、資本主義による再生という百年の夢を実現させようとしている。中国の指導者のなかに共産主義を本当に信奉する指導者がいたのだろうか。苛烈な近代史と過酷な風土を生き抜くために、彼らには手段を選ぶ余裕がなかったのかもしれない。「革命の聖地」を資本にして日銭をせっせと稼ぐ元農民たちも同じ心性であろう。
しかしこの紀行文学の意味は七十年ぶりの最新報告にとどまらない。より重要なのはエドガー・スノーの眼差しに対する批判が込められている点だ。レイモンド・ドーソン『ヨーロッパの中国文明観』によると、西欧における中国イメージは過剰に美化されるものか、不必要に貶(けな)されるもののどちらかだという。エドガー・スノーについて考えるときも、その点を考慮に入れるべきであろう。
アメリカ出身の日本語作家にとって、「アジア」について書くとき、二重の落とし穴が待ち受けている。オリエンタリズムの誘惑と、日本からアジアの後進国を見下ろすときの疎外感である。
仮に東京はポストモダンを過ぎて、「アジア」らしさをあまり感じさせないならば、延安の農民たちの生活は正反対の意味で「東洋的な魅力」に欠ける。だが、著者はあえて東京でも最も「非東洋的」である新宿に居を構え、延安という文化の辺境について日本語で綴る。オリエンタリズムから距離を置くための必要な戦術であろう。そのためか本書は、西洋人の手になる「アジア」見聞録とはひと味もふた味も違う。欧米のジャーナリストは原始的な生活を営む「アジア」を手放しで褒め称えるが、「アジア人」が少しでも尊厳のある暮らしを手に入れると、ケチをつける癖がある。だが、著者はそのような紋切型の視線を「アジア」に向けなかったし、中国という迷宮の幻像に惑溺することもない。「本質的にはわからない、把握しきれない風景」をわからないままにしておくところが、エドガー・スノーを凌駕している。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする