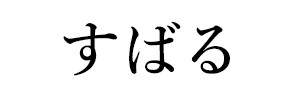書評
『終末のオルガノン』(作品社)
高山宏ほどパラディグマティック(範列的)な書き手はいない。それは扱う対象ばかりでなく、その文体、思考法においてもパラディグマティックだということである。たとえば彼は「板」と書いて横に「ボード」とルビを振るが、これは別に気取りではなく、「板」と書くと自動的に「ボード/テーブル/タブロー」という範列が横並び的に現れてくるからである。そして、「板」という単語がひとたび現れると、それはパラディグマティックな運動を開始して、「食卓、仕事台」などの系列を引き出し、そこから「部屋、家族」などを手繰り寄せる。また「タブレット」の系列では「木版、法典」を、「タブロー」の方で「絵」を、あるいは、重要な系列「図表、目次」などを次々に導きだす。こうして意味が意味を呼び、気がつくと「テーブル」に発する「近代」という「秩序化の身振り」が一望のもとに示される。
これは、序章の『「構造」はテーブルする』というマニフェストの要約だが、こうした文体と思考法におけるパラディグマティックな増殖と収斂の構造は、ダン、メルヴィル、デフォーなどの重層的作家を、「橋・数・螺旋・気象」などの多元決定的なテーマから考察した各章においても遺憾なく発揮されている。
本書は、高山宏を読むときは、「起」から「結」へと至る「線的」な読書ではなく「まるで絵でも見るときのように無方向的に拡散」した読み方をしなければならないことを「構造的」に教えてくれる貴重な一冊である。
【この書評が収録されている書籍】
これは、序章の『「構造」はテーブルする』というマニフェストの要約だが、こうした文体と思考法におけるパラディグマティックな増殖と収斂の構造は、ダン、メルヴィル、デフォーなどの重層的作家を、「橋・数・螺旋・気象」などの多元決定的なテーマから考察した各章においても遺憾なく発揮されている。
本書は、高山宏を読むときは、「起」から「結」へと至る「線的」な読書ではなく「まるで絵でも見るときのように無方向的に拡散」した読み方をしなければならないことを「構造的」に教えてくれる貴重な一冊である。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする