書評
『テクスト世紀末』(ポーラ文化研究所)
著者によれば、これらのテーマを連結している環は、「素材を織ってひとつの表層をつくりだすテクスト行為」であり、そして抑圧的なイデオロギーが自らを隠蔽するために、考えつく限りの経糸と緯糸を動員して絢爛(けんらん)たる表層を作りだすこのテクスト行為の遍在こそが、世紀末の隠れた構造だったという。
たとえばオリンピアンの絵画においては、「信じがたいほど白く滑らかで緻密な女の肌の肌理(きめ)」つまり表層のテクストが見るものの目を奪い、その深部で機能しているもうひとつの言語的テクスト、いいかえればギリシャ神話に仮託したヴィクトリア朝の男性中心主義的な女嫌い(ミソジニー)を隠蔽している。また、ジェロームを中心とするオリエンタリズム絵画でも、明暗対比(キアロスクーロ)を際立たせるためにことさら浅黒く醜く描かれた原住民の男たちによって競りにかけられる女奴隷の真っ白な肌は、そのわきにかかげられた絨毯の細密描写とあいまって「そこにあるすべてがテクスチャーであることを強烈に印象づける」が、同時に、黒い男たちに手ごめにされた色の白い女(オリエント)が救いをまっているという「救済の詩学・緊縛の政治学」を、イデオロギーと欲動の二重のレベルで我々のうちに刷り込んでいく。つまり、こうしたオリンピアンやオリエンタリズムの絵画では、磁器のように真っ白で滑らかな女の肌という肌理の下に、作者の言語的テクストが隠蔽されると同時に、それを見ている男性の視線もまた緊縛の網、つまり、アンドロメダ・チェインと化して、「救済の詩学」に酔いしれるのである。
いっぽう、世紀末の室内装飾や、博物館、万国博覧会やデパートといった巨大な空間などもまた、世紀末特有のテクスト的オブセッションが現れる特権的な場(トポス)であった。たとえばイタリア世紀末の頽唐派の詩人ダヌンツィオの邸ヴィラ・ヴィットリアーレは、壁や、家具や、カーテンが、彼の作品のテクストを反復するかのように絢燗たるテクストを織りなしている。すなわち、まず自然の入り込む余地のある「窓」を重畳たるカーテンで覆いつくし、ありとあらゆる様式の家具を集め、これを独特の美意識にしたがって配列する。その空間は「深い信仰心と正真正銘の文体」を欠いているが故に、数限りない珍奇なものを必要とする住人の「ビザンティン的精神」を反映していた。そして、この「覆う」「集める」「並べる」という世紀末的テクスト行為は、博物館、万国博覧会、デパートといった博物学の後裔(こうえい)たる十九世紀的トポスにおいても、その構造を正確に反復する。
ところで衣服、紙といった文字通りの意味におけるテクストも、世紀末文芸や絵画がほとんど細部狂いに近い熱狂をもって好んでとりあげた主題であった。その典型は、たとえば、愛人のキャサリーン・ニュートンをモデルにして、彼女の身に着ける華やかなドレスの襞のひとつひとつをいかにもいとおしげに描き出すティソ、あるいは、一語一語を経糸と緯糸のように複雑に繰り出して衣服を描写しながら「ドレスをつくるように」、『失われた時を求めて』を書いてみたいと夢想するプルーストにうかがうことができる。彼らは同時に、画中(作中人物)と鑑賞者(読者)が投げかけあう視線の戯れのテクストを意識しているアーティストでもあった。
あるいは紙、紙幣、画布といった題材をハイパー・リアリズムで描くことによって見るものの目を欺く世紀末のアメリカン・トロンプ・ルイユの画家たち。彼らのトロンプ・ルイユは、紙というものが紙幣という形で幻惑的な交換価値の媒介となった、十九世紀末を象徴的に現している。
要するに、筆者が世紀末の特権的トポスとしてとりあげたテーマは、すべてミクロ・スケールとマクロ・スケールの二重のレベルで相同形のテクスト行為を反復し、互いに相手の姿を照らし出すという、リフレクシヴな構造をもっているのである。そして、これは、冒頭で述べたような著者の方法論とも同じように反射しあい、ある種の螺旋(らせん)構造を描いて、読者を幻惑することになる。
しかしながら、こうしてチャート式に論点を要約することは、実は本書の面白さを減じこそすれ、けっして増やすことにはならない。なんとならば、本書の醍醐味は、奔放に枝を伸ばしていく著者のニューロン回路のスピードに同調しながら、著者の繰り出す無限のイメージ連鎖を読者自身が勝手に引き継ぎ、そこから自由に連想の枝を伸ばしていくことにあるのだから。つまり、著者の狙いは、自己完結した論理で読者を退屈させ、テクストの中に閉じ込めることではなく、読者を、旧套的な世紀末のイメージから解放して、多元的なテクスト世紀末の世界へと誘うことにあるのである。いずれにしても、読みやすいというのでは決してないが、読んでいくうちに元気が湧いてきて、がらにもなく、もう一度勉強をやりなおしたくなる本である。こんな本に出会ったのはベンヤミンの『パリ――十九世紀の首都』以来、久しぶりのことである。
たとえばオリンピアンの絵画においては、「信じがたいほど白く滑らかで緻密な女の肌の肌理(きめ)」つまり表層のテクストが見るものの目を奪い、その深部で機能しているもうひとつの言語的テクスト、いいかえればギリシャ神話に仮託したヴィクトリア朝の男性中心主義的な女嫌い(ミソジニー)を隠蔽している。また、ジェロームを中心とするオリエンタリズム絵画でも、明暗対比(キアロスクーロ)を際立たせるためにことさら浅黒く醜く描かれた原住民の男たちによって競りにかけられる女奴隷の真っ白な肌は、そのわきにかかげられた絨毯の細密描写とあいまって「そこにあるすべてがテクスチャーであることを強烈に印象づける」が、同時に、黒い男たちに手ごめにされた色の白い女(オリエント)が救いをまっているという「救済の詩学・緊縛の政治学」を、イデオロギーと欲動の二重のレベルで我々のうちに刷り込んでいく。つまり、こうしたオリンピアンやオリエンタリズムの絵画では、磁器のように真っ白で滑らかな女の肌という肌理の下に、作者の言語的テクストが隠蔽されると同時に、それを見ている男性の視線もまた緊縛の網、つまり、アンドロメダ・チェインと化して、「救済の詩学」に酔いしれるのである。
いっぽう、世紀末の室内装飾や、博物館、万国博覧会やデパートといった巨大な空間などもまた、世紀末特有のテクスト的オブセッションが現れる特権的な場(トポス)であった。たとえばイタリア世紀末の頽唐派の詩人ダヌンツィオの邸ヴィラ・ヴィットリアーレは、壁や、家具や、カーテンが、彼の作品のテクストを反復するかのように絢燗たるテクストを織りなしている。すなわち、まず自然の入り込む余地のある「窓」を重畳たるカーテンで覆いつくし、ありとあらゆる様式の家具を集め、これを独特の美意識にしたがって配列する。その空間は「深い信仰心と正真正銘の文体」を欠いているが故に、数限りない珍奇なものを必要とする住人の「ビザンティン的精神」を反映していた。そして、この「覆う」「集める」「並べる」という世紀末的テクスト行為は、博物館、万国博覧会、デパートといった博物学の後裔(こうえい)たる十九世紀的トポスにおいても、その構造を正確に反復する。
起源(オリジン)を欠いた「事物」が人々の個/孤をなぞるかのごとく、アレンジされては別の意味体系に身をひさいでいく「交換価値」(マルクス)の世界がはっきり可視化された。一切のマクロ・テクスト、「先在的超越的な意味(シニフィエ)」の見えなくなってしまった清潔無比な空間の中で、「展示」という名のアレンジメント、リアレンジメントが、個と個の「売り」を眼目としたかりそめの繋がり、とるにも足らぬミクロ・テクストを、日々、客のいる限り、飽きもせず紡ぎ出すのであった。
ところで衣服、紙といった文字通りの意味におけるテクストも、世紀末文芸や絵画がほとんど細部狂いに近い熱狂をもって好んでとりあげた主題であった。その典型は、たとえば、愛人のキャサリーン・ニュートンをモデルにして、彼女の身に着ける華やかなドレスの襞のひとつひとつをいかにもいとおしげに描き出すティソ、あるいは、一語一語を経糸と緯糸のように複雑に繰り出して衣服を描写しながら「ドレスをつくるように」、『失われた時を求めて』を書いてみたいと夢想するプルーストにうかがうことができる。彼らは同時に、画中(作中人物)と鑑賞者(読者)が投げかけあう視線の戯れのテクストを意識しているアーティストでもあった。
あるいは紙、紙幣、画布といった題材をハイパー・リアリズムで描くことによって見るものの目を欺く世紀末のアメリカン・トロンプ・ルイユの画家たち。彼らのトロンプ・ルイユは、紙というものが紙幣という形で幻惑的な交換価値の媒介となった、十九世紀末を象徴的に現している。
要するに、筆者が世紀末の特権的トポスとしてとりあげたテーマは、すべてミクロ・スケールとマクロ・スケールの二重のレベルで相同形のテクスト行為を反復し、互いに相手の姿を照らし出すという、リフレクシヴな構造をもっているのである。そして、これは、冒頭で述べたような著者の方法論とも同じように反射しあい、ある種の螺旋(らせん)構造を描いて、読者を幻惑することになる。
しかしながら、こうしてチャート式に論点を要約することは、実は本書の面白さを減じこそすれ、けっして増やすことにはならない。なんとならば、本書の醍醐味は、奔放に枝を伸ばしていく著者のニューロン回路のスピードに同調しながら、著者の繰り出す無限のイメージ連鎖を読者自身が勝手に引き継ぎ、そこから自由に連想の枝を伸ばしていくことにあるのだから。つまり、著者の狙いは、自己完結した論理で読者を退屈させ、テクストの中に閉じ込めることではなく、読者を、旧套的な世紀末のイメージから解放して、多元的なテクスト世紀末の世界へと誘うことにあるのである。いずれにしても、読みやすいというのでは決してないが、読んでいくうちに元気が湧いてきて、がらにもなく、もう一度勉強をやりなおしたくなる本である。こんな本に出会ったのはベンヤミンの『パリ――十九世紀の首都』以来、久しぶりのことである。
初出メディア
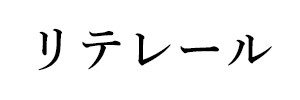
リテレール(終刊) 1993年3月
ALL REVIEWSをフォローする







































