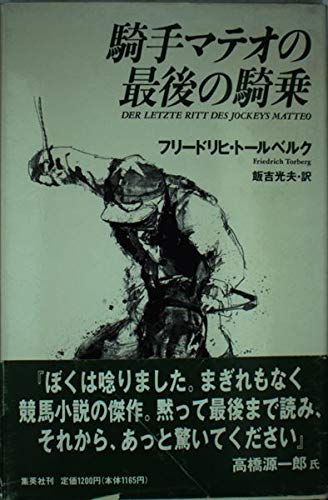書評
『ピネベルク、明日はどうする!?』(みすず書房)
ナチス前夜 すかし絵のように描く
若いピネベルクと恋人の子羊ちゃん。愛し合ったので子供ができてしまった。そんなことはこれっぽちも考えていなかった二人である。さて、今後どうする!?古今東西、世界中でごまんとあり、またあったケースで、顛末(てんまつ)をつづった物語もまたごまんとある。たえまなく現れては消えていく。
ハンス・ファラダの『ピネベルク、明日はどうする!?』もそんな一つであって、軽はずみな若い二人のその後を語っていく。現れては消えていく一つにちがいないのに、現れたのが一九三二年。以後、たえず読み継がれ、八十五年たっても消えなかった。いったい、何がこのフシギをもたらしたのだろう。
作者ハンス・ファラダ(一八九三-一九四七)は、ドイツ文学ではケストナーやブレヒトと近い世代だが、日本ではほとんど知られていない。私生活では何度も警察沙汰を引きおこした。ペンネームはグリム童話にちなんでいて、ハンスはおなじみの主人公、ファラダは首を切られても真実を語りつづけた馬の名前である。そんなペンネームを選んだ男だ。またドイツ文学はトーマス・マン、ヘッセ、ブレヒトに見るように、文学に神話や伝承や主義をもちこみたがる。ファラダは一切それをしなかった。ただ語りのおもしろさを小説にした。こういった特色が日本のドイツ文学者には、お気に召さなかったのかもしれない。
目次を開いて、すぐに気がつく。「なにも考えていなかった二人」は、まずは「小さな町」で「明日」の準備をする。小さな商店のしがない簿記係には何の展望もひらけないが、ふとしたことで幸運が舞いこんでベルリンへ出る事態になった。ユダヤ人の経営するデパートの主任ぐらいではラチがあかないにせよ、失業者がうなぎのぼりの世相ではゼイタクは言えない。
短章ごとに短い手引きがあたまにつく。
「ヤッハマンは嘘(うそ)をつき、ゼムラーは嘘をつき、レーマンは嘘をつき、ピネベルクも嘘をつく。それでも彼は職を得て、おまけに父親まで得る」
「子羊ちゃんはお客を迎え、自分を鏡に映してみる。その晩はお金の話はご法度」
作者がつけた要約だが、中身そのままではない。皮肉、反語、予兆、ユーモアがまじえてあって、同じころケストナーやブレヒトが愛用した語り口である。物語が巧みな二重性をおびてつづいていく。
初版が出た一九三二年は、ヒトラー政権誕生の前年にあたる。ドイツでは、先立って記録的なインフレがあり、ついでデフレがみまった。失業者が六〇〇万に達した。そのなかでナチ党が急速に人をとらえていく。通りでは毎日のようにSA(突撃隊)と左翼労働者の衝突があり、血が流れた。エピローグ「人生はつづく」の一章、「躓(つまず)きの石たるピネベルク。忘れられたバターと保安警察。これほど暗い夜がかつてあっただろうか」。
しがないベルリンの小市民夫婦を通して、ナチス前夜の時代相が、すかし絵のようにあぶり出されていく。作者はこの上なく醒(さ)めた目で、同時代の百面相を写しとった。ヒトラーが呼びかけたのは、まさにこの多数派小市民だった。お得意の演説は、一つの標的を狙うように、この小市民層に向けられていた。誇張して注目させ、おどしをかけて燃え上がらせた。ナチズムの妖怪は異常な人間集団のひきおこしたものではなく、その母胎にあたるものは、ごくふつうの人々だった。「明日、どうする!?」に往(ゆ)き迷った人々だった。(赤坂桃子訳)
ALL REVIEWSをフォローする