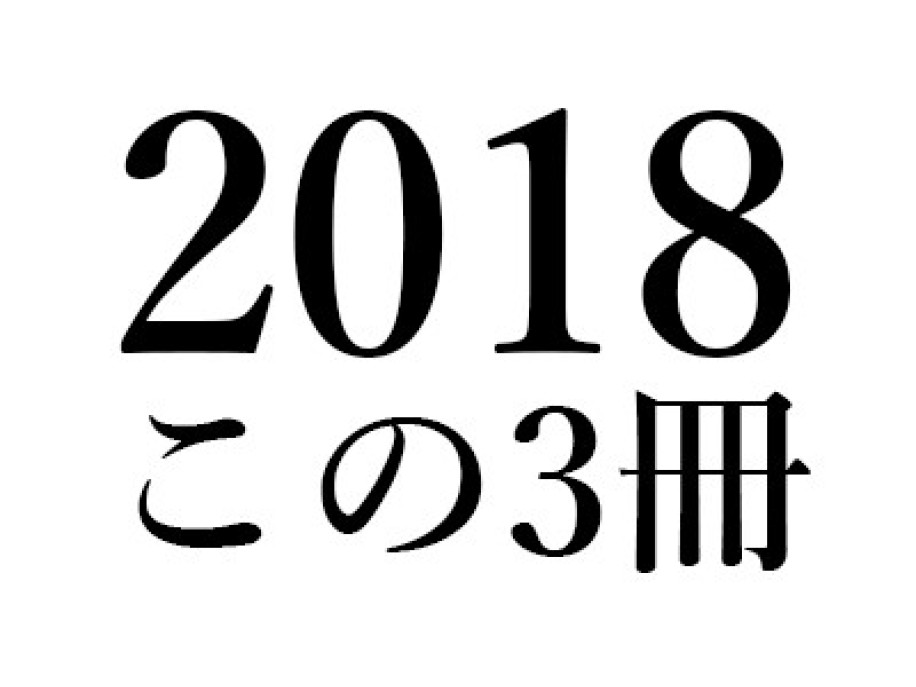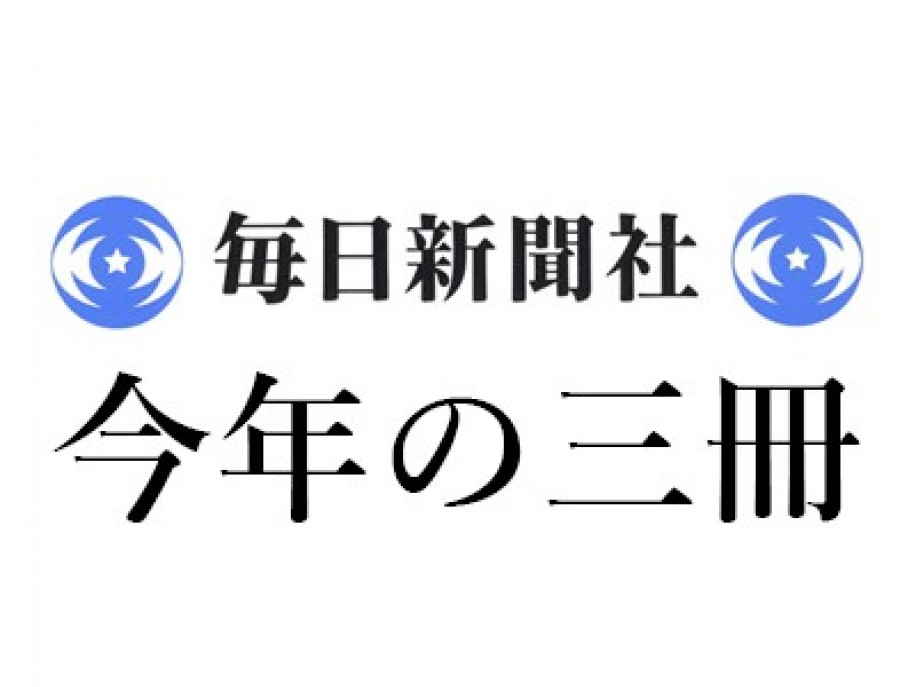書評
『ゲッベルスと私──ナチ宣伝相秘書の独白』(紀伊國屋書店)
すべてを可能にした原因は無関心
ヨーゼフ・ゲッべルスは、一九三三年三月、ヒトラー政権誕生の二カ月あまりのち、国会議事堂炎上事件で物情騒然とするなか、新設された宣伝省大臣に就任した。ときに三五歳。宣伝省とは、聞き慣れない名称だが、正確には「国民の啓蒙(けいもう)と宣伝(プロパガンダ)のための帝国省」。ながらく反共産主義、反ユダヤの超過激集団とみなされていたナチスは、政権につくやいなや、「ナチス革命」をひろく訴えるためにも、国民啓蒙の部局が必要と考えたのだろう。おりしも国会では、ヒトラーへの全権委任法案の議決を目前にしていた。党幹部は、才気煥発(かんぱつ)で、おそろしく演説のうまい若手を大臣に抜擢(ばってき)した。
就任直後の演説の有名なくだり。「宣伝の秘訣(ひけつ)は、いかにも宣伝らしくではなく、相手にそうと気づかれないうちに宣伝にどっぷり浸(つか)らせてしまうことだ」
反ナチスを公言していた指揮者フルトヴェングラーについて述べたくだり。「フルトヴェングラーには、彼が少しもわれわれに協力していないように思わせておけ。一方、世間には、彼はあたかも協力しているように見せることだ」
この政治的人間が、いかにはやばやと現代のプロパガンダ術を実践していたかがおわかりだろう。宣伝省のモットーにいわく、「用件は電話と口頭で処理して、それも即決を原則とする」。文書化は最後とすべし。現代では「マネッジメント・メソッド」と呼ばれるシステムを、いち早く官僚体制に導入した。
『ゲッべルスと私』は、一九四二年、国営放送局から宣伝省へ異動し、一九四五年五月のベルリン陥落直前まで、宣伝省の大臣官房秘書室に勤務したタイピスト兼秘書ブルンヒルデ・ポムゼルの回想である。まずドキュメンタリー映画に収録され、そののち映画関係者らの対話にもとづいてまとめられた。映画がつくられたとき、ポムゼルは一〇三歳だった。七〇年ちかい沈黙ののち、堰(せき)を切ったように人生を回顧した。その克明な記憶に、まず読者は驚くだろう。
ゲッべルスは見た目のいい人だった。(…)すべてが完璧で、非の打ちどころがなく、けちのつけようがなかった。
当時三一歳の女性は、大臣が毎日誰かに、爪の手入れをしてもらっているのを見逃さない。
だが、しだいに冷静沈着なキレ者の「真実の顔」に気がついてくる。「歴史に残る大演説」といわれるものの一つだろう。一九四三年二月一八日、ゲッべルスはベルリンのスポーツ宮殿で、一五〇〇〇人を前に演説した。秘書室から二人の動員がかかり、ポムゼルは同僚と出かけた。全土にわたってラジオ放送された。
演説が終わったとき、会場にいた人々はみな「スズメバチに刺されでもしたかのように」大声で叫び、足を踏み鳴らし、ちぎれんばかりに手を振り回した。「諸君は総力戦を望むか?」。ゲッべルスは十の問いかけを矢つぎ早にした。「総統のために」「われわれのために」「ドイツ民族の終極の勝利のために」。一五〇〇〇人がこぞって「ヤー(イエス)」と答えた。ラジオのまわりのドイツ国民がいっせいに「ヤー」と叫んだ。
私たちは二人とも、目の前の出来事に圧倒されて、息をすることもできずにいた。
熱狂する大衆のようすだけが印象に残った。
そしてゲッべルスを「とても恐ろしいと思った」という。
ゲッべルスの日記からわかるのだが、この時点で彼は、国民から逃げ出し始めたヒトラーを批判し、終極の勝利など信じていなかった。だが、自分の演説の力は信じていた。
しかしながら、この本の読みどころは、身近に見た稀代(きたい)の政治的人間以上に、ドイツ国民がナチズムに同調していった経過だろう。くり返し出てくるセリフは「人々の最大の関心事は、仕事とお金を得ることだった」「[KZ(強制収容所)という言葉を耳にしたとき]誰もそれについて深く考えてはいなかった」「何も知らなかった」「人々は多くを知りたいとは、まるで思っていなかった」。
ホロコースト(ユダヤ人大虐殺)をはじめとするナチスの悪行の原因を問われたのだろう。一〇三歳の証言者は、答えている。「すべてを可能にした原因は国民の無関心にあった」
対話の相手は、一〇三歳の高齢といったことに、いささかも顧慮していないし、また当の女性も、少しも老いを隠れ蓑(みの)にしていない。いまさらながらヨーロッパの個人主義の強靱(きょうじん)さを思い知らされる。ナチス同調の罪を問われて、ポムゼルは毅然(きぜん)として答えている。
「私たちに罪はない」
これほどの歴史的過去を、このように克明に覚えていることについて、編者は何も述べていない。私は思うのだが、ポムゼルには自分の経歴に照らして、ひそかに使命者意識があったのではあるまいか。長い長い沈黙のあいだ、目の底、耳の底にしみついたシーンを何百回、何千回となく反芻(はんすう)した。そして世紀をこえたある日、蚕が糸を吐くようにして語りつづけた。二〇一七年、ミュンヘンで死去。一〇六歳だった。
ALL REVIEWSをフォローする