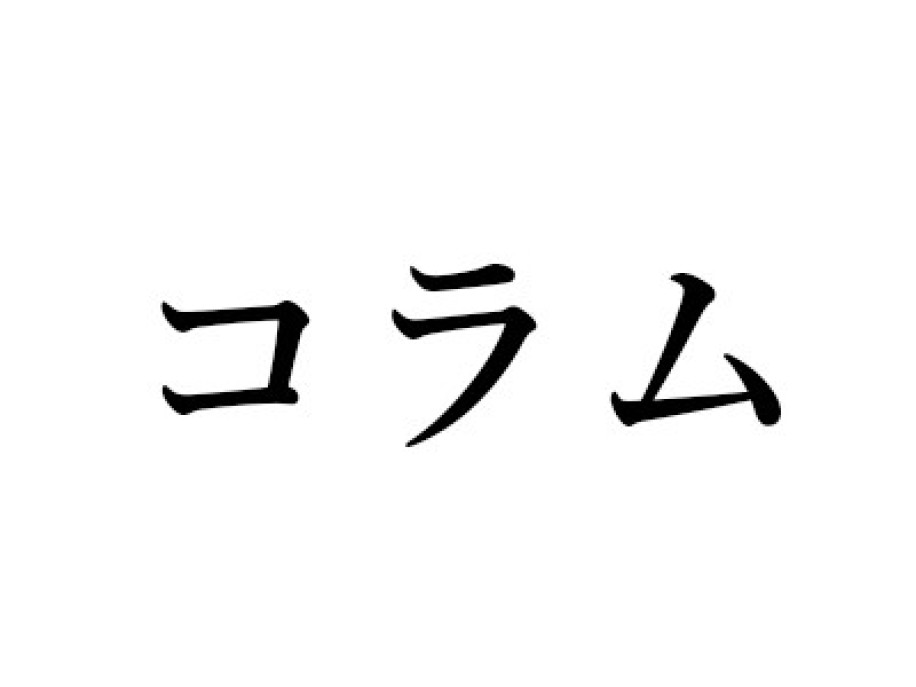後書き
『平成の重大事件 日本はどこで失敗したのか』(朝日新聞出版)
あとがき
降る雪や 明治は遠く なりにけり誰もがどこかで耳にしている句である。
すでに明治は遠いから、語義どおりに受け取っている人は少なくない。だがその感慨はもう少し具体的な実感がともなって生まれたものだ。俳人中村草田男(くさたお)が発句したのは昭和六年であった。
大正天皇が崩御したのは大正十五年十二月二十五日だった。昭和元年は年末まで一週間しかなく、年が開けると昭和二年だった。巷では大正十六年新年号と印字された月刊誌が売られていた。昭和三年十一月に昭和天皇の即位礼があり、あたらしい元号がじわじわと馴染んでくるまでに五年ぐらいかかったのだと思う。遠くなったのは終わったばかりの大正でなく、明治である。異なる元号をひとつ挟んで、ようやく明治は遠くなったとの想いがつのるのである。
中村草田男の心境がよくわかる気がするではないか。平成という三十年の時が過ぎてしばらくすると言いたくなるに違いない。昭和は遠く……、と。中村が明治生まれであるように、三十歳以上の人は昭和生まれなのである。
福沢諭吉は『文明論之概略』のなかでこう述べた。
あたかも一身にして二生を経るが如く、一人にして両身あるが如し。
幕末と明治の両方の異なる二つの時代を生きた。日本的な江戸時代と文明開化の明治時代、その意味では文明論的なテーマを抱えた述懐である。
そこまでの断絶はないとしても、日本人の宿命として、一人の人生のなかに元号で分離された二つの時代が棲むことになるのだ。日本独特の元号には不便なところもあり、西暦との混在もめんどうだ、と文句も言いたいこともなくはない。だが人生には元号が必要なときもある。年齢も重ねながら、こうした過ぎ越し時代に対する言い難き屈折感ないしは懐古の情は、西暦からは得られるものではない。
さて、振り返ることは前を向くためにするものだ。深く振り返るのは、より本気で前を向くためである。平成という息子は、昭和という遺産を食い潰しているようでいて、新しい未来への芽吹きを、デフレの風雪のなかで準備してきたのではないかと思う。
年功序列・終身雇用のライフスタイルを突き崩したのはインターネットの普及、跳梁(ちょうりょう)跋扈(ばっこ)とさえ言ってよい。テレビの時代からSNSの時代へ移り、やがて人工知能の時代へ辿り着く。それがいまはっきりと見えている。
田原総一朗さんとの対談は、自分のなかの三十年がどのような時代のなかにあったのかを確かめるために有意義だった。田原さんはジャーナリズムの第一線を走り続けた。いまも走り続けている。僕も作家として歴史を俯瞰する巨視的な眼と、個々の出来事や人物のなかに含まれるディテールの真実を描いてきた。
読者の皆さんとは、本書を通じて歴史という客観的事象を共有すること、あるいはエピソードで追体験をしていただくこと、それが少しでも未来に資するところがあれば本望である。
平成三十年五月 西麻布の寓居にて
猪瀬直樹
ALL REVIEWSをフォローする