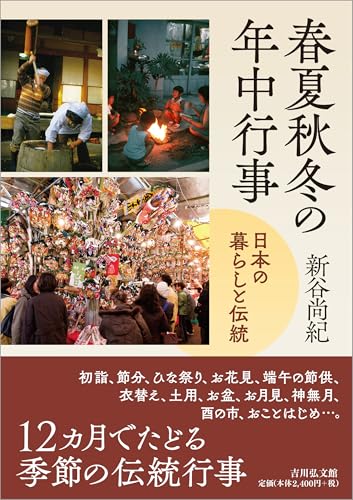書評
『1ミリの後悔もない、はずがない』(新潮社)
過去を引きずりながらも人は前に進む
ここにおさめられた五編の短編小説は、時間も語り手も舞台となる場所も異なるが、それぞれつながっている。だから短編連作集というのがただしいけれど、でも私には、五編でひとつの長編小説のように感じられる。第一章、「西国(にしこく)疾走少女」は、語り手である由井の、中学時代の回想である。由井こと「わたし」は、西国分寺駅にほど近い狭い一軒家に、母と妹と暮らしている。別居している父親は無職で、それによって由井は特殊な事情を背負わされていることがだんだんわかる。自分では選べず、変えることもできないそんな日々のなか、由井は同級生に恋をする。恋だって、実質的には彼女を救わないけれど、それでも彼女はその恋に向かって疾走する。
描かれるのは絶望と諦観に覆われた世界なのに、清潔な光に満ちている。閉塞(へいそく)的な世界を描きながらも、タイトル通りいきいきとした疾走感がある。そんな第一章に惹(ひ)かれて一気に読んだ。
中学時代、由井と親しかった友だちや、その友人が憧れた人気者の先輩、由井と似たような境遇を生きてきた、現在の由井の夫など、第二章以降に描かれるのは、今現在、三十代になった人々の姿だ。彼らの多くは、すでに自分で選べ自分で変えられる年齢でありながら、中学時代とはまた異なった、窮屈で息苦しい場所で生きている。ここに至る道のどこかで、何かを間違えた、何かを見落とした、何かをなくした、そんな人たちばかり。悪事を働くこともなく、他人をおとしめることもなく、ただごくふつうに歩いてきただけなのに、願ったような場所にはたどり着いていない。だから彼らは自分の人生を歩き続けながら、途方に暮れている。どこで間違った? どこで見落とした? どこでなくした? と自問自答しながら。
読み進むにつれて、あることに気づく。三十代になった由井の同級生や先輩たちは登場するのに、ひとりだけ描かれない人物がいる。中学時代の由井の恋人、桐原だ。
桐原の姿は見えないまま、最後の短編小説「千波万波(せんぱばんぱ)」で、読者は大人になった由井に再会する。中学卒業後、今日ここに至るまでの由井の日々がじょじょに明かされる。彼女が過ごした過酷な日々が、まったく美化されることなく描き出されていくのに、またしても私は、第一章と同じように、そこに清潔な光が射(さ)しこむのを感じる。それはたぶん、作者が描こうとしているのが過酷さではなくて、過酷さを乗り切る力だからではないか。彼女にそれを乗り越えさせる、さまざまな力が、光の粒のように見えてくるのだ。
かつての窮屈で息苦しい場所から抜け出して大人になった由井に、読者は深く安堵(あんど)するに違いないが、小説は突き放すようなラストを用意している。桐原不在の理由もようやく理解する。それで、後悔、という言葉を私は様々な角度からじっくりと眺めなければならなかった。タイトルにもある、後悔。彼女が、彼らが、いや、私たちもまた、ここに至るまでに、間違い、見落とし、なくしたもの。それこそまさに後悔だ。でもそれが何かわからないから、先に進むしかない。後悔を、背後にじゃらじゃらと引きずりながら。
この小説が描き出すのは、そんなふうに生きるしかない人の姿だ。そしてそこにとどまらず、なぜ、後悔を引きずりながらも私たちが前に進めるのかも、さりげなくしかし強く、見せてくれる。R―18文学賞の受賞作である短編を書きつないでいったことで、ほろ苦く、でもやさしい長編小説が立ち上がった。
ALL REVIEWSをフォローする