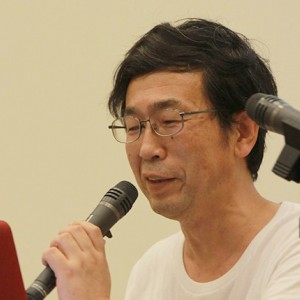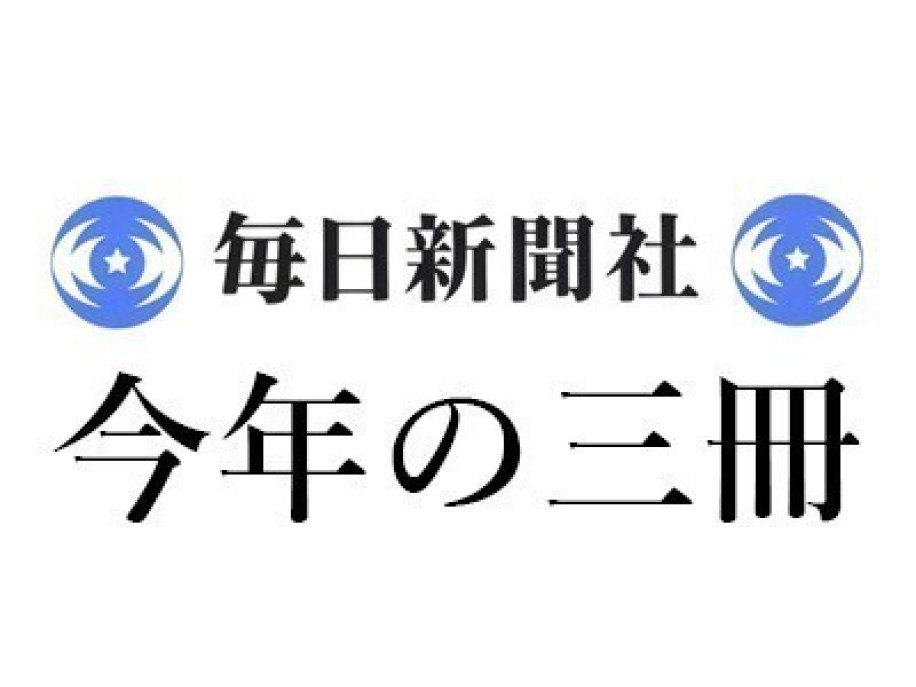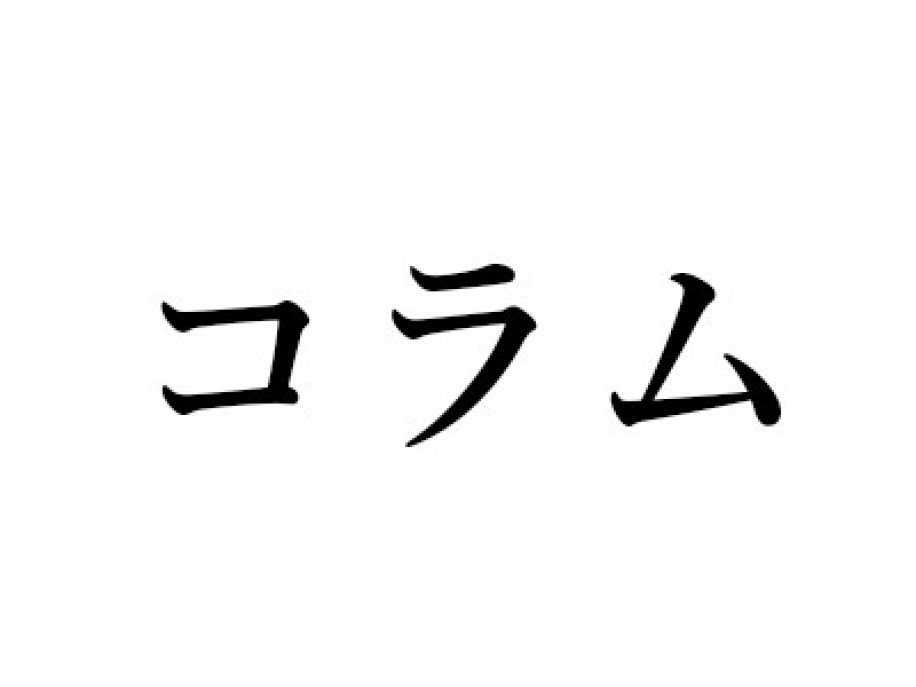書評
『数字が明かす小説の秘密 スティーヴン・キング、J・K・ローリングからナボコフまで』(DU BOOKS)
統計的処理から得られた「文体」
「文は人なり」という言葉がある。書かれた文章は、書き手の人間性をおのずから反映してしまう、という意味だ。これをもう少し言い直して、「文体(スタイル)は人なり」という言い方もある。それでは、ここでいう「文体」とはどんなものか。わたしたちは文体というものを漠然と理解していても、これがある作家の文体だとはっきり言い切れる一般的な決まりは持っていない。本書『数字が明かす小説の秘密』は、主に英米の著名な作家の作品やベストセラーを素材にして、その膨大な数のテキストデータに統計的処理を施し、そこから作家の文体についてどのような発見が得られるかを述べたものである。統計的処理を行うということは、簡単に言うと、個々の作品を読まない、ということだ。そこで問題になるのは、ある語、あるいは語句が、どのような頻度で使用されているかという「数字」である。従来、書物をめぐるわたしたちの営みは、ほとんどが「読む」という行為に基づいていた。たとえば、この書評欄にしたところで、書評者が対象となる図書を読んでいなければ書評が成り立たない。しかし本書では、個々の書物を読む代わりに、「数字」を「読む」。統計的処理をすれば、必ずなんらかの数字が結果として出てくる。しかし、その数字を読む技術を持っていれば、ただの数字の羅列にすぎないものが、興味深い物語を語っていることを発見できる。本書には、おっと驚くような、そうした発見があふれている。
第3章では、文体の定量化が扱われている。単語の使用頻度から割り出した、作家個人の文体的特徴を、ここでは「指紋」と呼ぶ。この指紋を比べれば、スティーヴン・キングがリチャード・バックマンという筆名で書いた作品は、作者として最も可能性が高いのがキングだという結果が出てくるし、「ハリー・ポッター」シリーズの作者J・K・ローリングがジャンルを変えて、ロバート・ガルブレイスという筆名で書いた探偵小説は、作者として最も可能性が高いのがローリングだという、一見当然のように思えるが、実は驚くべき結果が導かれる。
もちろんこの「指紋」は、わたしたちがこれまで漠然と抱いていた文体というものの概念を矮小(わいしょう)化したものであり、とても「人」を表すとは思えない、という懐疑派の反論は容易に予想されるところだろう。ただ、ハードな事実としての「指紋」が、「人」の鑑定に役立つこともまた確かなのである。その意味で、「指紋」とはまさしく言い得て妙なのだ。
本書には、こうした作家の文体上の特徴をめぐるミクロな問題の他にも、文章の複雑さを表す数式を規定し、その物差しで測った場合に、小説の文章の複雑さのレベルが年代を追うごとに低くなってきている、というマクロな問題も提起されている。その事実を私たちはどう「読む」べきか。一般的なリテラシーが低下しているという憂慮すべき事態だと読むのか、それとも、単純な言葉がより多くの読者に伝わるという、肯定的な傾向として読むのか。いずれにせよ、本書を読んでいると、考えさせられることは多い。
最後に一言。本書の第8章では、書物の表紙で作者の名前がどれくらい大きく書かれているかという、販売戦略に関した問題が扱われている。ところが、本書の表紙カバーでは、『数字が明かす小説の秘密』という文字は大きく書かれているが、著者と訳者の名前は帯に隠れて読めない。これはいかなる販売戦略によるものか、考えてみるのもまた一興だろう。
ALL REVIEWSをフォローする