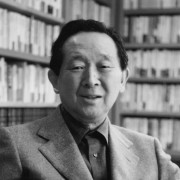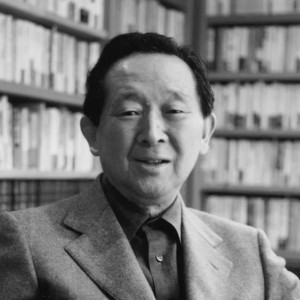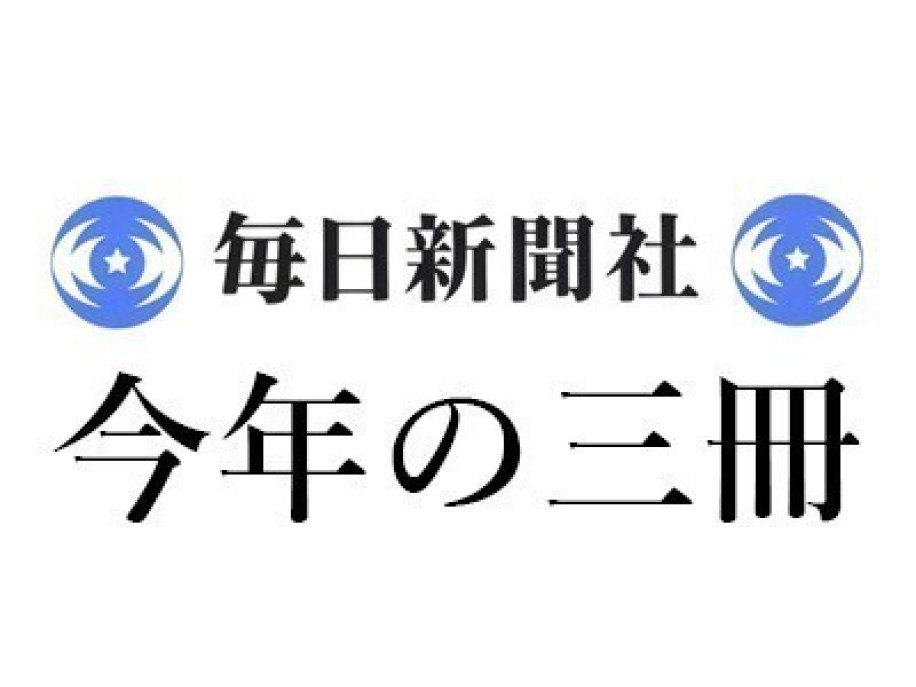書評
『真昼へ』(新潮社)
この作品のなかで、時間は通常の時間としての流れ方をしていない。それは、思い惑い、嘆き、夢を見る作者と一体になって、遡行したり渦を巻いたり、奔流のように溢れ出したり、じっと澱んだりしている。時間は鏡になって主人公の記憶の断片を映す。
突然の不幸に見舞われた時、人間は生命のはかなさを知り、絶望からの救いをいろいろなものに求めてきた。我が国においてもヨーロッパにおいても、中世の人は死を親しみ深いものとして受けとめてきた。死者は、西方浄土に旅立ち、神の国に召されたのだ、という宗教的な意識の存在は、彼等が(妙な表現だけれども)近親者の死の悲しみ方、自らの死を受容する方法を知っていたことを示している。
こんなことを書くのは、九歳になったばかりの息子を失った主人公の母親の死への態度のなかには、まざれもなく現代が映し出されていると思うからである。
作者は、通常の、誤魔化しと紙一重の嘆き方をきびしく拒否する。「苦労すると、それだけ人はいい顔になる」というような〝気くばり〟的発言に対して、作者は作中の私に「それは嘘よ、それだけ汚い顔になる」と主張させる。と同時に、私の母親は「思わぬ悲しみに会った人はかえって陽気だ」とも呟く。この、互いに予盾する意見は二つとも説得力を持っていて、息子の死の衝撃がいかに大きかったかを物語る。普通、死は、生きている人間にとっては他人事なのであり、それだから悲しみに同調してみたり、装った嘆きをまとうこともできるのであったが、母親にとっての我が子の死は、どうも他人事ではないらしいと分ってくる。
作者は表題作「真昼へ」のなかで白アリとヤモリにことよせて生と死の巡りゆきをまず暗示しておいて息子の死へと筆をすすめる。それはあたかも生態系の狂いであったかのような印象を読者に与える。作者の喩は、表現様式としての喩の域を超えて、発想の喩、といった性格を備えているので、読む者の意識の暗部へと働きかけるようである。その暗部から「無言のまま、そうして朽ち果てていくだけの家なのだ」との想いが顔を現し、その想いは、私の離婚につながったり、「世間が単純に心中事件と断定した」母親の連れ合い(私の父親)の死の思い出を呼び醒ましたりする。これらの連想は、「自分には子供を育てる条件がない」と思う夢と絡まって主人公を悩ませる。
ここには息子の突然の死によって夜の安らぎを奪われた若い母親の姿がある。その悲しみは、現代に生きる者には悲しみを容れる箱が与えられていないことを報せることによって、同時代人への問題提起になっている。私達は真昼へ、光り輝く中へ逃げ出す以外に憩いの夜を持つことができないのだ。しかしその光はなんと暗いことだろう。たとえ子供の追憶だけが眩しく輝いているとしても。
【この書評が収録されている書籍】
突然の不幸に見舞われた時、人間は生命のはかなさを知り、絶望からの救いをいろいろなものに求めてきた。我が国においてもヨーロッパにおいても、中世の人は死を親しみ深いものとして受けとめてきた。死者は、西方浄土に旅立ち、神の国に召されたのだ、という宗教的な意識の存在は、彼等が(妙な表現だけれども)近親者の死の悲しみ方、自らの死を受容する方法を知っていたことを示している。
こんなことを書くのは、九歳になったばかりの息子を失った主人公の母親の死への態度のなかには、まざれもなく現代が映し出されていると思うからである。
作者は、通常の、誤魔化しと紙一重の嘆き方をきびしく拒否する。「苦労すると、それだけ人はいい顔になる」というような〝気くばり〟的発言に対して、作者は作中の私に「それは嘘よ、それだけ汚い顔になる」と主張させる。と同時に、私の母親は「思わぬ悲しみに会った人はかえって陽気だ」とも呟く。この、互いに予盾する意見は二つとも説得力を持っていて、息子の死の衝撃がいかに大きかったかを物語る。普通、死は、生きている人間にとっては他人事なのであり、それだから悲しみに同調してみたり、装った嘆きをまとうこともできるのであったが、母親にとっての我が子の死は、どうも他人事ではないらしいと分ってくる。
作者は表題作「真昼へ」のなかで白アリとヤモリにことよせて生と死の巡りゆきをまず暗示しておいて息子の死へと筆をすすめる。それはあたかも生態系の狂いであったかのような印象を読者に与える。作者の喩は、表現様式としての喩の域を超えて、発想の喩、といった性格を備えているので、読む者の意識の暗部へと働きかけるようである。その暗部から「無言のまま、そうして朽ち果てていくだけの家なのだ」との想いが顔を現し、その想いは、私の離婚につながったり、「世間が単純に心中事件と断定した」母親の連れ合い(私の父親)の死の思い出を呼び醒ましたりする。これらの連想は、「自分には子供を育てる条件がない」と思う夢と絡まって主人公を悩ませる。
ここには息子の突然の死によって夜の安らぎを奪われた若い母親の姿がある。その悲しみは、現代に生きる者には悲しみを容れる箱が与えられていないことを報せることによって、同時代人への問題提起になっている。私達は真昼へ、光り輝く中へ逃げ出す以外に憩いの夜を持つことができないのだ。しかしその光はなんと暗いことだろう。たとえ子供の追憶だけが眩しく輝いているとしても。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする