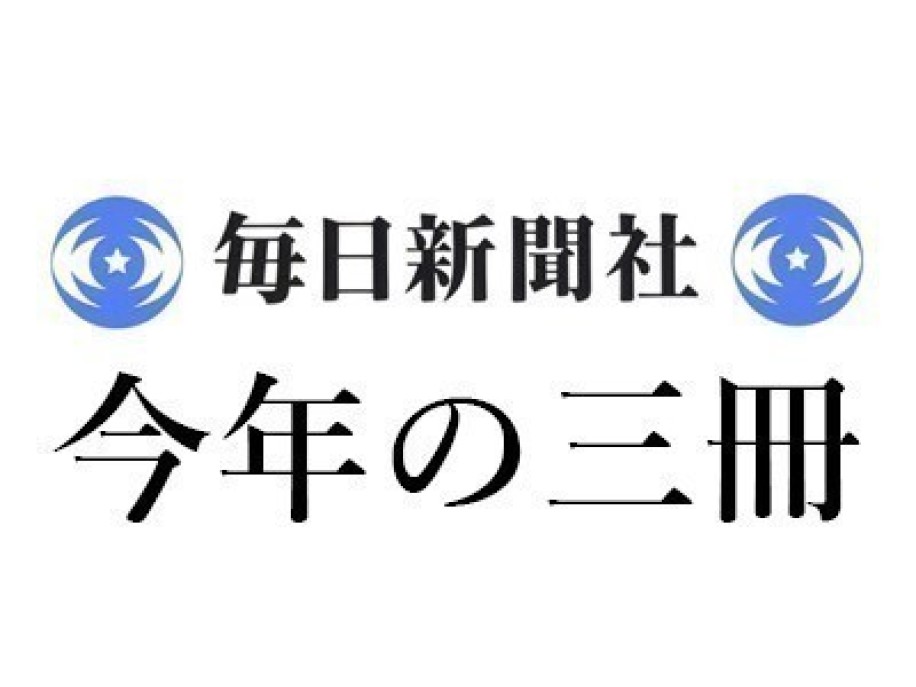書評
『日光』(朝日新聞社)
闇のなかの堂々めぐり
十一月中旬、降りしきる雨の一日、文筆を生業としているらしい五十過ぎの男が、三十そこそこの恋人X+C子――エクスタシー子!――を想いながら、彼女が残していったハーレクイン・ロマンスを読んでいる。マニュアルに沿って量産される恋愛小説の筋書きを冒頭に置くという、そんな意表をついた仕掛けの必然は、しかし『ハムレット』が持ち出されたところですぐさま明らかになる。いずれも身内の復讐劇を大枠とする物語なのだ。数ヵ月前、語り手ははじめてこの著名な芝居を観てテキストに興味を抱き、複数の翻訳を比較した末に坪内逍遥の訳を選ぶと、そのコピーを持ち歩いて台詞を暗記するほど夢中になる。あたらしい日本語を創り出すために雑多なジャンルからさまざまに言葉を取り混ぜて磨きをかけた逍遥の翻訳は、その後あちこちに引用されて物語の基調をなし、「存ふるか......存へぬか......それが疑問ぢや」と問いかける主人公の述懐も、たんなる参照物の役割を超えて、語り手の心象に大きな影響を及ぼしていく。
もっとも、ハーレクイン・ロマンスの紹介に触れた読者は、復讐劇に発展するならするでそれなりに見慣れた動きがあるのではないかと、きわどい渾名をつけられた女性と語り手の行く末をまず期待するだろう。ところが物語はここで先の読めてしまう安手のラヴ・ロマンスから一挙に飛躍して、破天荒なSF仕立てとなるのだ。部屋の天井からぽたりと落ちかかる水滴がとつぜん小さな石と化したかと思えば、そこには奇妙な老人が乗っていて、この老人に誘われるまま唐代の奇譚のごとく飛び立つと、舞台はいつのまにか“日光”になっている。
過激な場面転換の直後は、さすがにこれが幻想なのか現実にあった過去の出来事なのか判別がつかないのだが、ハーレクインの磁力はわずかに残っているのだろう、語り手は太郎杉の下でX+C子と待ち合わせていて、約束の時間に彼女の姿が見えないので仕方なく東照宮や華厳滝などの名所旧跡をめぐる。もちろん漫然とした散策ではない。天を駆って彼を導いてくれた先の老人が明治の洋画家・小杉未醒の絵のなかの人物であり、飛翔の途上で出会った大男が日光山を開山した勝道上人であるなどと、荒唐無稽ながら納得のいく辻褄合わせが披露されるからだ。
復讐譚の悩める英雄としてのフランケンシュタイン、謀略の先兵ともなった豊臣秀頼の妻千姫、ほかならぬ『ハムレット』の登場人物であるホレーショの名を遺言に書きつけて華厳滝に身を沈めた藤村操、あれやこれやと訓戒を垂れる、見ザル、言わザル、聞かザルの三猿。虚構と実在の人物が入り乱れるにつれて語り手そのひとの自我はあやふやになり、おまけに待ち合わせ場所に来なかったX+C子が一週間前に死んでいたと判明するに至って、夢幻と現実、現在と過去の境界のはざまの生々しい感触がにわかに沸き立ってくる。
雷雨のなかで出会った少女に「オバケ」と言われ、際限なく食べる米の飯で身体を膨張させながら前世はなめくじだったと嘯(うそぶ)く語り手は、もはやこちら側と向こう側のどちらにもつくことができない存在となっている。「なめくじにも戻れぬ、人間にも戻れぬ、そしていまや皺くちゃな生き物」にまで堕し、真っ暗な部屋で息をつめて逼塞していたいという「獄舎願望」さえ芽生えて、その監獄にも比すべき自室でXとCに分裂したX+C子としばし共生しつつ、周囲の闇だけは晴らすことができない。
この闇の閉塞を打破する唯一の解決策は、たぶん「死」を措いてほかにないだろう。フランケンシュタインもハムレットも藤村操も、それぞれの業を断ち切るために、夢と現実が異なることを明確に意識したうえで、自死を選んだのだ。ならばおなじ近代人として二十世紀末を生きる語り手は、どう対処するのか。頼れるものがあるのか。
まずは、言葉遊び。逍遥訳が発表される前に投身した一高生の名にひっかけて「操を堕す美の力は美を引上ぐる操の力の幾層倍ぢや」と呟く、時間軸を無視した語呂合わせがその好例だ。いまひとつは、ユーモア。藤村操が死への道すがら羊羹を五本買ったとの新聞記事に着目して、この異様な買い物の真意を探ろうとするあたり、痛ましさの陰でふっと笑わせてくれる。
だがこのふたつの要素をちりばめて、いわば世紀末バロック小説の体裁を整えながらも、本書には底なしの淋しさが漂っている。生死の境を問わない神仏に取り巻かれた“日光”は、そうした孤独に耐える語り手の彷徨に不可欠のジャンプボードだ。日の光どころか、内側を巣くう闇のなかでの堂々めぐり。それは彼のみならず、私たちすべてを待ちかまえている運命なのかもしれない。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする