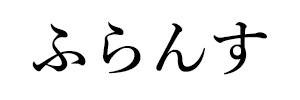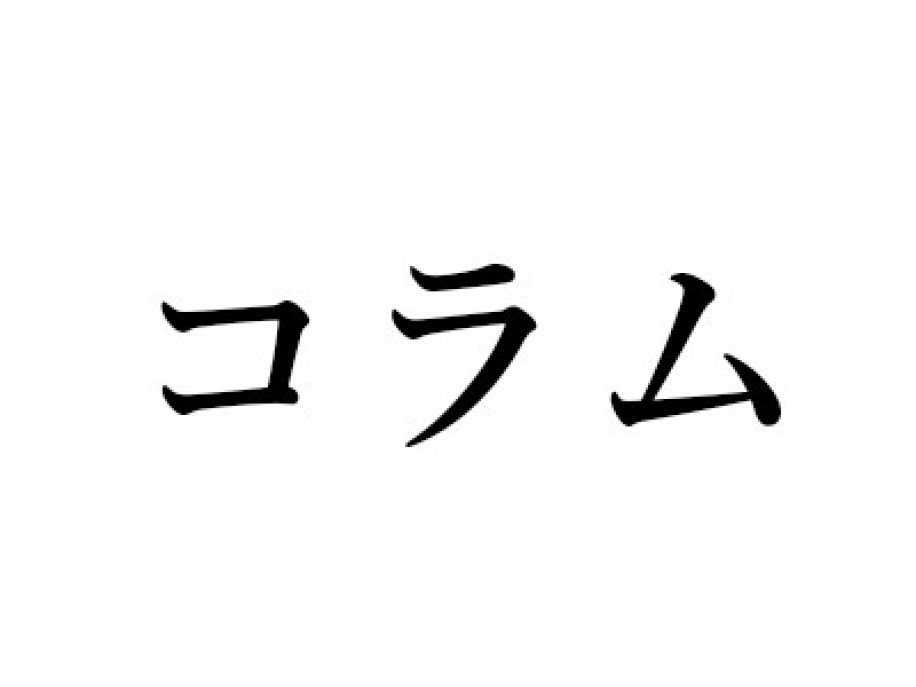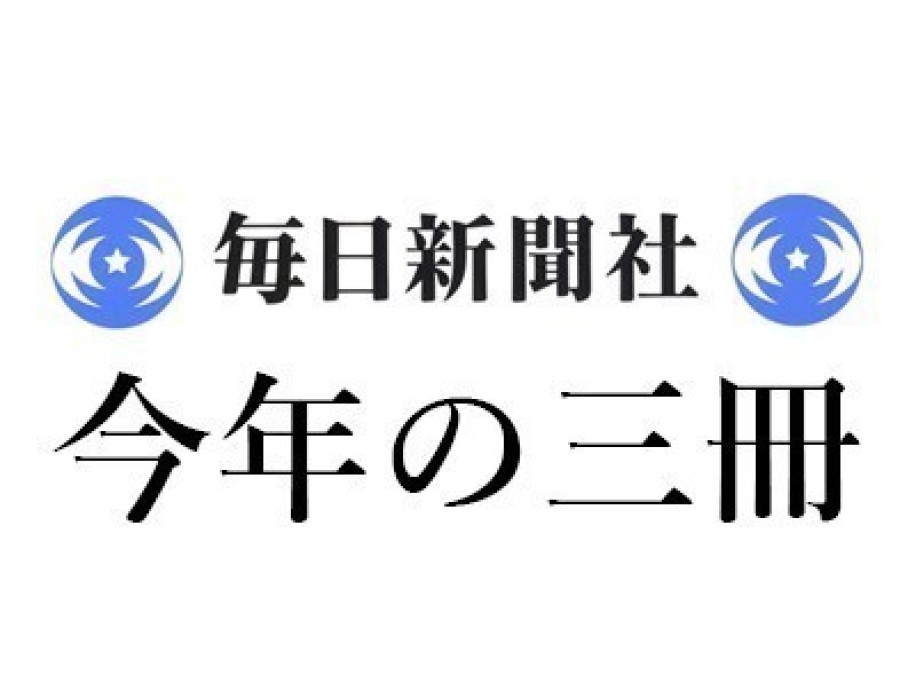書評
『ビールの最初の一口―とその他のささやかな楽しみ』(早川書房)
仮定で語られる人生
日本文学には「随筆」という奥深いジャンルの伝統がある。『枕草子』から『方丈記』を経て『徒然草』へ。ときに斬新な視点で読者を驚かせたり、郷愁を誘う筆致でほろりとさせたりする小さな物語風の文章の水脈は、多少の進化と退化を反復しながら、現在の文芸雑誌や小説誌の穴をうめる見開き頁にしぶとくあたりまえのように生き延びており、形式そのものが注目を集めることはほとんどないと言っていい。ところが、書きものといえば長篇小説を意味する現在のフランスで、アランでもポンジュでもないれっきとした小説家が、器としてことさらに短いテクストを選択し、丹精込めて書きあげたとしたら、これはもうまちがいなく一種の反動的な行為であり、またある意味で計算ずくの試みにもなるのである。フィリップ・ドレルム『ビールの最初の一口とその他のささやかな楽しみ』は、ここ数年、フランスで目立ちはじめた断章形式への寄りかかりをいっそう身近なものに変貌させた象徴的な作品だ。カフェではごく日常的に飲まれているにもかかわらず、ビールの普及度を認めることがワインの国としてなんとなくおもしろくないというフランスでこそ魅力的に響く表題の是非はともかく、原書では《物語 (レシ)》と明記されている三十四篇の散文からたちのぼってくるのは、清少納言の自己顕示欲とも、この分野の先達ジャック・レダの韜晦を支える穏やかな羞恥心とも、まして『中二階』のニコルソン・ベイカーが繰りひろげた雑貨や事物への執着ともちがう、適度に醒めたいかにもフランス的なひねりに独自の体温を加えた歳時記である。
それにしても、なんと慈味深い話題の選択であることか。老年と少年時代をともに抱えこんだオピネルのナイフ、朝の散策をいっそう軽やかにする日曜日の朝のケーキ、歩きながら食べるふわふわのクロワッサン、「内部のメトロノーム」に時間をゆだねるエンドウの莢むき、「時代遅れの甘さ」に浸ったポルト酒、「さりげなく記憶の道を粉ひく風車のようなモーターのリズム」に刻まれた自転車のダイナモ発電器。「気取りは、ごく平凡な暮らしの象徴とむすびつくとき、香りたつ」とはさりげなくも鋭い指摘だが、その気取りはドレルムのなかで、慌ただしい現代の暮らしにひっそり眠っている過去の痕跡を探る方途として生かされている。
ファクスで用を済ませる点と点のあいだの線分でしかない時間にあらがうというより、その流れからわざとはずれて「内部のメトロノーム」を修復すること。世の妄言にはもう耳を貸すまい、信用できるのは内なる声だけ、地下室に眠っている林檎が放つあの「内部の匂い」だけなのだ。ドレルムの筆の表向きの甘さは、バナナ・スプリットのそれとはべつのものであって、彼が提示してみせるのは、あくまで「仮定で語られる人生」にすぎない。目のまえにある光景をいったん破棄し、再構成しなければ生まれてこない架空の人生、自己満足に陥らずに「自分だけの料理をこしらえ、自分だけでうまいと思う」姿勢を貫くことはけっして容易ではない。ノンシャランスを装いつつ、現代をあたたかい「仮定で」とらえざるをえない一種の諦念に支えられてもいるドレルムの試みは、したたかな逆説なのである。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする