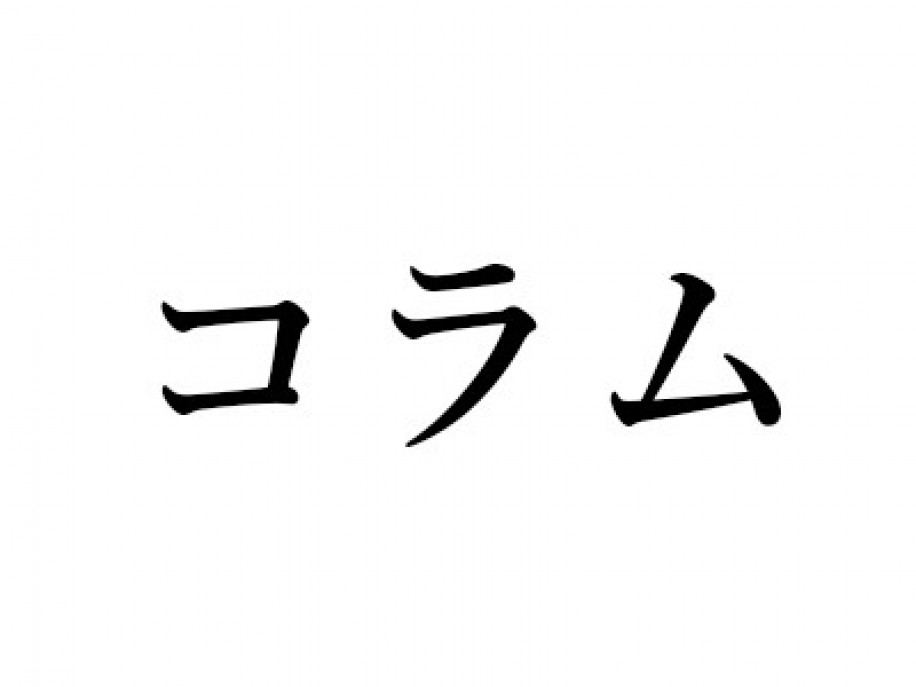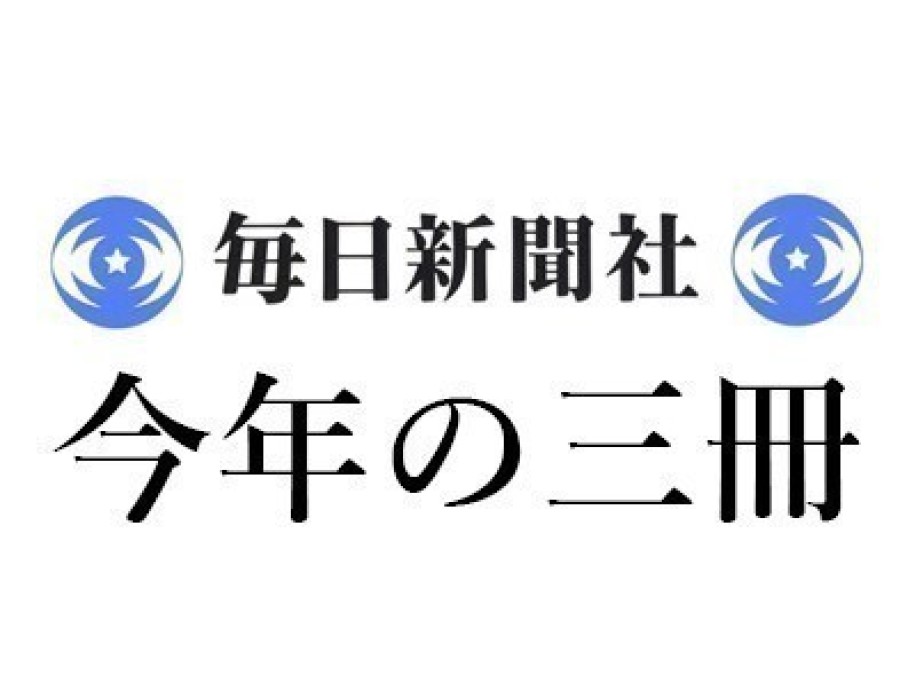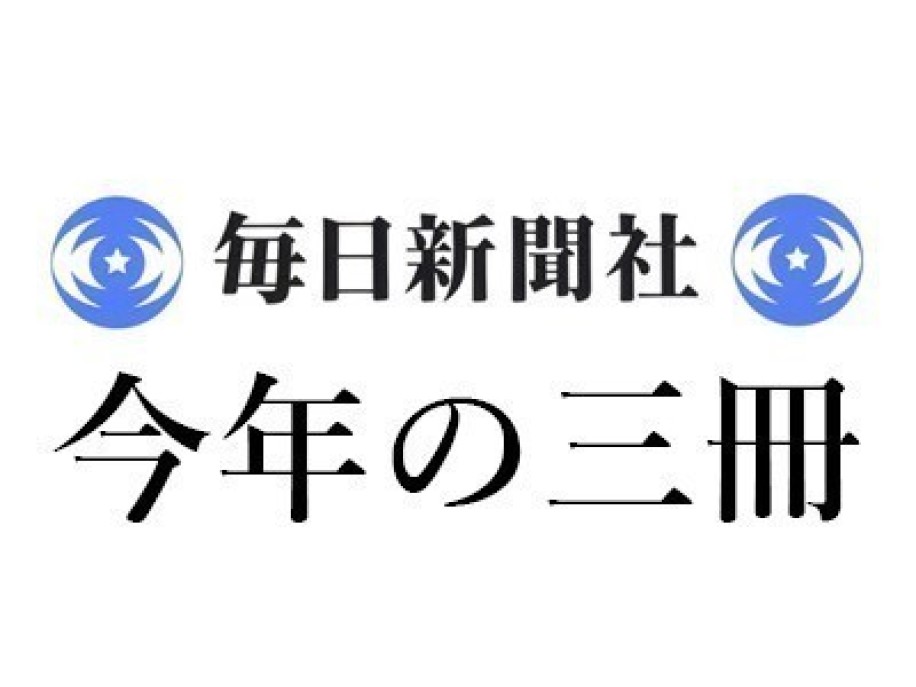書評
『日本の異端文学』(集英社)
山田風太郎は異端か
いつだったか、コラムニストのえのきどいちろう氏に「せめて本ぐらい好きに読ませてよ。世の中、ままならないことばかりなんだから」と言われ、深く、深く、うなずいた。そうだ、本ぐらい自由に読みたい。ためになる本だの、役に立つ本だのはごめんだ。『日本の異端文学』で川村湊が紹介するのは、著者が隠れるように読んできた、ためにもならなきゃ、役に立つわけもなく、読んでほめられるどころか叱られる小説の数々である。作家名を挙げると、中井英夫に山田風太郎、小栗虫太郎、あるいは国枝史郎、三角寛に、宇能鴻一郎、団鬼六など。
ここでの異端とは、川村の定義によると「文学それ自身(の有用性や社会的評価)を白眼視する文学」、私流に言いかえるなら、斜に構えたような後ろめたさを持つ小説群だ。芸術としての完成度を目指すわけでもなければ、娯楽としての成熟を徹底させるわけでもなく、それでも書かずにはいられなかった人々である。
と、書いてきて、ここで私は奇妙なことに気づいた。中井英夫や山田風太―郎は異端か? たしかに文学史的にはそうかもしれないけれども、われわれ一般の本好き、小説好きの間では、むしろ彼らこそがメジャー作家であり、たとえば芥川やら白樺派やらを読んでいる人のほうがよほど異端な読書家である。いつのまにか正統と異端が入れ替わっている。そして、それは小説だけでなく文化一般にいえることで、しかもその入れ替わりの時期は、一九六〇年代から七〇年代にかけてなのだと、本書を読むとよくわかる。
その異端の読み方が大きく変わってしまったらしい、と痛感させるのが東浩紀の『動物化するポストモダン』(講談社現代新書)だ。オタク系消費者たちは作品の物語性や作者の世界観を味わうのではなく、データベースにアクセスするように作品に接する。それはくノー(山田風太郎)や机龍之助(中里介山)やサンカ(三角寛)の世界に溺れるのと似ているようで違う。
ALL REVIEWSをフォローする