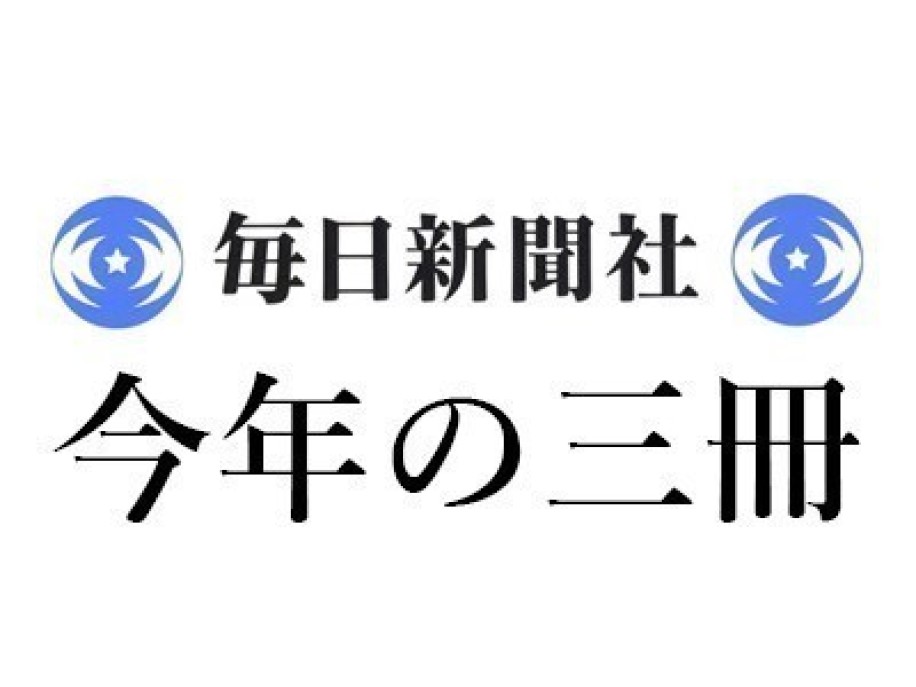書評
『ベネディクト・アンダーソン グローバリゼーションを語る』(光文社)
新書という器を生かした「古典的名著」への再入門
アンダーソンの『想像の共同体』は、83年に発表されるや政治学という枠を超え強いインパクトをもたらし、瞬く間にナショナリズム研究の古典と位置づけられた。本書は05年に早稲田大学で2日間にわたり行われたアンダーソンの講義録だが、その古典的書物に著者自身が批判的な検討を加え、展開のヴィジョンを示す内容となっている。さて、古典の多くの例に漏れず、『想像の共同体』を実際に読んだ人というのはそれほど多くないだろう。だいたい本屋に行っても売ってないし(絶版である)。が、ニューアカやカルスタ・ブームのおかげ(?)で、「国民とはイメージとして心に描かれた想像の政治共同体である」という根っこの主張(だけ)はそれなりに人口に膾炙している。
ようこそ。そんなハンパな聞きかじりさん――ということはおそらくほとんどの人ということだけど――こそ本書の読者だ。正直アンダーソンの講義はわかりやすいとはいいがたいのだが、編著者である梅森直之の解題「アンダーソン事始」が見事で、『想像の共同体』の概説はもちろん、アンダーソンが自論のどこに反省の必要を覚え、どこに向けて展開しようとしているのか、見晴らしのいい鳥瞰図を示してくれる。
アンダーソンの目指すのは、グローバリズムという現象を人と人とのネットワークとして歴史的に捉え直すこと、その上で、ナショナリズムがじつはグローバリズムを基盤とするコミュニケーション(の一形態)であったことを示すこと、となるだろうか。それはすなわち、いま世界で進行しつつあるナショナリズムにいかに対峙していくかを考えることにほかならない。
本書に先だって、やはり光文社新書からほぼ同じ構成の『スティグリッツ早稲田大学講義録』が出ている。これも良い本だった。新書という器の新たな利用方法として歓迎したい。スティグリッツとかアンダーソンとか読むの大変だしね(笑)。
初出メディア

Invitation(終刊) 2007年8.9月号
ALL REVIEWSをフォローする