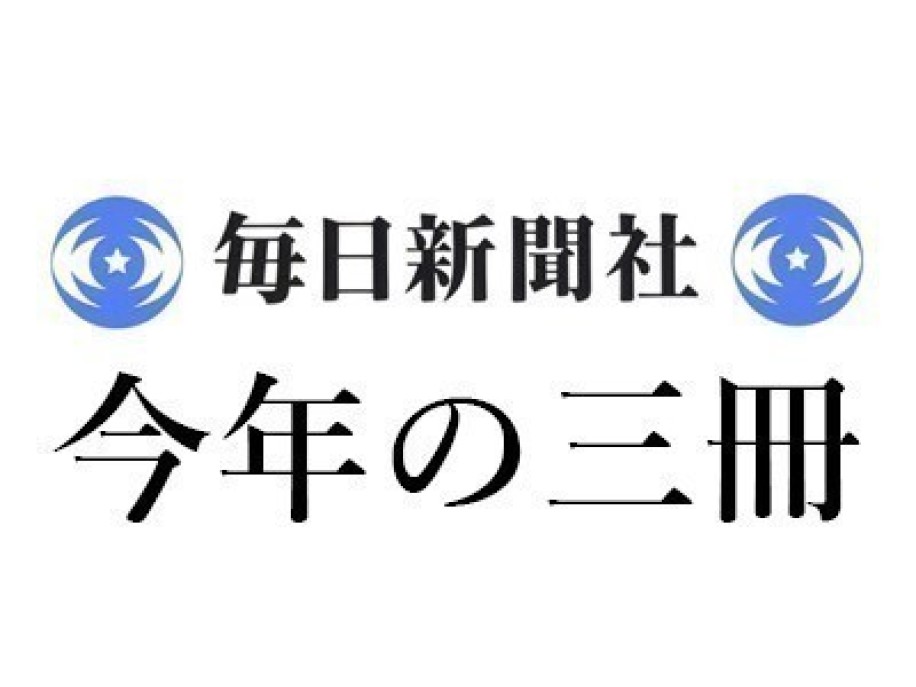書評
『みるなの木』(早川書房)
椎名誠の「或る戦後」
いつだったか椎名誠さんにお会いした時「ぼく、椎名さんの小説では『武装島田倉庫』がいちばん好きなんですよ。あれはほんとに超・超傑作ですよねえ」といったら、椎名さんは「ありがとう、でも書くのたいへんなんですよ」とおっしゃったのだった。その椎名さんの新刊『みるなの木』(早川書房)に収められた十四の短編のうち四編が『武装島田倉庫』の「シチュエーションの延長」だ。もう一つ「対岸の繁栄」という短編にもその雰囲気があるが、これは名作『アド・バード』もそうだったように椎名SF全体に漂う雰囲気の一つといった方がいいのだろう。
『武装島田倉庫』は或る「最終戦争」の後の「戦後」を舞台にしている。そこでは、とにかく途轍もない「最終戦争」があって世界は破滅寸前になり、生き残った連中が必死になって生存のための闘争を繰り広げている。あやしげな人間たちやあやしげなものたちがどかどか現れ、あやしげな事件が起こる。
売る物は張伯達に作り方を教えてもらった。張は鳥獣仕掛けの靡爛(びらん)内爆弾で皮膚から筋肉まですべて灼(や)け爛(ただ)れてしまったので、全身解体手術を受け、今では脳髄だけだ。それでも脳髄だけでも残っていれば、政府の集合思考慰撫(いぶ)センターが再開復活するとそこでの仕事に優先就業することができる。
……。
張が教えてくれたのはこの地方(あたり)に沢山群生している火焔麦(かえんばく)と野生化したバイオ果球、タマニギリの実を粉にして、そこからある種の饉飩(こんとん)をつくることだった。火焔麦の穂は小さくて実が薄く、たとえそれを粉にしても色が毒々しいまだら紅梅なので、使い方が難しい。しかしこれにタマニギリの実を粗く粉砕したものを加え、半如水(はんにょすい)で捏(こ)ねて熱を加えると、赤紅色が相当に薄くなり、不思議にねっとりとした芳香をたてるようになる。そうして出来た饉飩は、そのままにしておくと固くひきしまり、数日間は日保(も)ちする。(「饅鈍(こんとん)商売」)
椎名さんの小説はSFでなくても、想像力を大胆奔放に解き放つ。どこまで飛んでいっちゃうのという感じになる、しかし、この「或る戦後」シリーズでは、その大胆奔放をコントロールしている重力のようなものを感じる。だから椎名さんも「書くのはたいへん」とおっしゃったのだろう。解き放たれた想像力を引き戻す重力はいつも「現実」である。けれども、それはふつう一般に使われる「現実」とは若干違う。つまり、作家にとっての「現実」なのだ。
「或る戦後」の椎名さんは、ゆっくりとその世界を自信を持って歩いている。それは、その世界が椎名さんの「現実」だからではないかと思う。つまり、そこは椎名さんの想像力がいちばん休まる場所なのだ。休まる場所とは懐かしい場所でもある。そう、ぼくは「或る戦後」を読んでいるとひどく懐かしい気がする。それは未来であるのに遠い過去のようだ。だからといって、この「或る戦後」を、実際にぼくたちが遭遇した昭和二十年以降の戦後の比喩だというわけにはいかないだろう。椎名さんは、現実の戦後を懐かしくも同時にうんざりだとも思っていたはずである。だから、これは理想の「戦後」の姿でもあるのだ。「理想」の戦後。それは徹底的な破滅によってしか訪れぬ世界であり、ぎらつく生命力を持つ者しか生き残れぬ世界でもある。
「こんな世界は一回きっちり滅びた方がいいぞ」椎名さんはこういっているのだ。ひこひこ笑って読んでる場合じゃないんだよな。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする