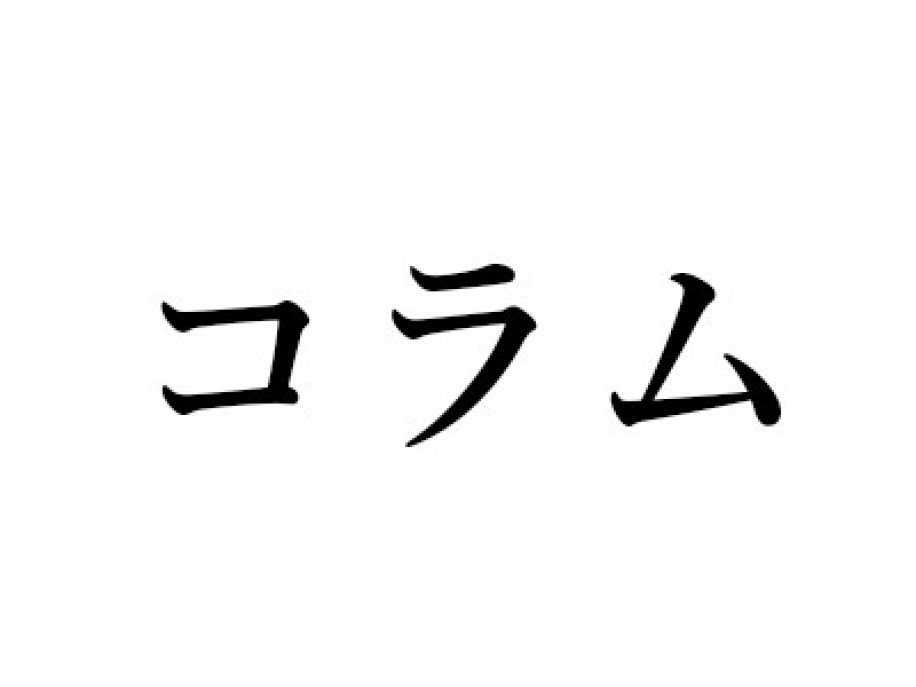書評
『母という経験―自立から受容へ 少女文学を再読して』(学陽書房)
少女からの旅立ち
幼いころに両親の離婚を体験した著者は、これまで壊れた愛をとりつくろう近代家族の欺瞞(ぎまん)を突き、女性の自立を論じてきた。しかし、これは、なんというやさしい本であり、語り口の変化だろうか。宮迫千鶴の『母という経験』(平凡社)は『若草物語』『秘密の花園』『小公子』をはじめ名作少女文学を再読しながら、昨日の自分を思い出し、成熟を確認していく。「スミレクリーム」「白い夜会服」「そば粉のパンケーキ」「カエデ糖のシロップ」などかつての憧れもまぶしてあって、それだけでも共通の読書体験を持っていれば懐かしいが、少女時代に読みすごしていたものを気づかせてくれる本だ。
たとえば『アルプスの少女ハイジ』はそれぞれ心に灰色の影を持つ登場人物の「癒しの文学」とみる。『小公女』のセーラの「変わったうつくしさ」の秘密は「父に育てられた娘」の少年精神だという。また「十八年にただ一度の冒険もない、単調な子供時代」を孤児院で過ごしたジュディへの「足ながおじさん」最高のプレゼントは、自然と愛と冒険に満ちた「夏の農場生活」ではなかったかということ。いずれも盲点直撃でうなづかされ、俄然、少女本を再読したくなった。
『ふたりのロッテ』に著者は「なにしろ本当の人生ではこうはいかない」とため息をつく。ふたこが入れ替わって離婚した両親をふたたびくっつけちゃうというのだから。しかし母親に育てられ女性原理を育まれたロッテと、父親に育てられ男性原理を豊かにしたルイーゼが入れ替わり、おたがいを演じることで二人とも「両性具有」となり、両親も離婚とシングルペアレントを経て「性別役割分担」から脱け出し、一家みんな自立して、よりを戻しての再婚生活はずっと豊かになるだろう、とはなんとちゃっかりして夢のあるご託宣であろう。
とはいえ一番胸を打つのは、著者自身の自立から受容へ、性急から成熟への変化を語る序章「母という経験」である。「幸福になるためのすなおさ」を卑俗でなく描いて、著者は激しい問題提起者の座を降り、新たな広汎な読者を獲得したようにみえる。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする