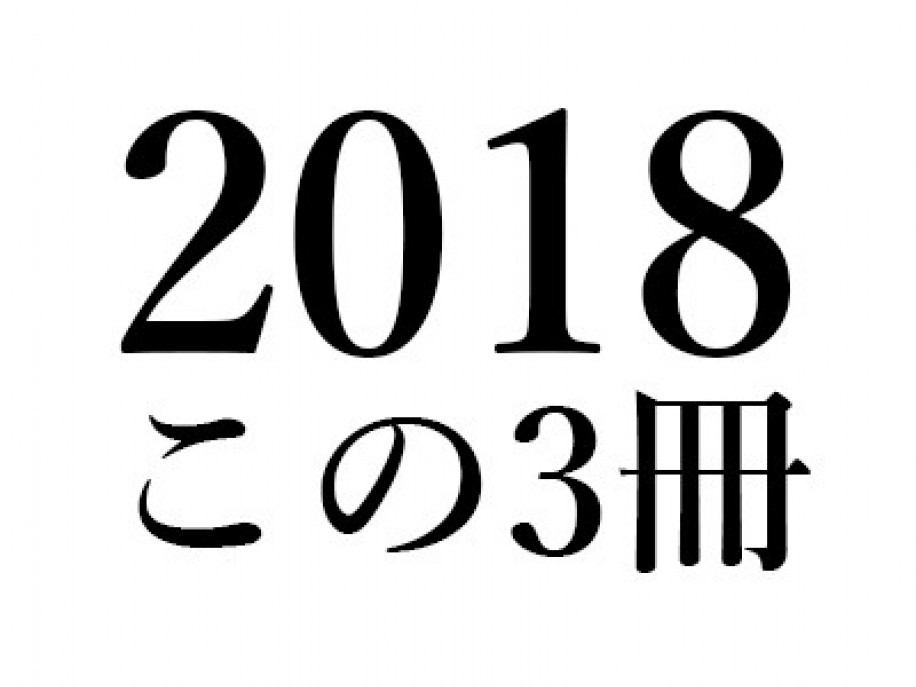書評
『日本史の黒幕』(中央公論新社)
豊かな歴史学を形作る碩学の融通無碍な鼎談
そうだ、これだよ、懐かしいなあ。会田雄次、小松左京、山崎正和。3人の碩学(せきがく)の1976~78年の鼎談(ていだん)が、文庫になっての再登場である。日本史の黒幕という書名だが、実は黒幕だけが主題ではない。日本史全般を、人物に焦点を当てながら、ときに世界史まで話を広げ、古代から現代まで縦横に語り尽くす。さて黒幕が話題になるや、3人は忽(たちま)ちに1.汚れ役型、2.参謀型、3.元老型の三つを挙げる。これは機能からの分類で、1.には後白河法皇、3.では西園寺公望らの名が挙がる。他に資格からの分類として、(1)政治的実権を持つ資格に欠けるタイプ、(2)政治的能力のうちの何かが決定的に欠けるタイプ、(3)政治を汚いものと認識するために身を引きたがるタイプが提示される。(1)には黒衣の宰相と呼ばれる僧侶、(3)には西郷隆盛が当てはめられる。3人の意見は相違点を持ちながら、共通理解を瞬時に導き出す。豊かな知識量と強靱な論理性には驚嘆するほかない。
10代の私はこうした書物を熟読し、会田先生たちに憧れ、日本史の研究者を目指した。だが、3人がみな日本史学者でないことが物語るように、当時の日本史研究は別の方向に舵を切っていた。いわく、歴史の主人公は英雄ではなく、無名の庶民である。いわく、文献資料に基づかないことを語るのは科学的=学問的な態度とはいえない。
現在、歴史学は暗記物として子どもたちに嫌われている。教科書はもちろん大切だが、本書のような融通無碍(むげ)な考察もまた、立派な歴史ではないのか。はっきり言って、これほど実りある鼎談をしてのける研究者は、今ほとんど見当たるまい。どうしたら豊かな歴史学を再構築できるのだろう。歴史に活気を取り戻せるのだろう。本書を読み直し再考した。
ALL REVIEWSをフォローする