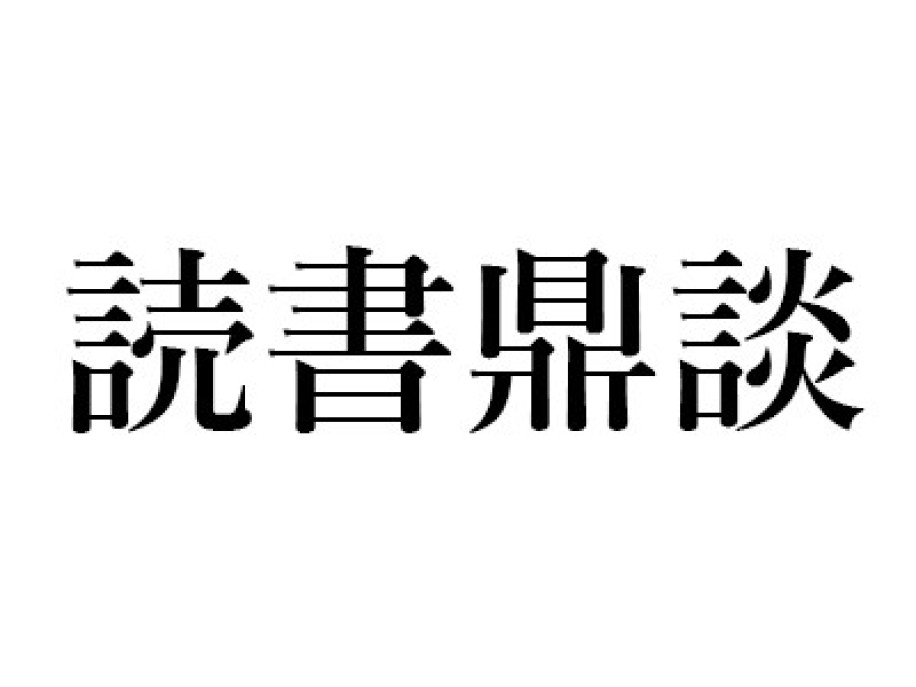書評
『手縫いの旅』(新潮社)
おもわず縫物がしたくなる
縫う、という手仕事はひとりっきりの仕事。ときに誰かに話しかけたくなって座を立ち、旅に出てしまい、その地で縫い仕事をする人に出会い、なじみになる。それぞれの気候や風土の中でどの人も必要から針を運びながら、つましく生きている。私はその姿に支えられながら歩いてゆく。
どうでしょう。何一つ、むずかしい言葉、わざとらしい言葉はない。でもリズムがあって、ちゃんと選びぬかれていて、著者の思いがそくそくと伝わってくる。こうじゃなくちゃ、と思います。
『手縫いの旅』(新潮社)。森南海子さんの文章は洗いざらしの木綿のようにゴージャス。見かけ倒しがなくって、だけど織りは複雑で、しなやかで、刺子の目も生きている。読み込むほどに味の出る文です。
そしてきゃしゃな体を運んでふいっと旅に出る。
“今ならぎりぎり”という言葉にすがって青森に角巻き姿を見に行きます。大きな布を二つ折りにしてゆったり着る角巻きの保温力は抜群。でも上から羽織るので手が自由にならない不便がある。そこで南海子さん、工夫を加えて、切れ目を入れ、手を通して着る大型ケープを考案してしまいます。こんな風に各ページに、日本の風土に根ざした着る物が紹介され、写真と著者オリジナルの作り方まで載っているという、たいへん便利でお得な一冊です。
十代から手縫いの仕事を志し、リフォームを手がけてきたデザイナーの著者は、さながら日本の手縫いの文化の情報交差点。「春間近になってかえって厳しい寒さがやってきました」。肩冷えを気づかって、函館からは丹前がとどきます。
「みかんの摘果が始まりました。日差しの強い戸外での仕事なので、手甲は離せません」と和歌山からは新型の手甲。親指が日に焼けぬように、という女たちの思いが形となっていてハッとします。でも手甲は日よけ虫よけだけではないのよ、とつづけて冷房から腕を守るアームカバーが紹介される。都市のオフィスに働く女性への目くばりも、著者は忘れないのです。
「老いを飾る」の章には、たべこぼし用のエプロンやおしめのことも、わがことのようにさりげなくやさしく語られています。
私が一番、作ってみたくなったのは長崎・五島列島の「ドンザ」。洋風に説明すると「ウエストをブラウジングさせたブルゾン」のようなもの。この形にはわけがある。「かたし」とよぶ椿の実を女たちが採ってふところに入れるのです。
いまでも大切なものは、肌に近い内ポケットや胴巻きにして身につける本能を人々は持ち続けている。衣服の中に異物を入れると、人間の肉体の美しさが損なわれ、いびつなふくらみやみっともない形をつくりだすが、それさえが「生きること」の証しになっている。
やせてカッコよく、男にモテて、仕事ができそうに見えたい、という都会風のファッションが急に色あせて感じられる一節です。
木のぼりの好きな著者は、このドンザを着て椿にのぼり実を取りふところに入れます。
いくらもしないうちに腰のあたりにだるさを感じた。それは大地に向かってひき寄せられて行くような重量感と、孕(はら)んだ女たちの鈍い気だるさの入り交じったものであった。
ううっ……。私も、これを着て町を歩き、墓地のどんぐりだのじゅず玉だの、猫だのをふところに入れてみたいな。矢も楯もたまりません。
こんな風に、森南海子さんの本はいつも、「衣」のちがう側面を照らし出し、いかにも縫うのが簡単そうに挑発し、うきうきさせて、私の暮らしを変えてしまうのです。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
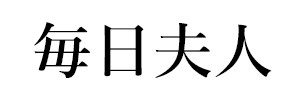
毎日夫人(終刊) 1993~1996年
ALL REVIEWSをフォローする