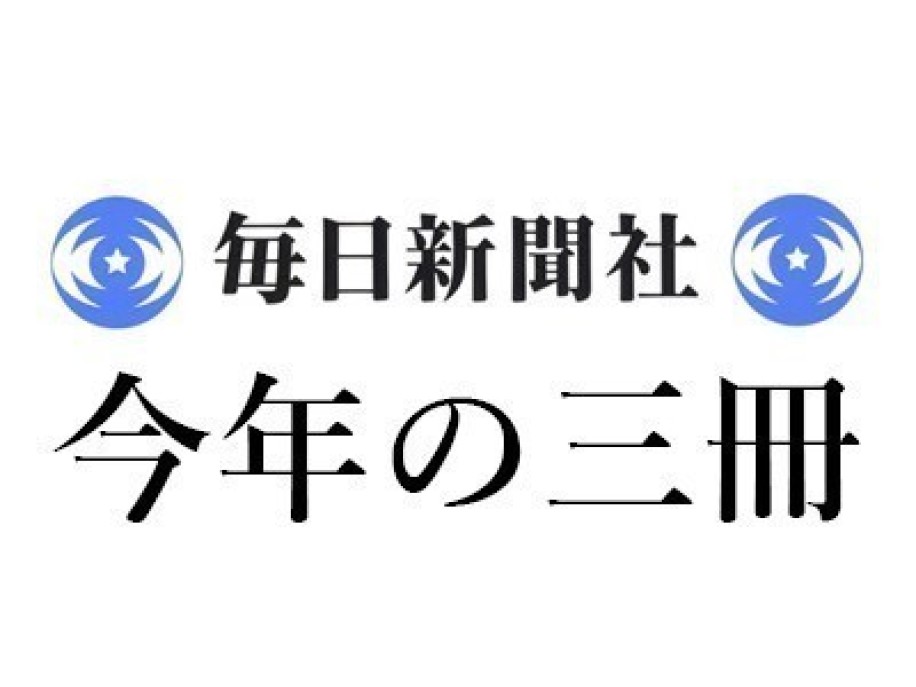書評
『坊っちゃんのそれから』(河出書房新社)
時代と人に思い馳せ
注意したいのは、タイトルが『続・坊っちゃん』ではないことだ。『坊っちゃんのそれから』で語られるのは、東京に戻った無鉄砲な坊っちゃんが、どのように活躍していくか、という話ではない。冒頭で作者は、松山に教師として赴いた坊っちゃんは、たった四十日で東京に戻ったことになると書く。そして『坊っちゃん』のラスト、簡潔に記されている、新橋に着いてから「其(その)後ある人の周旋(しゅうせん)で街鉄(がいてつ)の技手(ぎて)」となるまでには、八年が経過していることを史実を元に指摘する。そして物語は、山嵐と坊っちゃんが新橋に到着した明治二十八年十月十五日あたりからはじまる。
山嵐こと堀田銀蔵は、叔母の嫁いだ牧場で働いた後、富岡製糸所で職を得、そこで女工たちのストライキに巻きこまれ、退職させられる。その後、日本鉄道初のストライキ騒動のおかげで福島機関庫で機関助手となり、遊説にきていた渡米前の労働運動家、片山潜(せん)と会う。
一方、坊っちゃんこと多田金之助は、後の安田財閥を興した実業家、安田善次郎が創業した東京建物で不動産の営業をはじめる。再会した清(きよ)の縁で、彼も片山潜に会う。福祉事業のための施設をさがす片山潜に、キングスレー館となる土地と建物を紹介したのが、東京建物での坊っちゃんの初仕事である。
こんなふうに、坊っちゃんがその後暮らした東京が、実在の人物と史実を交えてじつに巧みに描かれている。労働運動が盛んだった短い時期を経て、治安警察法が公布され、東京市街鉄道が開業し、日露戦争がはじまり、ポーツマス講和条約に怒る国民が大規模な反対大会を起こし、アメリカから帰国した幸徳秋水はアナキズムへと傾倒していき、そして大逆事件へと時代は流れる。そんな時代のなか、坊っちゃんと山嵐は再会し、交友がはじまる。坊っちゃんは念願の清と暮らすが清は亡くなってしまう。山嵐は、スリの大親分、仕立屋銀次の元でスリとして働き、鉄道技手から刑事となった坊っちゃんは、若き大杉栄を何度も逮捕する。
東京で暮らす坊っちゃんの姿よりも、水紋のように広がっていく時代の流れに、断然読み応えがあるのだが、だからこそ、時代と人の関係に思いを馳(は)せる。当時の今を生きる坊っちゃんには、その時代は見えない。同様に、今自分が生きている時代を感じることはできるが、俯瞰(ふかん)することはできない。私たちはしっかりと個の目指すほうへ歩いているつもりだが、そのじつ、その日どこにいたか、何を見たか、だれと会って何を語ったか、何に憤り、何を信じて、何を嘘だと思ったか、そうした微々たるものごとにいちいち方向転換を余儀なくされ、また他者を無自覚に巻きこんで水紋を広げていくのだと思い知らされる。手にした新聞、乗った電車、通りすぎた公共施設、すれ違った美女、熱燗(あつかん)を飲んだ飯屋、まさにその「微々」こそが時代という巨大で強大なうねりなのだ。堀田がたまたま参加した新年会で、幸徳秋水が歌を詠み、ふざけてブリキ缶を投げ合ってはしゃぐ場面には、得体の知れない薄気味悪さがある。目指す場所が、見えざる手によって大きくねじ曲げられていくような薄気味悪さである。
史実とフィクションの織り交ぜられた妙を味わうこともできるし、大正へと向かう時代の空気を吸いこむこともできる。坊っちゃんや山嵐、その他彼らの出会う人々、みな何かあたらしいことを目指していた彼らの、青春群像劇として読むこともできる。当然ながら、没後百年の漱石先生へのオマージュでもある、新鮮な小説。
ALL REVIEWSをフォローする