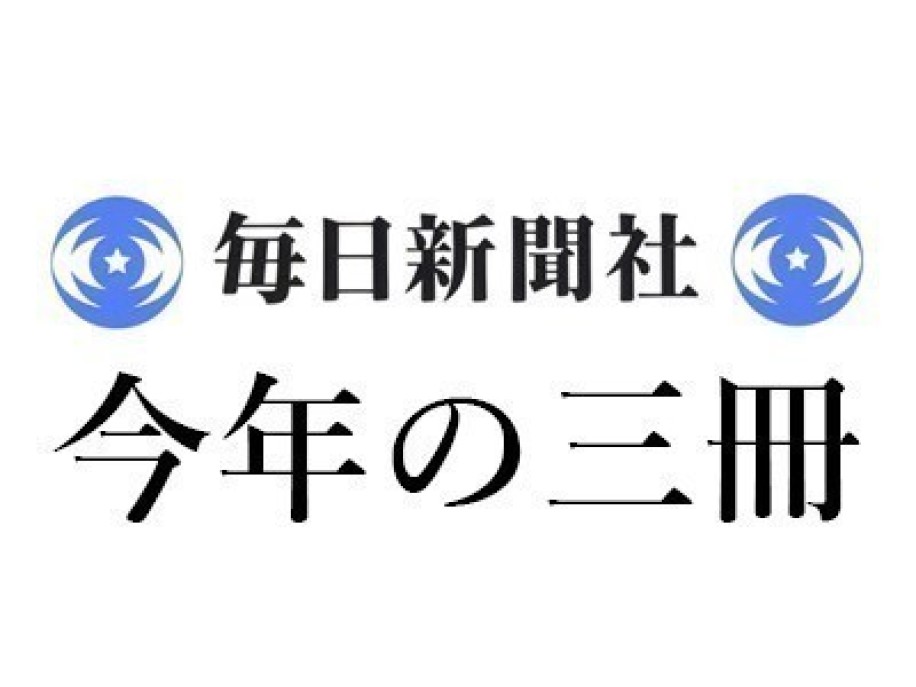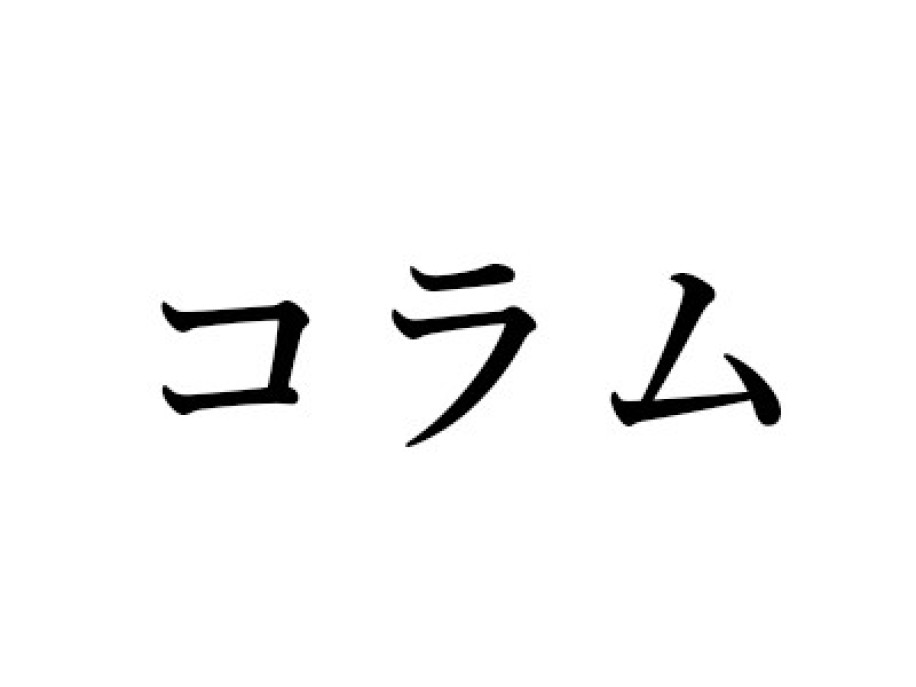解説
『恋衣』(勉誠出版)
『恋ごろも』山川登美子他
『恋ごろも』は明治三十八年一月、本郷書院から出版された。山川登美子、増田雅子(茅野雅子)、与謝野晶子の合同詩歌集である。収められた短歌は、山川登美子「白百合」百三十一首、増田雅子「みをつくし」百十四首、与謝野晶子「曙染」百四十八首。他に晶子の詩が六編載せられている。すでに晶子は歌集『みだれ髪』『小扇』『毒草』(鉄幹との共著)を出版しており、「明星」の大スターだった。その晶子と、中スター(?)くらいの登美子・雅子を組み合わせて「明星の女流パワー」を一気に見せつける――そんな思惑が、背景に感じられる。誰の思惑かといえば、もちろん「明星」の主宰者である与謝野鉄幹だ。
合同歌集というのは、合同であることをプラスに働かせなければ意味がない。歌壇に生まれつつある「流れ」や「動き」のようなものを、うまく結集させれば、一人一人がそれぞれの歌集を出すよりも、何倍もの力を発揮することができる。逆に「一人で一冊は無理なので、集まってみました」という感じを与えてしまうと、弱くなる。『恋ごろも』は、その点、かなり成功している歌集だろう。一+一+一が三以上の効果をあげている。
登美子や雅子は、晶子と名を並べることによって、注目もされただろうし、多くの読者を得たことだろう。三人が集合することによって、「明星」の女流ここにあり、といった花火を打ち上げる効果は大きい。
晶子はひっぱる役で何も恩恵を被らなかったかというと、そうでもない。鉄幹との燃えるような恋愛が一段落して、妻となった晶子。『みだれ髪』のような激しい恋愛の歌は、そうそう生まれるものではない。『恋ごろも』というタイトルだが、この集に収められている晶子の作品には、恋の歌が以前ほど多くない。かわって、恋愛以外をテーマにしたものに、多くの秀歌がある。
『みだれ髪』に酔った読者には、やはり晶子の恋の歌が読みたい、という気持ちがあるだろう。そのあたりのバランスをとるかのように、登美子には激しい恋愛の歌が多い。それもそのはずで、彼女にとってはこれが初めての歌集であり、かつての鉄幹をめぐる晶子との三角関係時代の歌が入っているのだ。つまり「白百合」は登美子にとっての『みだれ髪』(それだけではないが)という一面がある。一冊の歌集を編むうえで、恋愛部門は登美子に任せ、晶子はそれ以外の歌を、心おきなく載せることができたのではないかと思われる。
ただ、この合同歌集について私は、一点だけひっかかることがある。『恋ごろも』の翌年に、早くも『舞姫』『夢之華』と二冊の歌集を出版する晶子にとっては、こういう形の一冊もあっていいな、という感じだっただろう。が、若くして亡くなった登美子には、生前の歌集はこれ一冊である。(雅子は大正六年に『金沙集』という歌集を出版した。)合同歌集に参加できるだけでも、素晴らしいことではあるけれど、自分だけの一冊で、作品を世に問うてみたくはなかっただろうか。
出版事情の違う現代の目から見ての、これは大きなお世話なのかもしれない。それに、繰り返しになるが、この段階で山川登美子として(あるいは、増田雅子として)一冊の歌集を出版しても、おそらくは『恋ごろも』ほどは脚光を浴びなかっただろう。雅子の場合は特に、この一冊が世に認められる契機となったようだ。穏やかで、悪くいえば地味な歌風の雅子。彼女のよさは、登美子と晶子にはさまれて、かえってくっきり見えてくる。
こう考えてくると、『恋ごろも』は合同歌集のメリットを、かなりよく生かしている。
プロデューサーとしての鉄幹の手腕は、やはりたいしたものだ。
では、三人の作品を、それぞれ読んでみよう。歌集に収められた順に、まず山川登美子の「白百合」から。白百合とは、登美子の雅号である。タイトルに自分そのものを表す「白百合」とつけるところに、登美子の並々ならぬ気合が感じられる。これが私のすべてなのだ、とでもいうように。
さきほど、恋愛部門担当のように登美子のことを書いた。しかし次のような激しい歌は、なにか勢いが空回りしているように私には感じられる。
こがね雲ただに二人をこめて捲けなかのへだてを神も許さじ
狂へりや世ぞうらめしきのろはしき髪ときさばき風にむかはむ
ここにあるのは、激しさのための激しさ、だ。晶子に触発され、鉄幹にのせられ、登美子は自分を見失っていたのではないだろうか、とさえ思われる。
もちろん、我を忘れている歌ばかりではない。「白百合」で私が好きなのは、次のような歌たちだ。
うけられぬ人の御文(みふみ)をなけぬれば沈まず浮かず藻にからまりぬ
待つにあらず待たぬにあらぬ夕かげに人の御車(みくるま)ただなつかしむ
一首目の「人」を鉄幹とすると、せつない恋歌になる。許されぬ思いを断ち切るように、愛しい人からの手紙を投げ捨てる。たぶんそこは池なのだろう。手紙は沈むでもなく、浮くでもなく、藻にからまっている。まさに今の自分の、宙ぶらりんの心のように。
二首目は、夫を病でなくした折りの挽歌の中の一首。待っていても人は帰ってこない。
待っていてもしかたがない。それはわかっている。だから「待つにあらず」なのだ。けれど、きれいさっぱり忘れてしまったというのではない。そんなに早く心は整理できるものではない。だから「待たぬにあらぬ」でもあるのだ。そのたゆたう思いが、結句の「ただなつかしむ」へと収斂してゆく。
「沈まず浮かず」「待つにあらず待たぬにあらぬ」「ただなつかしむ」――妙な言い方だけれど、姿勢は消極的ながら、気持ちは積極的な状態だ。案外こういった表情が、登美子の素顔なのではないだろうか。
増田雅子の「みをつくし」は、他の二人に比べると、華やかさは少ないが、しっとりとした品のいい作品が並んでいる。
はかない風景に思いを重ねる、とでも言ったらいいだろうか。次のような作品が私は心に残った。
君待たせてわれおくれこし木下路(こしたぢ)ときのふの蔭の花をながめぬ
心とはそれより細き光なり柳がくれに流れにし蛍
一首目は、恋人との昨日のひとときを、大切にかみしめながら回想している。初々しい感覚の歌だ。約束の時間に作者は遅刻してしまった。初句の字余りが「なんてこと、大好きなあの人を待たせてしまった!」という感じを、よく出している。きっと優しく相手は迎えてくれたのだろう。その後の二人の会話は想像するしかないが、それがとても充実したものであったことが伝わってくる。昨日あんなことがあったこの場所。この場所に咲いている花。おまえは私たちを見ていたの?
他人から見れば、どうということもない空間だろう。が、恋する乙女の瞳には、ありありと二人の幸せな時間が再現されている。
二首目も、繊細な歌だ。柳のかげに隠れてしまった蛍。その消え入りそうな光よりも、さらに細く頼りない光、それが心だと歌う。
内容の繊細さとは対照的に、言葉の並べかたは、とても大胆だ。「心とは」というズバッとした入りかた。つづく「それより」の「それ」の指すものは、この段階では何のことやらわからず、あとで登場する。謎の答えであり、一首のオチでもある「蛍」。これが説得力のないつまらない答えだったら、一首はだいなしだ。最後までひっぱって、びしっと決める。「柳がくれに流れにし」という丁寧な描写が、蛍の説得力をさらに強化した。
まぼろしに得たるみすがたたどる眼にいつしか霧の枯野を得たり
こんな幻想的でしゃれた歌もある。愛しい人の姿を、まぼろしに見た。その姿をたどるうちに、いつしか風景は霧の枯野となっていた……。
風景が花園になったりしないところが、なんとなく辛い恋愛を感じさせる。先の見えない、霧のたちこめる、モノトーンの風景。そこには、恋愛の辛さや頼りなさや不安が映し出されているようだ。作者の心象風景といってもいい。
晶子の「曙染」の特徴は、さきほども述べたように、恋愛をテーマとしないものに秀歌が多いことだ。
海戀し潮(しほ)の遠鳴りかぞへては少女となりし父母(ちゝはゝ)の家
鎌倉や御佛(みほとけ)なれど釋迦牟尼は美男(びなん)におはす夏木立かな
金色(こんじき)のちひさき鳥のかたちして銀杏ちるなり夕日の岡に
「へえっ、この歌も、この歌も『恋ごろも』だったんだ」と、ちょっと驚いてしまう。いずれも、人々に最もよく知られている晶子の作品に、数えられるものばかりである。
それまで恋愛を軸に世界を築いてきた晶子の、これは一つの広がりとして注目していいだろう。右の三首ほど人口に膾炙してはいないが、なかなかユニークでいい歌が、他にもたくさんある。
花に見ませ王(わう)のごとくもただなかに男(を)は女(め)をつつむうるはしき蕊(しべ)
今日(けふ)みちて今日たらひては今日死なむ明日(あす)よ昨日(きのふ)よわれにしらぬ名
君やわれや夕雲を見る磯のひと四つの素足(すあし)に海松(みる)ぶさ寄せぬ
男とは、王のように中心に立つ女を、つつむものなのだ。見てごらんなさい、花というものを。雌蘂をとりかこんで雄蘂が並んでいるでしょう――一首目は、新しい男女観を持つ晶子らしい主張だ。花の姿を見ると、なるほどと思わせられる。
二首目は「死」という語が出てくるが、むしろ、一生懸命生きよう、という歌だ。今日という日を充実して、今日という日に満足して、そういう今日という日に死ぬ。どんな一日も、その日にとっては今日なのだから。昨日とか明日とか考える時間があったら、今日を懸命に走りぬく。生涯を通しての、晶子のパワーというのは大変なものだった。十一人の子どもを育て、十四冊の歌集を出版し、『源氏物語』の訳までなしとげた晶子。そのパワーの源の秘密を見るような歌である。
三首目は、数少ない恋愛の歌だが、『みだれ髪』のころと比べると、なんと穏やかなのだろうと、びっくりする。しみじみとした平和な気分が、よく伝わってくる。自分と相手を、まるで映画の一シーンに登場する人物のようにとらえている視点がおもしろい。風景のなかで二人をとらえていたカメラが「四つの素足に海松ぶさ寄せぬ」でズームアップする。具体物を配したこの下の句は、歌の手ざわりを確かなものにして効果的だ。
最後に、「君死にたまふことなかれ」について。この詩は五つの段階からなっているが、私が日本史の教科書で読んだのは、第一段落と第三段落だけだったことを、後に『恋ごろも』で知った。その間にある第二段落を読むと、ほんとうに晶子が個人的な立場から「君死にたまふことなかれ」と訴えていたことがわかる。それが、はからずも普遍的なものとなったところが、この詩の素晴らしさだろう。が、戦争を憎んだ晶子をいたずらに美化することなく、等身大の彼女を受け止めることも大切だ。普遍性の前に、この個人的感情があったことを忘れてはならないと思う。
堺(さかひ)の街のあきびとの
舊家(きうか)をほこるあるじにて
親の名を繼ぐ君なれば、
君死にたまふことなかれ、……
【この解説が収録されている書籍】
初出メディア

國文學(終刊) 1994年2月号
ALL REVIEWSをフォローする