書評
『一本の樹からはじまった』(アリス館)
風が運ぶもの
これは一つのマチヅクリの話である。『木を植えた男』という名作があるが、土岐小百合著『一本の樹からはじまった』(アリス館)は木を切るのである。
渋谷区広尾といえば東京でも都心の閑静な住宅街だが、ここに大正時代に建てられた古いドイツ風の洋館があった。その庭に亭々と伸びたけやきが一本そびえていた。
バブル期にはどこでもそうだったように、持ち主は相続税で持ちきれなくなる。住み続けるためには、古い家を壊し、木を切ってマンションを建てなければならない。西洋館は運よく家のゆかりの群馬県沼田市に引き取られ移築された。が、木は切られてしまう。その木をたくさんの人と分かちあいたい。この邸(やしき)で生まれ育った土岐さんは思う。
「一本の「けやき」を糸口に、自然、芸術、物語、生活とあらゆる分野へつながっていく人間の輪が広げられるかもしれない」
造形作家で子育て仲間のナボこと下中菜穂さん、写真家の土田ヒロミ氏が協力して一九八九年八月十二日、「一本の樹プロジェクト」は始まる。運営はユニークだ。十万円の「株券」、五万円の「枝券」、一万円の「葉券」、人々の醵金でまかなう。
十月二十二日、移築工事の都合で枝が一部切られる。枝を広げたけやきの最後の姿を見に二百人が集まってきた。「けやき」にささげる舞踏や演奏が行われ、「けやき」に住んだ虫たち、セミの幼虫から羽化へのパフォーマンスもあった。
十月二十三日、「けやき」の下で子どもといっしょにキャンプをした。落葉をたいてサツマイモやリンゴを焼いて食べた。「それにしてもなぜわたしは「けやき」が好きであることを、切られると分かる前に気がつかなかったのだろう」
当たり前の風景は失われるとわかって、初めてその価値が身にしみる。近所の人たちも同じ。秋の落葉を掃くのが大変だ、といっていた人々も、「けやき」の立派な姿、ざわざわという葉音、落ちつく木陰が、どんなに暮らしの中で大切だったかを知る。隣接する小学校の子どもたちは「けやき」を写生する。
十一月二十五日、いよいよ伐採の日だ。木こりの小野寺さんは「どうやって切るかはもう決めたよ。この「けやき」は育ちざかりのときに苦労している」と樹の皮にいとしそうに触れる。
「やがて、見上げるわたしたちの頭の上に、その紅葉がふってきた。真っ青に晴れわたった空をバックに、紅葉は朝日をうけ、光りながら下りてくる。枝からはなれた葉が、くるりくるりと回転しながら、天からやってくる」
地上に降りた大枝は空地を埋めつくす大きさがあった。「けやき」を欲しい人はそれにチョークで名前を書き込む。小学校の子どもたちが手に手に枝を持ち帰った。葉や根で布を染めようという人、皮でカゴを編む人、植木の棚にしようという人、笛にする人……。
そして三年後、乾いた木でさまざまなものがつくられ、「けやき」の展覧会が開かれた。根っこでできた「地球を育てるベンチ」をはじめ、堅いけやきはさまざまによみがえった。
土岐さん、ナボさんの企画力、行動力と自由な発想には敬服する。けやきを「ちがう人と分けあいたい」から生じた、怒ったり、泣いたり、がっかりしたりを乗り越えたつよさにも……。
「力およばずあなたの運命を変えることができませんでした」というナボさんの言葉。その悔やみは、日々、私たちの周りで切られる樹、消える原っぱ、そこでのかけがえのない時間への感覚をするどくする。「一本の樹」の展覧会を見た人が、公団住宅の建て替えで何百本もの樹が切られるとも「木霊(こだま)まつり」をして三本の大樹を残すことに成功した。
こんなふうに風が「けやき」の種を運ぶのである。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
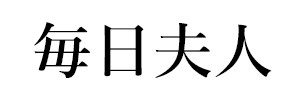
毎日夫人(終刊) 1993~1996年
ALL REVIEWSをフォローする












































