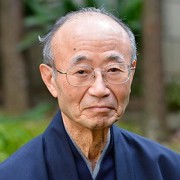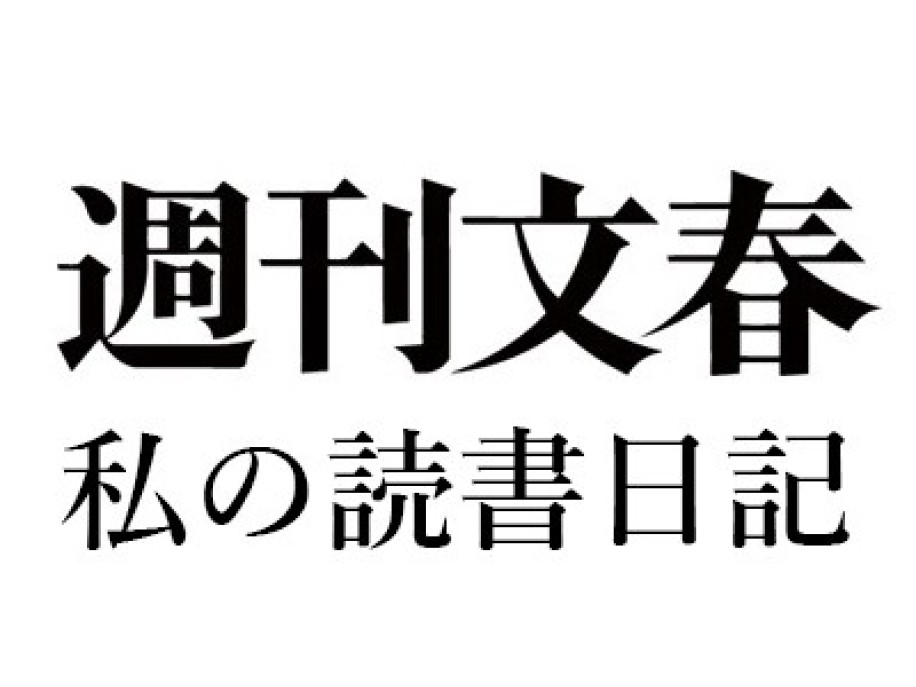書評
『彷徨のまなざし―宮本常一の旅と学問』(明石書店)
本書の主人公、宮本常一は、今日の民俗学の水準からは想像もできないような破天荒の民俗学者であった。終生、日本列島のすみずみを歩き通し、ほとんどの離島を踏査してうむことのない楽天的で、孤高の旅人であった。その徹底した貧乏旅行は一日平均四十キロ、のべ日数にして四千日に及んだという。合して十六万キロの民俗採訪者、ということになるだろう。その宮本常一の旅と学問の内実を、教育学を専攻する著者が傾倒と哀惜のかぎりをつくして照らしだそうとしたのが本書である。
宮本常一は山口県周防大島に生まれ、大阪で郵便局員になった。のち師範をでて小学校の教師となったが、やがて上京、渋沢敬三、柳田国男に見出されて民俗学の世界に入っていった。とりわけ渋沢はその才能を愛して物心両面にわたる援助を惜しみなく与え、かれを「日本一の食客」として親しみ、信頼していたことはよく知られた話だ。
本書はその宮本と渋沢の師弟の関係を軸に、数々のエピソードを重ねてかれの人間的な魅力を浮かびあがらせ、同時に生活の中からにじみでる民俗学の可能性に光をあてて論をすすめている。
それにしても、著者によってつぎつぎにすくいあげられていく宮本の言葉の一つひとつには胸をつかれる。――戦後の子どもたちの不幸は、学校で表彰される子と村でほめられる子が一致しなかったことだ。姑(しゅうとめ)の嫁いびりという問題は、じつは話が逆で、むしろ嫁の方が姑をいびって自殺にまで追いこんだ事例が多かった。農民による雑草とのたたかいが日本人を勤勉にした。村人たちの沈黙がちな生活態度は、仲間への思いやり、悲しみの中の心安らぎ、苦しみの中の希望を可能にする集団生活の中から生まれでたものだ……。
著者は宮本常一を正面から論じつつ、明らかに日本の「教育」の現状に痛烈な批判を浴びせかけているのである。
宮本常一は山口県周防大島に生まれ、大阪で郵便局員になった。のち師範をでて小学校の教師となったが、やがて上京、渋沢敬三、柳田国男に見出されて民俗学の世界に入っていった。とりわけ渋沢はその才能を愛して物心両面にわたる援助を惜しみなく与え、かれを「日本一の食客」として親しみ、信頼していたことはよく知られた話だ。
本書はその宮本と渋沢の師弟の関係を軸に、数々のエピソードを重ねてかれの人間的な魅力を浮かびあがらせ、同時に生活の中からにじみでる民俗学の可能性に光をあてて論をすすめている。
それにしても、著者によってつぎつぎにすくいあげられていく宮本の言葉の一つひとつには胸をつかれる。――戦後の子どもたちの不幸は、学校で表彰される子と村でほめられる子が一致しなかったことだ。姑(しゅうとめ)の嫁いびりという問題は、じつは話が逆で、むしろ嫁の方が姑をいびって自殺にまで追いこんだ事例が多かった。農民による雑草とのたたかいが日本人を勤勉にした。村人たちの沈黙がちな生活態度は、仲間への思いやり、悲しみの中の心安らぎ、苦しみの中の希望を可能にする集団生活の中から生まれでたものだ……。
著者は宮本常一を正面から論じつつ、明らかに日本の「教育」の現状に痛烈な批判を浴びせかけているのである。
ALL REVIEWSをフォローする