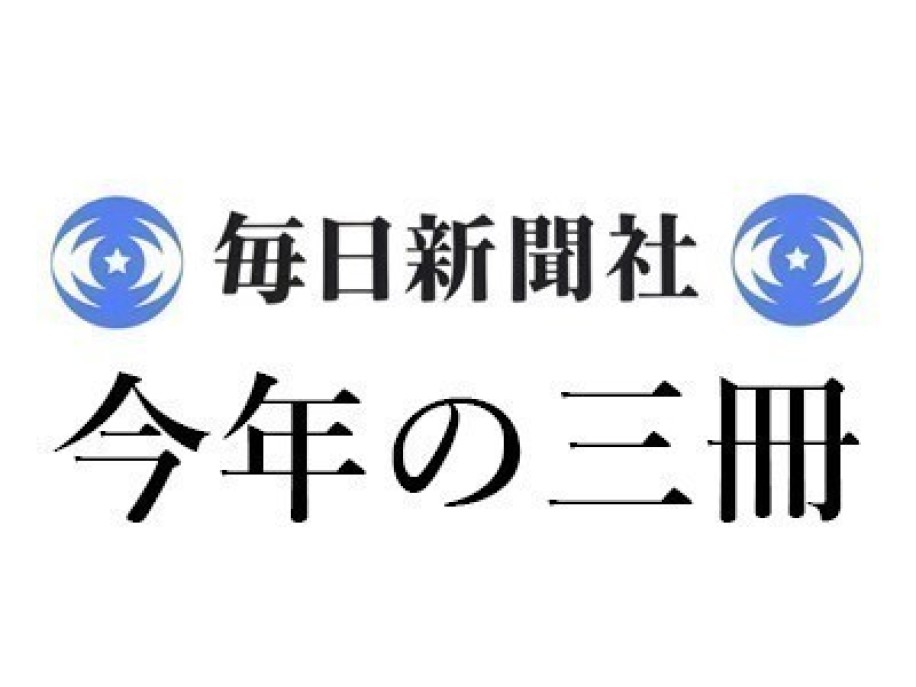書評
『選書日本中世史 4 僧侶と海商たちの東シナ海』(講談社)
豊かに跡づける「遣唐使後」のうねり
東シナ海をめぐる交流の歴史は、古くは太古にまでさかのぼるのだが、はっきり文献で見えてくるのは、古代の遣唐使の派遣の頃(ころ)からであり、それ以後、実に多様な形で推移してきた。しかし教科書では、遣唐使の廃止後についてはあまり語られることがない。大陸に渡った僧の話が少し出てくるだけで、「国風文化」ということで日本の歴史の流れが内的動きへと向いたとされ、対外交流は付随的に扱われてきた。ただその後の平氏による日宋貿易やモンゴルの襲来などを見ても、日本の歴史の展開において対外交流の歴史は大きな意味をもつことはいうまでもない。
そうしたところから室町時代の対外交流については、日明貿易・日朝貿易のあり方など、最近になって研究が大きく前進してきている。ところがそれ以前になると、さっぱり研究が進まなかった。戦前や戦後すぐの研究のままに停滞していたと言っても過言ではない。その大きな原因は、史料が絶対的に少なく、手がかりが乏しいことにある。
しかし著者は、史料が少ないのではなく、扱い方がよくわからなかっただけである、その気になりさえすれば、史料は極めて豊富にあるとして、史料を博捜し丹念に分析し、ここに九世紀から一四世紀にかけての東シナ海を舞台とした僧侶と海の商人たちの活躍を豊かに描いている。
多くの僧侶たちは信仰を求めて大陸に渡った。それは中華の国家と日本の朝廷や幕府の外交政策の変化により、あるときは多くの援助をあたえられ、またあるときは援助がないなかを密航する形で渡っていった。著者はその苦難の旅を淡々と、しかし的確に再現し、入唐僧たちをめぐる政治情勢や宗教事情などをふまえて叙述してゆく。
今のように大陸に渡ってもすぐに帰ることができる時代ではない。次の船便は早くて二十年、それに失敗すれば、さらに二十年ということもあったし、また政治情勢の変化によって法難がおきると、スパイとして軟禁されることもあった。この点は、今も変わらないような部分もあるわけなのであるが。
そうした僧の渡航を助けたのが、海を舞台にして活躍した海商たちである。使節派遣を利用した時代から、海商を利用した時代への転換期にあたる九世紀から、話は始まる。最後の遣唐使船に乗った天台僧の円仁(えんにん)は、帰国にあたって新羅(しらぎ)人海商の船を利用している。九世紀になって新羅で国内に混乱が起きると、新羅人はその活躍の場を南の唐に求め、日本にも求めていったのだが、そのうち唐にいった人々が海を活躍の場とする海商として成長してきたのである。
ここに海商の時代が始まった。新羅の内紛からやがて新羅の海商の姿が消えると、その跡を継承しつつ、さらに新たな航路を開拓して登場してきたのが唐の海商であった。彼らは活発な交易活動を展開し、太宰府の鴻臚館(こうろかん)に滞在して政府が先買権を行使する鴻臚館貿易を行なうようにもなっていった。彼らのもたらした情報をもとに、僧侶たちは経典を求め、また信仰の疑義への解答を求め、さらには留学僧としての名誉を獲得しようとして、危険がいっぱいの海を渡ったのである。
しかし対外関係は国々の状況で左右される。渡航が許可されなくなる事態が生まれるなか、十一世紀になると密航する僧たちが現れる。六十歳になった成尋(じょうじん)は渡航の許可がおりないまま密航することになったのである。ここに管理外交・貿易の衰退がはっきり認められるようになり、それとともに海商たちも交易を行なった後はすぐに帰国させられていたのだが、あまり問題にされなくなり、博多に住みつくようになった。
ではそれで密航僧が増えたかというと、そうではなく逆に減っていった。朝廷の援助がなくなると、多額の費用がかかる渡航に挑む僧侶が減っていったのであろう。再び渡航が盛んになるのは、平氏が行なった宋との交渉からで、その援助で宋に渡った栄西や重源の動きが再び渡海熱に火をつけるようになった。新たな宗教の動きに触れようとして、鎌倉中期からは大陸に僧たちが殺到する状況となった。
著者はこの動きを二人の禅僧、京都の東福寺の開山となった円爾(えんに)と、四十六年間も元に滞在した龍山徳見(りゅうざんとくけん)の動きから見ている。特に龍山が遭遇した事態を明らかにした部分には創見が多い。伝記のみならず、墨蹟(ぼくせき)や詩文などの史料を巧みに使って新知見を提出しており、その論旨には説得力がある。
龍山が帰国する頃から、大きな変化が起きていた。倭寇(わこう)の活動や日明貿易の開始とともに、明が海禁政策をとった影響から、海商の活動の場は狭まり、大陸に渡った僧の動きも制限され、かくして「僧侶と海商たちの東シナ海」は終焉(しゅうえん)をつげることになったという。
本書は「選書日本中世史」と銘打ったシリーズの第四冊であるが、東シナ海の海域の歴史が日本列島の中世史といかに連動していたのかを見事に描いており、今に繋(つな)がる問題も提出され、実に読み応えがあった。
ALL REVIEWSをフォローする