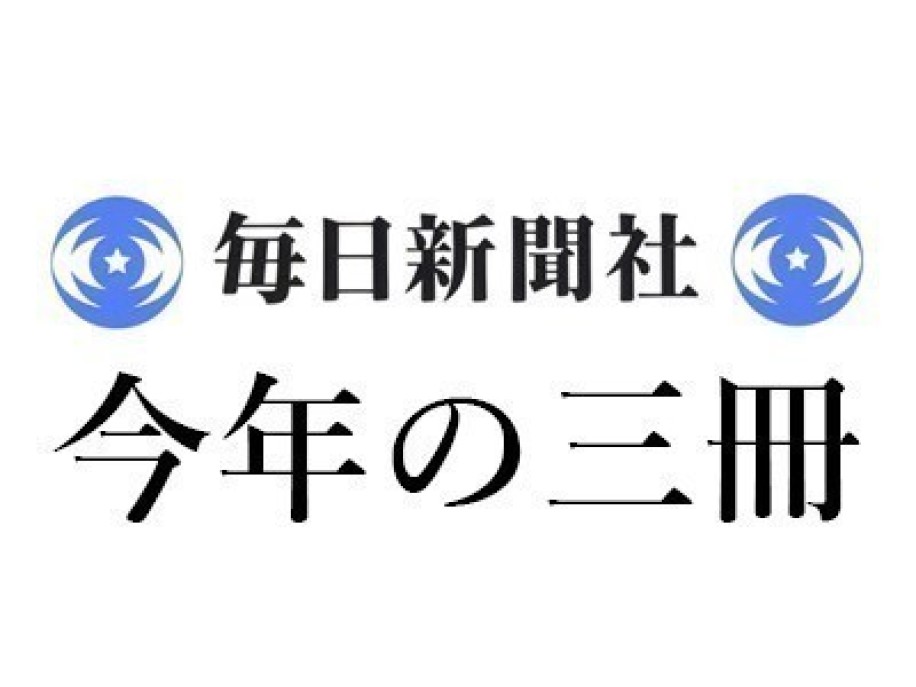書評
『家事の政治学』(岩波書店)
協同と共同
私は仕事を持っており、子どもは三人いるし、悩みの種は家事である。掃除はしなくてもホコリでは死なない。洗濯はまあ、清潔の許容度を少し引きさげればよい。だけど食事づくりは後ろめたくてなかなか手抜きができない。かといって子どもに家事を仕込むには暇がない。柏木博『家事の政治学』(青土社)は、洗って使ってまた洗う洗濯、作って食べて皿を洗う炊事、こうしたシジフォスの神話のように退屈で、反復的な家事から、どう人類を、いや正確にいうと女性を解放するかの歴史を、博引旁証であとづけている。
すでに十九世紀の半ば、炊事や洗濯を公共のものとする言説が現われた。すなわち「キッチンのない住宅」である。私たちも考えた。仕事仲間の女性三人で十人の子どもがいる。三人の主婦が別々の食事をつくるより共同キッチンをもつ集合住宅を建設しようと。一人が十数人分の食事をつくり、一人が子どもと遊び、もう一人が読書でも映画に行くでもした方がラクで楽しいのではないか。
「協同家事は、孤独な空間でおこなわれていた女だけに押しつけられた過重な家事を公的空間での労働にする」と著者はいう。しかし、私たちの挫折もまた「妻の労働力を他人のために使われるのは耐えられないという夫たちの感情にあった」。食事くらいは家族水いらずで食べたい、と夫たちはいう。戦後の日本の目標となった「一戸建て住宅」は主婦を各戸別の家事に従事させるという意味で、たしかに政治的イデオロギーだったという。
同じく十九世紀の後半、「アンクル・トム」の著者ストウ夫人らは簡素で家事の動線の短い家を提案した。それは中産階級が黒人の召使いを使わずにすむ住宅だった。
同じころ、貧乏な市民に栄養ある「均質的料理」を与えるための共同キッチンもロンドンやニューヨークで実現された。一九三〇年代には家事の徹底的なエンジニアリングがすすめられ、それはファースト・フードという商品化の方法論へ取り込まれていった。
ハンバーガーやフライドチキンの日本への上陸は戦後である。家にいる女たちも、家事よりも、“自分のために生きる”ことに時間を使うようになった。そういえばデパートが主催するカルチャーセンター帰りに、夫のために地下の食品売場でトンカツや寿司弁当を買う主婦をみかける。
でも家事とは複雑な効用があり、私など気分転換や究極の癒しとして、あるいは創造の喜びのために家事を行うこともあるのだが、本書はそういう側面にはあまりふれていない。
とはいえ私が日々恨んでいる家事一つをめぐり、かくも様々の言説、工夫、提案があったのか、と驚かされた。家事の省力化はバックミンスター・フラーやバウハウスの建築家、デザイナーによっても提案されたが、「家事労働の問題を自ら考えようとする女性たちの運動にはつながらなかった」と著者はいう。
しかし家事労働の一切を住まいの外側に押し出してしまうとき、家事の商品化が促進される。子育てをベビーシッターに、庭の手入れは園丁に、掃除を掃除会社に、食事を店屋物に、と「社会化」するとき、私たちはお金を払わねばならない。もし家事や消費を小さく止めようとすれば生活はかぎりなくミニマムになると著者はいう。そこで私は新宿地下街のホームレスの人々を思い出す。私はひそかに憧れている。家事もほとんどせず、消費にも身をゆだねない、あの生き方を。
いや神戸の大地震のようなことが起こればだれしも「ホームレス」になる可能性がある(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1995年頃)。生き残った人々は、残された設備を共同で使い生きてゆくしかない。神戸では皮肉にも協同(コーポレーション)と共同(アソシエーション)という十九世紀の夢が実現した。お金で解決できないとき、人は無償で助けあう。それは近代が豊かさと共に排除したユートピアの皮肉な実現なのかもしれない。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする