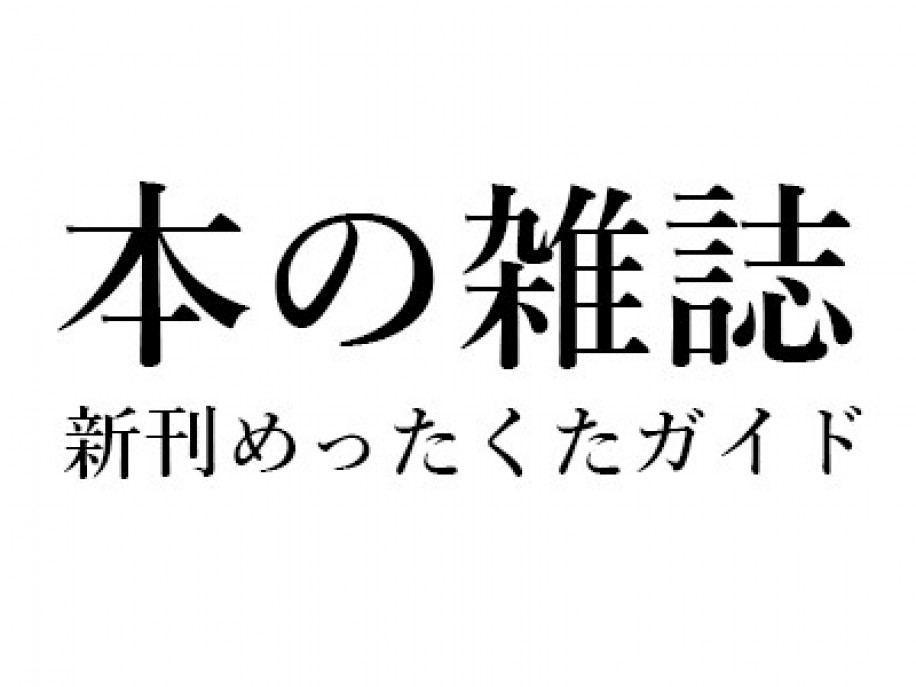書評
『中国禅宗史』(筑摩書房)
世界的なポテンシャルを読み解く
中国で独自の発達を遂げ、仏教なのかさえ疑問な禅宗。その真の姿を、語録を通して探り出す。禅宗は、初期→唐代の禅→宋代の禅、と変遷した。日本に伝わったのは宋代の臨済/曹洞宗。以来各宗は、語録を漢籍として訓読してきた。でも語録は唐宋の口語。素直に中国語として読むべきだ。敦煌(とんこう)から初期禅宗の文書も出土した。これらを踏まえ、当時の思想や社会にも目配りし、宗門の常識の届かない禅の原点に迫ろう。
インドの達磨が中国に来て、禅の行法を伝えた。達磨→恵可→僧璨(そうさん)→道信→弘忍→恵能へと、「伝灯」が継承されたという。語録は禅宗独特の、師弟の問答録だ。禅問答は意味不明なのだろうか。
初期の禅は過激だった。「仏に逢(お)うては仏を殺」せ。修行して仏になろうみたいな雑念を捨てろ。近代の思想家胡適(こてき)によると「偶像破壊」そのもの。「修行して覚って仏になる」という小乗大乗の根本原則を認めない。後に開祖とされる初期の習禅者たちは、≪中国の北地に散在しながら、書翰(しょかん)や口頭で道を論じあっ≫た。その方法論が『二入四行(ににゅうしぎょう)論』である。理入(頭で考え)し行入(正しく行動)して、苦そのものである己れの存在を忘れようとする。
唐代に禅宗の原型ができた。有力な禅僧らが正統を争い、恵能の「南宗」と神秀の「北宗」が並立した。神会(じんね)は頓悟(とんご)を唱えた。≪自らの本性を自らが見る≫のに時間はかからない。坐禅も必要ない。日常の現実が大事である。安史の乱を境に、牛頭(ごず)宗、荷沢(かたく)宗など禅の七宗が各地に成立。従来の戒律を廃止する流れも広まった。
問答はそもそもどんなものだったか。唐代禅を代表する馬祖(ばそ)は言う、≪自らの心是(こ)れ仏、此(こ)の心即(すなわ)ち仏なり≫。弟子が言う、即心是仏の意味がわかりません。馬祖、うるさいな、出直せ。帰ろうとすると呼びとめる、おい。思わず振り向くと言う、「何だ」。弟子はハッと覚って礼をした。
馬祖の弟子如会(にょえ)は、即心是仏ひとつ覚えの僧が多くて頭に来た。そこで言う、≪心は仏ではない、…即心即仏は…見当ちがい≫だ。
行脚僧が禅僧雲門に面会した。どこから来た? 湖南です。馬鹿者、棒で打つぞ。翌日また聞く、昨日は何が悪かったのですか? このムダ飯食いが、行脚なんかしおって! 行脚僧は大悟した。
誰が誰にどう言ったか。これを記録する。仏より経典より、言葉で闘う語録のほうが大切なのだ。
宋代になると禅宗は、問答の意味を詳しく分析する「文字(もんじ)禅」、問答を意味不明なまま丸のみにする「看話(かんな)禅」になった。臨済宗は看話禅にもとづく。初期とは正反対の、権威主義に堕落した。
禅宗は「清規(しんぎ)」に従う。釈尊の定めた戒律に代わる、集団生活の規則だ。労働(農作業)に価値を置く点が、通常の仏教と異なる。初期は仏殿も仏像もなく、法堂で師と問答するだけだった。宋代には建物も立派な官僚組織になり、それが日本に伝わった。
思想も組織も窮屈な宗門の枠を離れ、禅の真実に迫る科学的研究は可能か。入矢義高が京都で研究会を始めた。語録を中国語の字義通りに読み解こう。著者小川氏はその教えを受け、師の志を継いでいる。鈴木大拙は言った、禅のポテンシャルは世界的だ。本書はその可能性が詰まった宝物だ。
ALL REVIEWSをフォローする