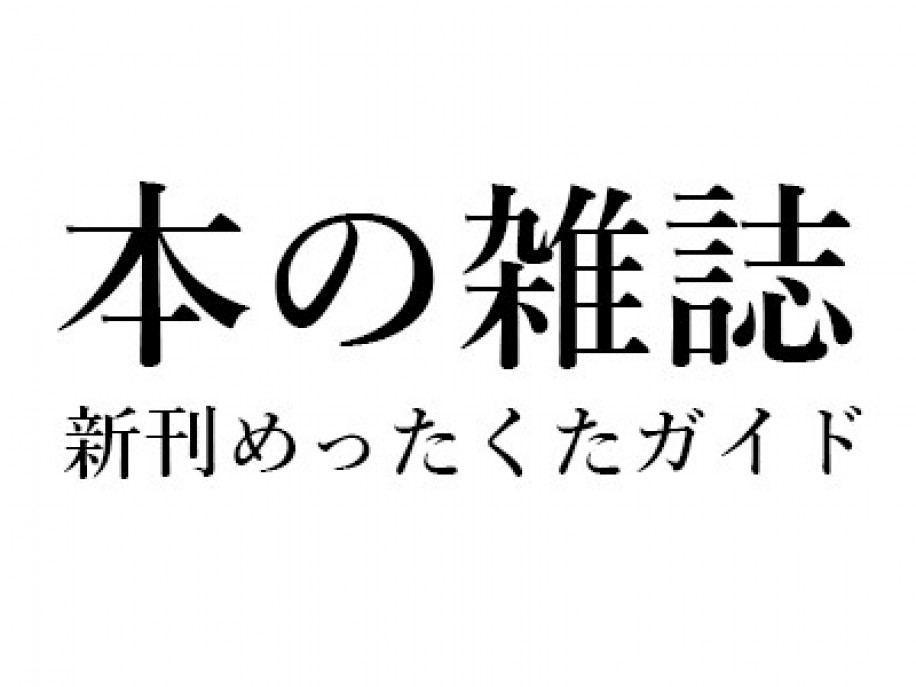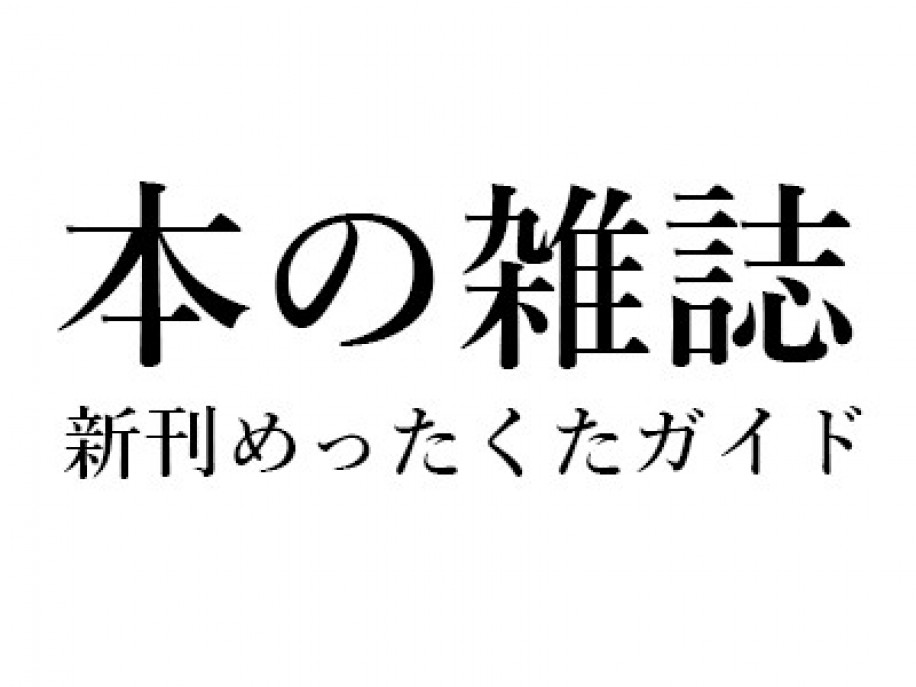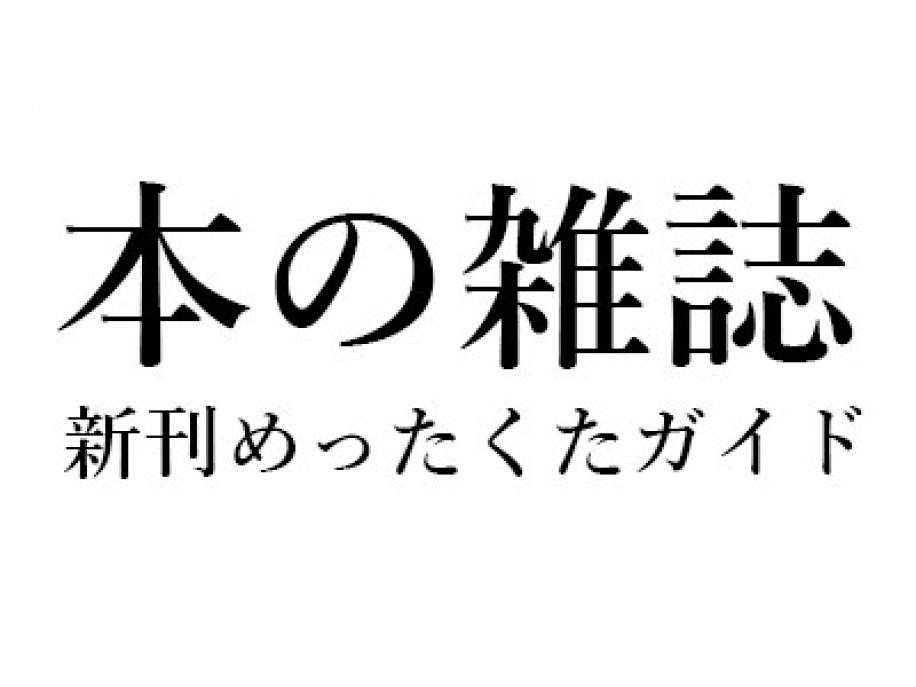書評
『この不思議な地球で―世紀末SF傑作選』(紀伊國屋書店)
桜とSF
ぼくの住んでいるマンションは石神井池に面していて、玄関を出ると桜並木がある(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1995年頃)。ここ数日、ぼくは本を一冊持って出かけ、池の横の小さな野外音楽ホールの椅子に座って一時間ぐらい読み、それから帰って寝る。朝五時半から六時半にかけてだから、さすがに(花見の)観光客の姿はない。早朝ジョギングの人たち、それから早朝集団(?)散歩の老人たちが、座って本を読んでいるぼくのことなど気にせず、桜の下を走ってゆく。桜は、あと一日か二日で散り始めるだろう。本から目を上げると満開の桜が見える。これは、やはり異常な風景だな、とぼくは思った。
異様な風景を前にしたり、尋常ではない状況で、本を読む。そうすると、どうでもいいような内容の本がものすごくいいものであるように感じられる時もあれば、その逆に、すごくいいものであるはずなのに、なんかもう全然どーしよーもないような気になっちゃう時もある。ぼくの中学時代の親友は、女の子(「チエちゃん」っていったっけ)との別れ話がもつれ、逆上した彼女が包丁を持っている前で、ヤケクソになってルソーの『エミール』を読んでいたら、世界の秘密がわかったような気がしたといっていた。でも、その秘密が何だったのか、次の日には忘れていたようだ。しかし、そんな事態に追いこまれたら、どんな本でも色褪せて見えるんじゃないかな、ふつう。
これはもう時効だから書いてもいいと思うけれど、遥か昔、我が友Aは秘密のアジトで手製の爆弾を作り、それからしばらくそいつと寝起きしていたが、その間、なにを読んでも、文字が抽象的な記号に見えてこの世界のことが書かれているとは思えなかったといっていた。ぼくは同情しつつも、
「世界が一変して見えたらよかったのにね。それは、きみ、なにかが間違っていたんだよ」といった。
「そうだよな。おれもそう思う」とAは答えた。Aはいま長野県でペンションをやっている。先週、「百武彗星を見た」というハガキをもらったばかりだ。
ぼくが外に持ち出したのは巽孝之さんが編纂した『この不思議な地球でー世紀末SF傑作選』(紀伊國屋書店)という新しいSFのアンソロジーだ。SFファンでもあるぼくでも、SFが「ニューウェイヴ」という難解路線に行っちまった時は、さすがに読めなかったが、いまの「流行り」 に抵抗はない。いや、結構いい線をいってるんじゃないかと思うことも多い。満開の桜の下では、純文学(のほとんど)なんか読めたものじゃないが、このSFたちはぴたりと合うのが、なんだか不思議。「世紀末SF」だからなんだろうか。無政府自治区となり、独立した文化空間となったサンフランシスコ・ベイ・ブリッジを描いたウィリアム・ギブスンの「スキナーの部屋」、児童失踪ホラー小説、オースン・スコット・カードの「消えた少年たち」、地球に戻ったまま宇宙船から出てこない宇宙飛行士たちの物語、J・G・バラードの「火星からのメッセージ」あたりは誰が読んでも感心するだろうが、ぼくがいちばん好きなのは、性的玩具となった遺伝子奴隷を描いたエリザベス・ハンドの「アチュルの月に」。せつない愛の物語に、思わず涙腺が緩んじまった。ここまで仕掛けを作らないと、「恋愛小説」は書けないのか。
そんなことを考えつつ、目を上げると、一枚、二枚と桜が散り始めるのが見えた。そうか。満開の桜が異様に見えるのは、それがとても自然のものには見えないからなのだ!
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする