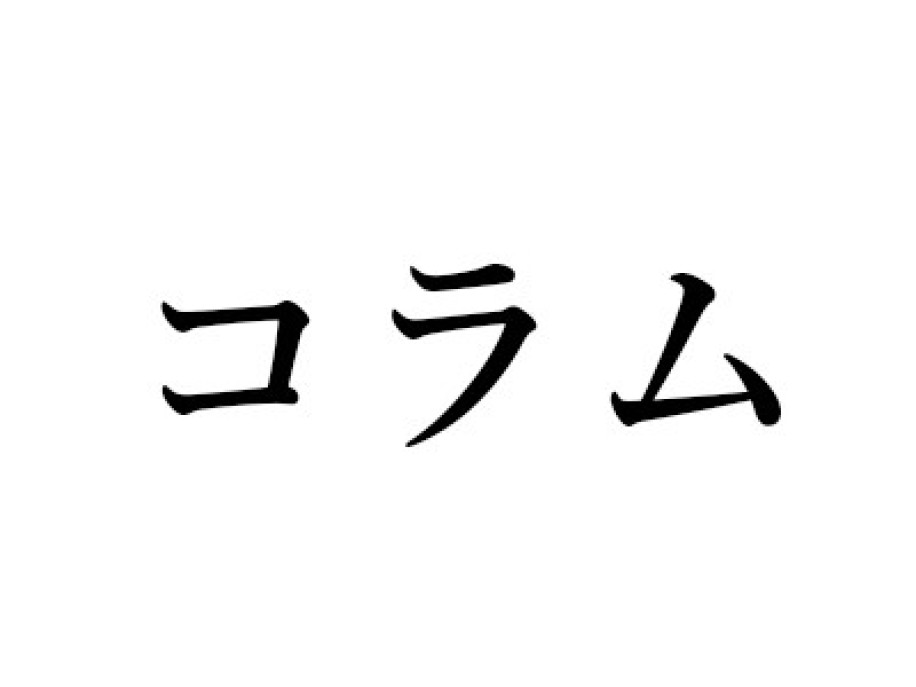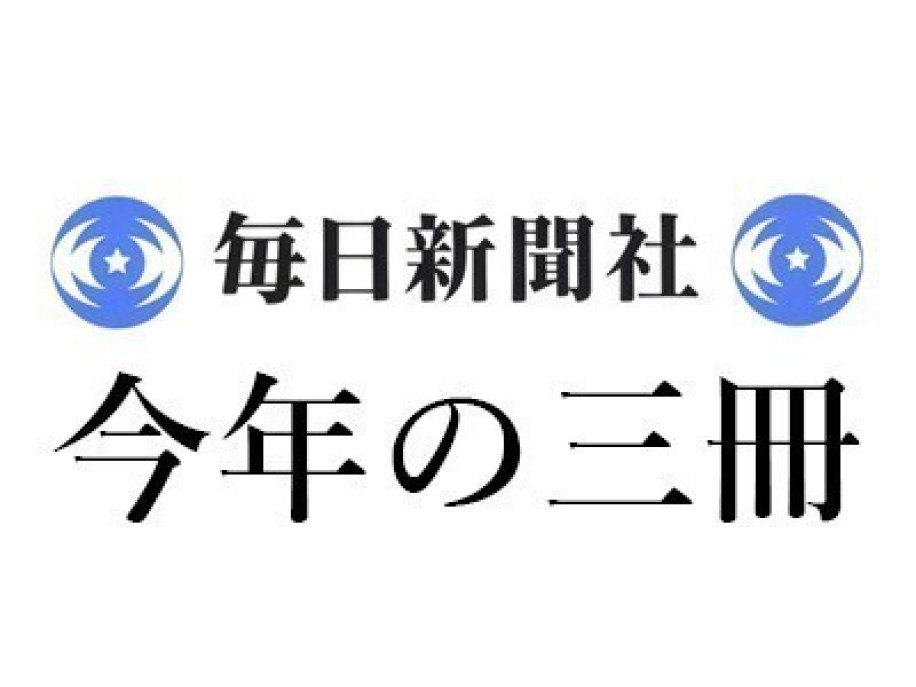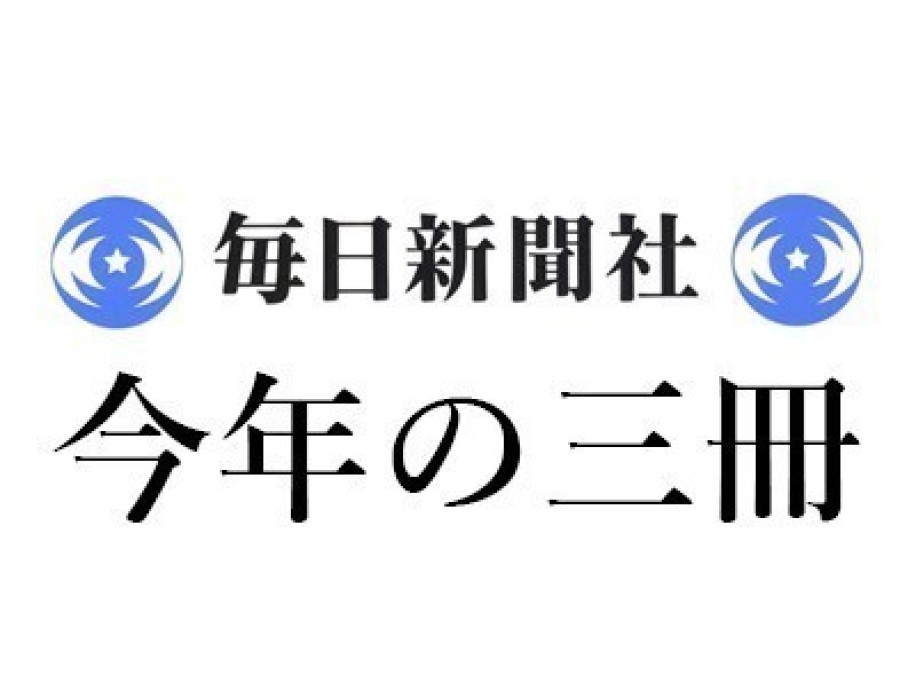書評
『彼方なる歌に耳を澄ませよ』(新潮社)
スコットランド高地からの移民が多く住むカナダ東端の島ケープ・ブレトンで育った、一九三六年生まれの作家アリステア・マクラウドの小説を読むと、心の森の奥深いところにあって普段はまるで意識もしない小さな窪地のような場所が自分を呼んでいる気がして、やましさを覚える。前ばかりを見つめて、進歩に努めて、来し方を振り返るのを潔しとせず、自分だけの力でこの世に生まれ育ってきたかのようにふるまう――そんな人間にとって、マクラウドの小説はある種の痛みを伴わずに読み切ることが不可能なのだ。
勇猛果敢で誇り高いことで知られるハイランダー(スコットランド高地人)一族の赤毛の男キャラム・ルーア。彼は十八世紀末、スコットランドからケープ・ブレトン島に家族と共に渡る。『灰色の輝ける贈り物』『冬の犬』という二冊の短編集で日本の読者にもよく知られるようになったマクラウド唯一の長編である本作は、そんな男の子孫「クロウン・キャラム・ルーア(赤毛のキャラムの子供たち)」の、幾世代を経ようとも決して自分たちの身体に流れるその血を忘れない生き方を描いて静かな、しかしとても力強い感動をもたらす傑作なのである。
ここには、二卵性の双子が生まれやすい、赤い毛や黒い毛を持つクロウン・キャラム・ルーアの人々がいる。飼い主であるキャラム・ルーア一家が新天地を求めて乗った小舟を追いかけて、どこまでも泳ぎ続ける犬がいる。その子孫の、情が深すぎて頑張りすぎる茶色い犬たちがいる。身内の面倒をちゃんとみるべきだと信じている人たちがいる。野生の馬と心通わせる男がいる。男のゆるぎない信頼に精一杯応えようと頑張る雌の馬がいる。「別々の包みに入ってはいるが、同じ悲しみ」を共有する人々がいる。息子を助ける父親たちと、父親を助ける息子たちがいる。誰かが助けてくれたから生きてこられたことを知る者がいる。「誰でも愛されるとよりよい人間になる」と孫に説く老人がいる。父祖の物語を語り伝えていく一族がいる。見事な声でゲール語の古い歌を奏でる男がいる。歌声を重ねていく大勢の人々がいる。
かつて一族の者から「ギラ・ベク・ルーア(小さな赤毛の男の子)」と呼ばれ、貧しい境遇にあって苦学をし、今では成功した歯科医になっている「私」を語り手においたこの小説は、今というこの瞬間が、目眩(めまい)を起こしそうになるほど遠い昔から、無数の“今”を踏んでやってきたのだということ、わたしという命が幾世代もの感情豊かな交歓を経て生まれ得たのだということを、たくさんの悲喜こもごものエピソードによって読者に伝える。それは、「昔はよかった」式の老人作家の懐古趣味などではもちろんない。「私」とその双子の妹は成功して、荒れやすい天候や貧しさに苦しんだ島での生活とは正反対の、穏やかで豊かな日常を送っている。しかし、若い頃から炭坑で働いてきた、年のうんと離れた長兄キャラムは、街の生活にはなじめず、酒浸りの生活を送っており、時々様子を見にくる「私」相手に父祖の逸話や島での思い出を語りかけるのが心のよすがとなっている。「私」にはそれがつらい。長兄を訪ねるのは気が重いと思っている自分がやましい。
自らを「つくづく自分は二十世紀の人間なんだと思う」と規定する「私」は、おそらく人生のある時――歯科医として働き出した頃か、それとも結婚した時なのか?――からクロウン・キャラム・ルーアの血を意識的に忘れようとしてきたのではないだろうか。前へ前へ、後ろを振り切り未来だけを見つめて歩き出した瞬間があるのではないだろうか。その「私」のやましさを根底に横たわらせたからこそ、この作品は単なる懐古趣味を超え、どの時代や民族、家族、そしてあまたの個人にも訴えかけるだけの普遍性を獲得しているのだと思う。
人間は、とくに先進国と呼ばれる地域に住む人間は、未来ばかりを見すえ、暮らし向きを向上させ、簡便さを追求しようとするあまり多くのものを失い、しかし、さらに前に進むためにそのことから目をそむけてきた。「そんなことは誰にだってわかってるよ」、大上段から言われるとシニカルにかわしたくなる当たり前のことが、マクラウドの小説を読むとどうだろう、胸にしみいるのだ。心が痛むのだ。立ち止まって、こわごわ後ろを振り向こうとする自分がいるのだ。彼方なる歌に耳を澄ませたくなる自分に驚くのだ。それが、物語の力というものではないだろうか。
【この書評が収録されている書籍】
勇猛果敢で誇り高いことで知られるハイランダー(スコットランド高地人)一族の赤毛の男キャラム・ルーア。彼は十八世紀末、スコットランドからケープ・ブレトン島に家族と共に渡る。『灰色の輝ける贈り物』『冬の犬』という二冊の短編集で日本の読者にもよく知られるようになったマクラウド唯一の長編である本作は、そんな男の子孫「クロウン・キャラム・ルーア(赤毛のキャラムの子供たち)」の、幾世代を経ようとも決して自分たちの身体に流れるその血を忘れない生き方を描いて静かな、しかしとても力強い感動をもたらす傑作なのである。
ここには、二卵性の双子が生まれやすい、赤い毛や黒い毛を持つクロウン・キャラム・ルーアの人々がいる。飼い主であるキャラム・ルーア一家が新天地を求めて乗った小舟を追いかけて、どこまでも泳ぎ続ける犬がいる。その子孫の、情が深すぎて頑張りすぎる茶色い犬たちがいる。身内の面倒をちゃんとみるべきだと信じている人たちがいる。野生の馬と心通わせる男がいる。男のゆるぎない信頼に精一杯応えようと頑張る雌の馬がいる。「別々の包みに入ってはいるが、同じ悲しみ」を共有する人々がいる。息子を助ける父親たちと、父親を助ける息子たちがいる。誰かが助けてくれたから生きてこられたことを知る者がいる。「誰でも愛されるとよりよい人間になる」と孫に説く老人がいる。父祖の物語を語り伝えていく一族がいる。見事な声でゲール語の古い歌を奏でる男がいる。歌声を重ねていく大勢の人々がいる。
かつて一族の者から「ギラ・ベク・ルーア(小さな赤毛の男の子)」と呼ばれ、貧しい境遇にあって苦学をし、今では成功した歯科医になっている「私」を語り手においたこの小説は、今というこの瞬間が、目眩(めまい)を起こしそうになるほど遠い昔から、無数の“今”を踏んでやってきたのだということ、わたしという命が幾世代もの感情豊かな交歓を経て生まれ得たのだということを、たくさんの悲喜こもごものエピソードによって読者に伝える。それは、「昔はよかった」式の老人作家の懐古趣味などではもちろんない。「私」とその双子の妹は成功して、荒れやすい天候や貧しさに苦しんだ島での生活とは正反対の、穏やかで豊かな日常を送っている。しかし、若い頃から炭坑で働いてきた、年のうんと離れた長兄キャラムは、街の生活にはなじめず、酒浸りの生活を送っており、時々様子を見にくる「私」相手に父祖の逸話や島での思い出を語りかけるのが心のよすがとなっている。「私」にはそれがつらい。長兄を訪ねるのは気が重いと思っている自分がやましい。
自らを「つくづく自分は二十世紀の人間なんだと思う」と規定する「私」は、おそらく人生のある時――歯科医として働き出した頃か、それとも結婚した時なのか?――からクロウン・キャラム・ルーアの血を意識的に忘れようとしてきたのではないだろうか。前へ前へ、後ろを振り切り未来だけを見つめて歩き出した瞬間があるのではないだろうか。その「私」のやましさを根底に横たわらせたからこそ、この作品は単なる懐古趣味を超え、どの時代や民族、家族、そしてあまたの個人にも訴えかけるだけの普遍性を獲得しているのだと思う。
人間は、とくに先進国と呼ばれる地域に住む人間は、未来ばかりを見すえ、暮らし向きを向上させ、簡便さを追求しようとするあまり多くのものを失い、しかし、さらに前に進むためにそのことから目をそむけてきた。「そんなことは誰にだってわかってるよ」、大上段から言われるとシニカルにかわしたくなる当たり前のことが、マクラウドの小説を読むとどうだろう、胸にしみいるのだ。心が痛むのだ。立ち止まって、こわごわ後ろを振り向こうとする自分がいるのだ。彼方なる歌に耳を澄ませたくなる自分に驚くのだ。それが、物語の力というものではないだろうか。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする