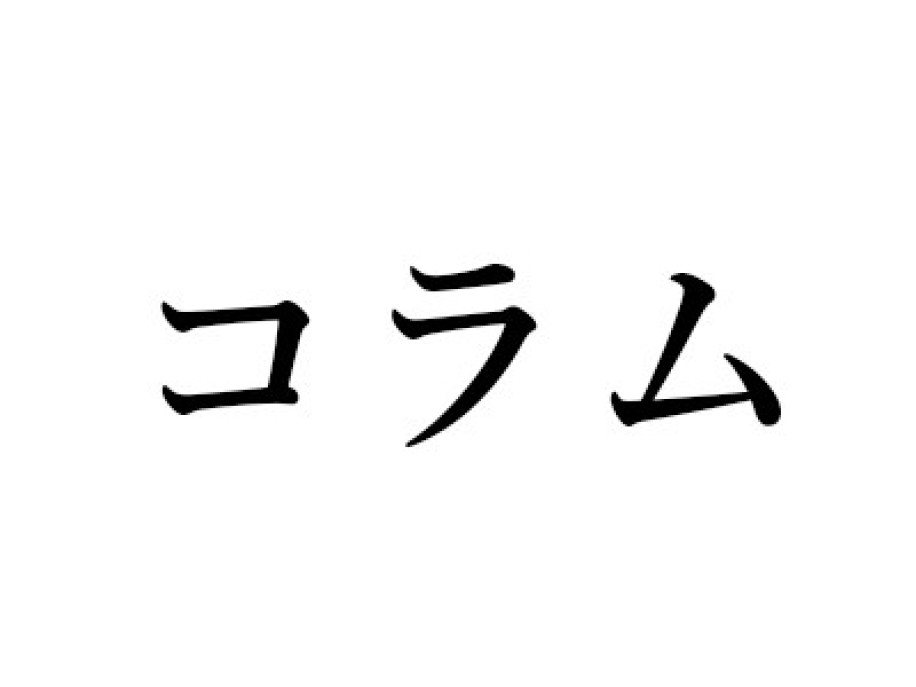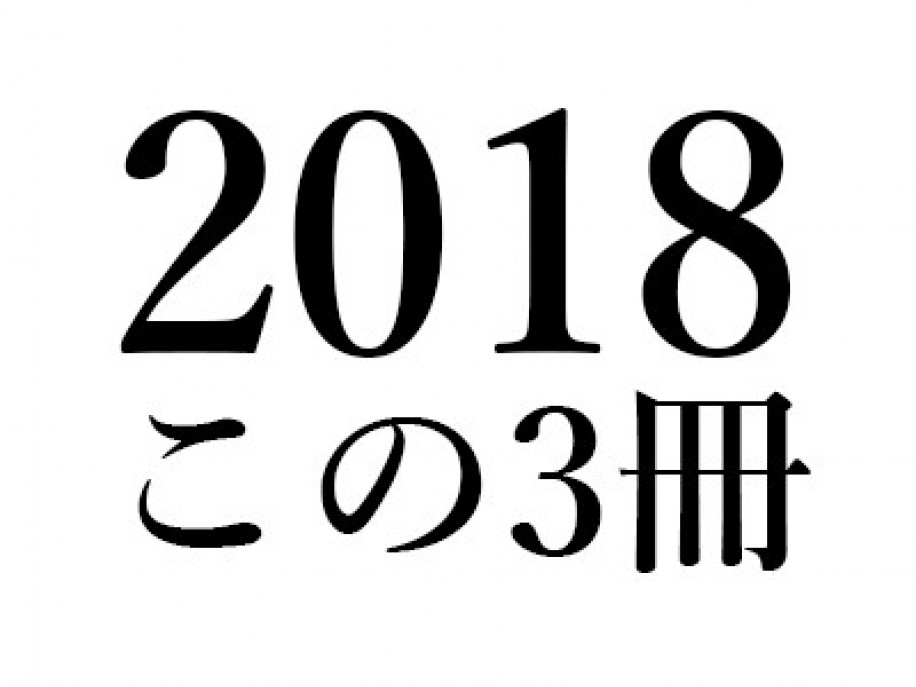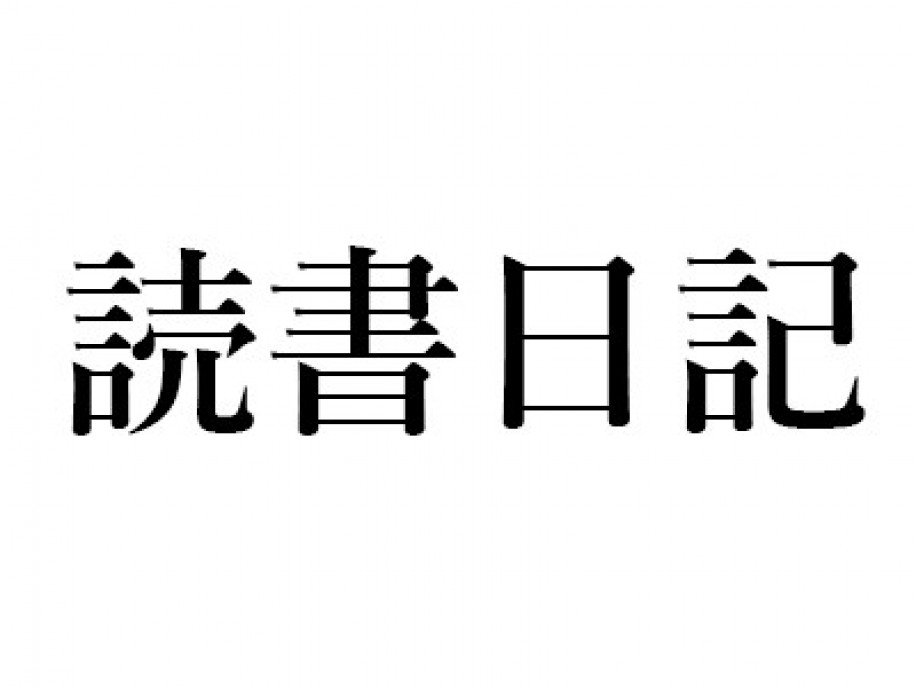書評
『愉快な本と立派な本 毎日新聞「今週の本棚」20年名作選(1992~1997)』(毎日新聞社)
読み手に届く小さな矢の秘密
書評家を根絶せよ。書評は役に立たないから――と、批評精神と辛辣(しんらつ)なユーモアに溢(あふ)れたエッセイを書いたのは、自らも書評を手がけた小説家のヴァージニア・ウルフ。一九三九年のことだ。また、ディケンズにとって、書評家は小さな矢を携えた悪魔みたいな存在だったという。二十世紀前葉のイギリス書評のなにがいけなかったのか。伝統ある有力紙について纏(まと)めた『タイムズの歴史』なる書物によれば、一つは、十九世紀中葉に比べて「書評が短くなった」、二つめに、「出版から間をおかず出るようになった」、三つめに、「数が桁違いに増えた」とのこと。分量・内容ともに日本と比べてずっと分厚いと言われるイギリスの書評ですら、前世紀前半には「短・速・多」が問題視されるようになっていたわけである。
さて、ウルフの随筆から七十三年後の日本には、書評家はさておき書評じたいは(どっこい)生きている。そして、今から二十年前、新聞書評におけるこの「短・速・多」問題に立ち向かったのが、丸谷才一を編集顧問としてスタートした「今週の本棚」だった、ということだ。本書『愉快な本と立派な本』は、その独自の方針で組まれる読書面から最初の六年間の書評を精選し、編集したものである。
実をいうと、わたしはそれ以前の時代をよく憶(おぼ)えていないのだが、少なくとも現在、新聞雑誌の書評は通常が約八百字(原稿用紙二枚)。毎日新聞のこの欄だと通常が千四百字(三枚半)で、大きい枠は二千字(五枚)。一本の字数が多いため、書評本数は絞られる。刊行から時間が経(た)った本も、文庫化された本も、取りあげるべき時に取りあげる方針だと聞いている。新刊ガイドに留(とど)まらない評論のスコープをもちえている所以(ゆえん)は、こうした点にあるのだろう。
本書の書評ラインアップは圧巻の一言だ。のちには、シュリンクの『朗読者』のような良書をいち早く評したケースもあるが、他にも、後々その作家の里程標的な作品となったものや、ある分野でのクラシックになった本も多い。どの評者が書いたかにもご注目いただきたい。
本川達雄『ゾウの時間 ネズミの時間』(中村桂子評・いまやその筋の定番書)、ユルスナール『東方綺譚(きたん)』(須賀敦子評・ユルスナール・リバイバルはここに始まった)、ブルゴス『私の名はリゴベルタ・メンチュウ』(松山巖評・邦訳刊行から六年後にあえて「今年の一冊」として紹介)、ダルモン『癌(ガン)の歴史』(杉浦日向子評・「癌の歴史」は向き合う自己の歴史でもある、と評す)、デヴィ『女盗賊プーラン』(山室恭子評・爆発的にヒットした翻訳書の超ダークホース)、片岡義男『日本語の外へ』(沼野充義評・作家の論理的な文体の核心を批評)……。
「本棚」の看板である和田誠・装画の「私の三冊」がふんだんに収録されているのも楽しい。井上ひさしのシェイクスピア三冊、萩尾望都のブラッドベリ三冊、野坂昭如のアンデルセン三冊等々。ともかくも書評の妙技が百花繚乱(りょうらん)。そして最後に言うと、吉田秀和『マネの肖像』の清水徹評の出だしは、書評者のもつべき矜恃(きょうじ)をも語っているだろう。「みごとなマネ論である。なぜ『みごと』なのか?著者がここで絵画のことしか語っていないからだ」。あてこすり書評や自説開陳や美文を気取る空回り。こうした下心から距離をおいた書評だけが、まっすぐに読み手の胸に届くに違いない。小さな矢のさばき方と収め方いかんで、書評の「愉快さ」と「立派さ」は決まるのである。
ALL REVIEWSをフォローする