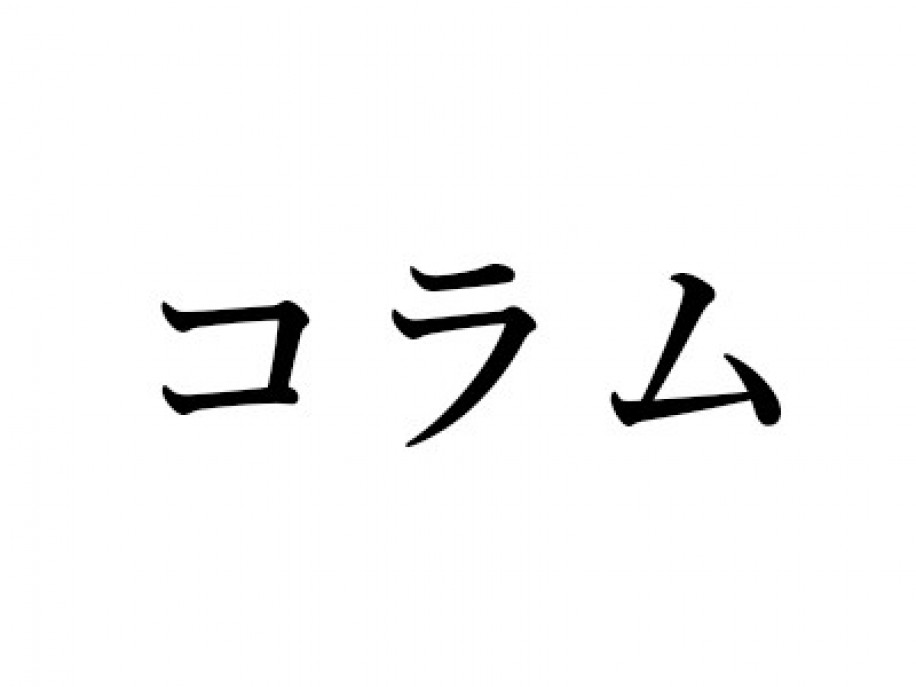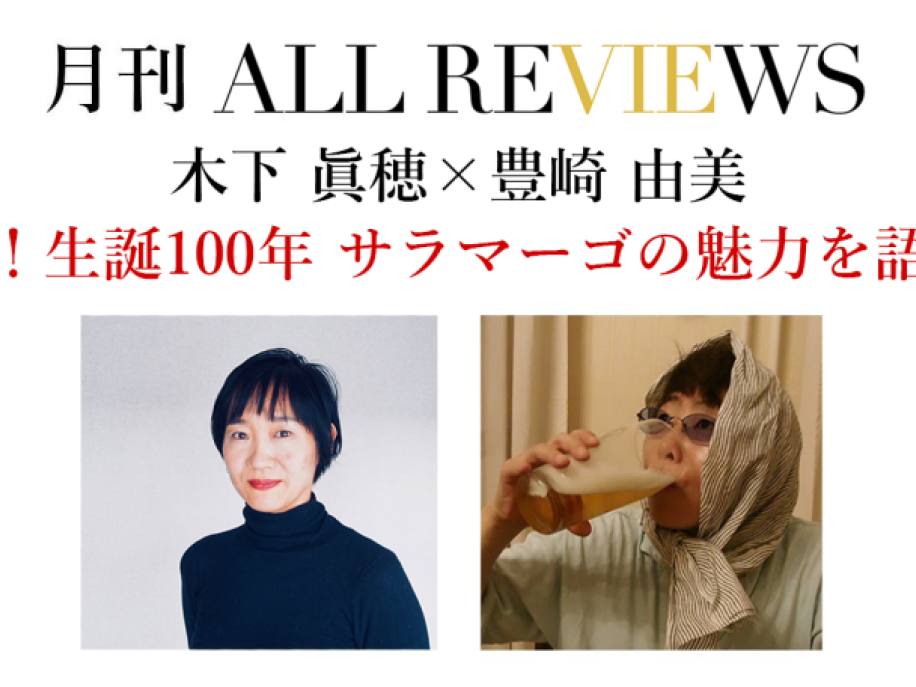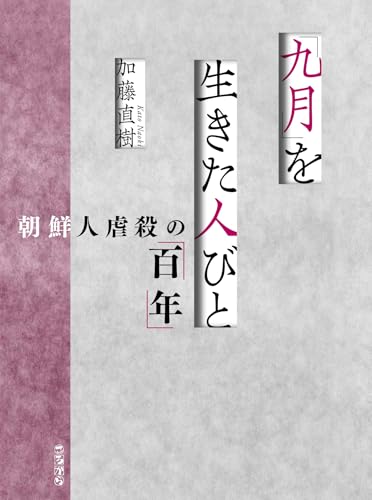書評
『エルサレム』(河出書房新社)
恐怖と狂気充満、悪夢のリアリズム
五月二十九日の夜明け前、死が近づいたミリアは、体の痛みをおして教会を目指すが、戸は開かない。痛みを忘れるほどの空腹に突き動かされて、ミリアはかつての恋人に電話をかける。エルンストは、ミリアの電話を受ける直前、人生に絶望して窓から飛び降りようとしていたが、元恋人のSOSに、夜の街に出る。ミリアの元夫テオドールはといえば、娼婦のハンナと会っている。ハンナの情夫のヒンネルクは、銃を持って夜中の街をうろついている。父テオドールが自分を一人にしたことに憤った十二歳の息子カースも、父を探して家を出てしまう。「こんな夜中に一人で歩いてはだめだ」と、カースに声をかけるのはヒンネルクだ。この夜の出来事だけでも、登場人物たちの運命は舞台劇のように濃密に絡み合う。そして、その運命の日の記述と入れ子状に語られるのが、彼らの過去。テオドールの妻だったミリアは、規律の厳しいゲオルグ・ローゼンベルク精神病院で、同じく患者だったエルンストと恋に落ち、生まれたのがカースである。
タイトルは、「エルサレムよ、もしも、わたしがあなたを忘れるなら、わたしの右手はなえるがよい」という旧約聖書からの引用で、ミリアは「エルサレム」を「ゲオルグ・ローゼンベルク」と入れ替え、折に触れて「右手」を確認する。恐怖によって患者の狂気を統制していた病院での日々を、彼女が忘れることはないからだ。
恐怖と狂気は、小説中に充満している。本書の舞台は架空の、東欧あたりの街らしい。リアリズム小説の手法で書かれているのに、カフカのような迷宮感がある。それでいて、登場人物のキャラクターの強烈さには、古典的な風格さえ漂う、不思議な小説だ。
もっとも不気味なのは、テオドールがのめりこむ「恐怖の歴史」の研究だ。虐殺の犠牲者についてのもので、「弱者を前にした際、強者がいかにふるまうか」が研究対象。「弱者」とは抵抗の可能性がない圧倒的な弱者のことで、力の差が歴然としていても戦う意思のある相手との「戦争」は除外される。
この、テオドールの奇妙な研究と、ゲオルグ・ローゼンベルク精神病院の患者への統制がオーバーラップする。読んでいるうちに心が恐怖に震え出すのは、この「強者」による「弱者」への恣意(しい)的拘禁や虐待に近いことが、たとえば精神病院で、介護施設で、入管収容所で、じっさいに行われたという報道に震撼させられることがあり、それが絶対的な過去のものでも、想像の世界のものでもないことを知っているからだ。
カナダで先住民の子どもたちの寄宿舎だったところから大量の遺骨が発掘されたニュースなども頭にちらつく。結局のところ、人は加害者になるか被害者になるかだ、というテオドールの凄(すさ)まじい研究は、読み手の心を抉(えぐ)る。
タヴァレスは現代ポルトガルの最重要作家であり、本書は長篇群「王国」四部作の第三部だという。強烈な印象を残す『エルサレム』以外の作品も邦訳を読んでみたい。現在、日本語で読めるのは短篇「ヴァルザー氏と森」(近藤紀子訳。『ポルトガル短篇小説傑作選』所収。現代企画室刊)のみで、これはちょっと笑える掌篇だが、いずれにしても読者をよい意味で手玉に取って、グイグイ読ませるのが、絶妙にうまい作家だと感じた。
ALL REVIEWSをフォローする