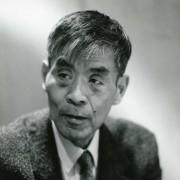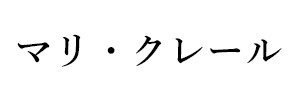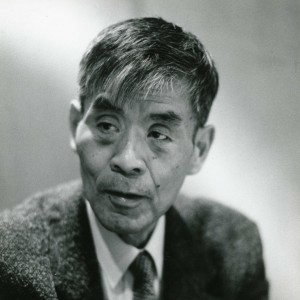書評
『仮往生伝試文(新装版)』(河出書房新社)
この本を何と呼ぶべきだろうか? 著者のつけた本の名前に忠実にいえば『往生極楽記』『法華経験記』『続本朝往生伝』『拾遺往生伝』『今昔物語』のたぐいに書かれた法華浄土思想から身をすてた僧侶や遁世の者たちの説話を読みながら、浮んできたイメージを自在に展開したものだといえそうだ。説話をどう呼んだかわかる記述がいつの間にか著者のイメージにつながって、どこまでもひきのばされる場合もあれば、説話を述べた前半部にたいして、ちょうど反歌のように現在のじぶんのなりわいや日常の心の影を追っている場合もある。もっと形をこわして現在の著者自身の日常の出来ごと、関心、自然物やエロスについての想像のひろがりのなかに、さり気なく往生(生と死)に託された感懐が述べられている場合もある。
この本をどう読むか、ひとそれぞれだろうが、わたしは説話の文学化というモチーフからはじまっていると読んだ。つまりそこが入口だとおもう。説話も文学じゃないかと混ぜかえされないために、急いでつけ加えれば、この文学化は固有化ということで、著者の想像力の展性の質と方法の叙述がそのまま創作になっているということだ。著者はたぶんそこを読んで欲しいのだとおもう。これはさくばくとした、だが高度な達成だ。
わたしは何とかして内容に立ち入ってゆきたいので、どこかに強烈な記述がないかと探す眼つきになった。それはたったひとつあった。一遍らの開宗した時宗の遊行集団が、この世浄土の信仰のまにまに念仏の旅をつづける。道中に一行のうちからつぎつぎに病んだ落伍者や、定住したくなったものや、行倒れてそのまま死ぬものや、あらたに一行の旅にとび入りで加わるものがいる。いずれにせよ落伍したり、行倒れたりして果てたところが浄土のきわみであり、そこで死ぬことが往生だということになる。ひどい理念だが一遍のようなラジカルな小思想家の浄土理念では、どうしてもそういうことになる。この本の著者の想像力と仮構力の質が量れるので、そこを引用してみる。
いくらか軍隊の強行軍や、山登りの遭難のイメージが混ざってくるが、本来とても感銘をうける信仰習俗のカタストロフィの場面なのだ。わたしはこの個所にぶつかって柳田国男の『故郷七十年』のなかの柳田の母の兄にあたる人のことを、あるとき母親が語ってきかせてくれたこととして記述しているところをおもいうかべた。あるとき母親は、じぶんの兄は不治の性病に感染していて、その頃の商家の習いとして、跡目を継ぐことができない兄は、御遍路に出てそのまま還らないはずの旅にいった。それが不文律のような習俗だったことを柳田は記している。わたしはこの個所の柳田の記述を読みながら、じいんとしてきたのをおぼえている。これが柳田民俗学の往生伝のかなめにあたることが、すぐにわかる記述だからだ。
この本の著者の往生伝のかなめはどこにあるのだろうか。もうすこし立ち入ってみる。引用したところでも充分なのだが、際立たせていえば、ひとつは感受性の型の特異さだといえよう。「また明後日ばかりまねるべきよし」のなかで著者とおぼしき記述者は、競馬場で暮れの寒い最終レースまで帰らない客たちの混雑を眺めながら、来年の暮れころには、このなかの何人にひとりは、競馬場にもこの世にもいないだろうとおもいながら、ひとしお人々の顔々を見渡す。ここまではごくふつうの往生伝の感性だ。ところでそう思って一回きりかも知れぬ人々の顔を見渡しているうちに、どれもこれもおなじことを考えている面相に見えてくる。
つまりひとつは一点に収縮するはずのイメージが、集団を同一にする場所へ、展性をもってひろがってゆくこの著者の初期からの特質につながってゆく。もうすこし著者に沿っていえば、イメージが薄まってゆくはてに現実の光景が眼ざめてくるのではなく、現実の光景を最初のイメージのなかに放ってゆけばゆくほどイメージは集団性を帯びてひろがり、そのはてにじぶんの場所を内省する眼ざめがやってくる。この感受性の型は特異で、ふつうわたしたちがやっているのと逆行する。これはいつも既視であるようなイメージなのだ。
この本の文体は、対象となる物と事を既視へいつも戻そうとするところにうまれた独白体(反独白体)からできている。つぶやき、独り言、内省的な告白、このいずれともちがう独白体(反独白体)だから、独白といっても仕方がないのだが、また独白がはじめにあり、また最後にあるということでは、そう呼ぶほかはない。強いて意味づければ、じぶんに向って独白しているのでもなく、他の人間への関心で独白しているのでもない。〈物〉と〈事〉に向って〈物〉と〈事〉に入りこみ、それを内在化しようとして、独白している。
この文体は収録されたぜんぶの作品に貫かれているものだ。対象は石畳であっても景物のなかの樹木の群れであっても、空襲のときの夜景の記憶のような〈事〉であってもおなじだ。特質はすぐにふたつ指摘できる。主格がヒトであり、一人称であってもほとんど〈物〉にちかい存在であって、これは描写されている対象が、この場合石畳のような〈物〉でありながらヒトにちかい位相で描かれているのとおなじになっている。これは『源氏物語』のような古典物語が、はじめから読者と黙契した文体であるために、人称が不明で、あいまいで、脈絡がたどりにくいというのとはまったくちがう。〈物〉とヒトを、また〈事〉とヒトを同一化しようとするこの著者の文体の特徴、その試みからきている。もっといえば物神志向からきている。石畳がどう存在していようと、存在自体には何の物語もないとかんがえる視点からは、退屈で無意味な描写なのだが、この本の著者の飽くなき〈物〉と〈事〉の存在にたいする描写の好奇心に周波数をあわせられる読者には、かつてこういう文学作品は存在しなかったし、しようとおもってもできなかった次元に、文体の領域を走らせているともいうことになる。
ほんとうをいえば、書評として和解の余地のない分岐点はここの問題につきるとおもう。ただこの著者にはいつも実験する意識があって作品を作品として読む人たちを遠ざけるとともに、作品を描写実験として読む人たちにとって魅力の源泉をもった作家だということもたしかなのだ。わたしはいつもそう感じるのだが、この本でもまた、和解のところでこの著者の作品を読みたいという気持を持ちつづける。この仮往生伝でいえば、老、病、死の説話を繋いで流れるエロスのたくらみのところで、〈物〉になった身体と〈事〉になった感性との結合する場面を重要におもいたい気がするのだ。
この情景は秋声や荷風のいた大正末から昭和はじめの風俗のなかに置いてみようとしても、それは成り立たない。男に抱かれるうちに、「軒」が暮れていく、という感性がその時代の女に存在できなかったからだ。逆に現在の風俗のなかに置こうとしても、この古めかしい感性の粘りに、女は耐えられないにきまっている。この本の著者はどこの風俗を描こうとしているのか。さまざまな幻想の階梯のどこからでも自在に言葉をとりだせるこの著者の想像力の次元でいえば、生、死、老の身体を流れる無意識が往生する場所というのが、この本の風俗が成り立つところのような気がする。
【文庫版】
【この書評が収録されている書籍】
この本をどう読むか、ひとそれぞれだろうが、わたしは説話の文学化というモチーフからはじまっていると読んだ。つまりそこが入口だとおもう。説話も文学じゃないかと混ぜかえされないために、急いでつけ加えれば、この文学化は固有化ということで、著者の想像力の展性の質と方法の叙述がそのまま創作になっているということだ。著者はたぶんそこを読んで欲しいのだとおもう。これはさくばくとした、だが高度な達成だ。
わたしは何とかして内容に立ち入ってゆきたいので、どこかに強烈な記述がないかと探す眼つきになった。それはたったひとつあった。一遍らの開宗した時宗の遊行集団が、この世浄土の信仰のまにまに念仏の旅をつづける。道中に一行のうちからつぎつぎに病んだ落伍者や、定住したくなったものや、行倒れてそのまま死ぬものや、あらたに一行の旅にとび入りで加わるものがいる。いずれにせよ落伍したり、行倒れたりして果てたところが浄土のきわみであり、そこで死ぬことが往生だということになる。ひどい理念だが一遍のようなラジカルな小思想家の浄土理念では、どうしてもそういうことになる。この本の著者の想像力と仮構力の質が量れるので、そこを引用してみる。
歩きつづけてきた者が、道に坐りこんだが最後、立ちあがれなくなる。膝上までの水を渡っていたのが、流れの中で立ちつくす。劣らず蹌跟と歩む仲間たちは、しばらく行ってから背後のけはいを感じて振り返るが、そこまでは戻る体力がない。立ちつくした者はわずか数間の向こうから、すでに境を異にした目で見送っている。やがて膝を折って水の中に坐りこむ。つられて立ち止まった何人かの者たちが同様にそれぞれその場に沈む。そのすぐ傍を通りかかり、坐りこんだ仲間の腕にたまたま手をかけた者も、一度は引き起しかけて、自分からその傍に沈みこむ。皆、腰まで水に漬って、うっすらと笑いのようなものを口もとにうかべながら、行く手を見つめる目の光が薄くなっていく。
いくらか軍隊の強行軍や、山登りの遭難のイメージが混ざってくるが、本来とても感銘をうける信仰習俗のカタストロフィの場面なのだ。わたしはこの個所にぶつかって柳田国男の『故郷七十年』のなかの柳田の母の兄にあたる人のことを、あるとき母親が語ってきかせてくれたこととして記述しているところをおもいうかべた。あるとき母親は、じぶんの兄は不治の性病に感染していて、その頃の商家の習いとして、跡目を継ぐことができない兄は、御遍路に出てそのまま還らないはずの旅にいった。それが不文律のような習俗だったことを柳田は記している。わたしはこの個所の柳田の記述を読みながら、じいんとしてきたのをおぼえている。これが柳田民俗学の往生伝のかなめにあたることが、すぐにわかる記述だからだ。
この本の著者の往生伝のかなめはどこにあるのだろうか。もうすこし立ち入ってみる。引用したところでも充分なのだが、際立たせていえば、ひとつは感受性の型の特異さだといえよう。「また明後日ばかりまねるべきよし」のなかで著者とおぼしき記述者は、競馬場で暮れの寒い最終レースまで帰らない客たちの混雑を眺めながら、来年の暮れころには、このなかの何人にひとりは、競馬場にもこの世にもいないだろうとおもいながら、ひとしお人々の顔々を見渡す。ここまではごくふつうの往生伝の感性だ。ところでそう思って一回きりかも知れぬ人々の顔を見渡しているうちに、どれもこれもおなじことを考えている面相に見えてくる。
あれだけ面相があらわに通いあっては、いくらたがいに無縁の大衆だろうと、おそらく身体の相と言ったものもいっとき通いあうことだろうから、もしもこの場に何かの、はやり病いの種子でもひそんでいたら、たちまちひろがって、根をおろすことになりはしないか、と埒もない危惧が風とともに吹き抜け、足もとが冷えこんで、立ち停まったばかりに肌から蒼味をおびてくるように感じられた。
つまりひとつは一点に収縮するはずのイメージが、集団を同一にする場所へ、展性をもってひろがってゆくこの著者の初期からの特質につながってゆく。もうすこし著者に沿っていえば、イメージが薄まってゆくはてに現実の光景が眼ざめてくるのではなく、現実の光景を最初のイメージのなかに放ってゆけばゆくほどイメージは集団性を帯びてひろがり、そのはてにじぶんの場所を内省する眼ざめがやってくる。この感受性の型は特異で、ふつうわたしたちがやっているのと逆行する。これはいつも既視であるようなイメージなのだ。
この本の文体は、対象となる物と事を既視へいつも戻そうとするところにうまれた独白体(反独白体)からできている。つぶやき、独り言、内省的な告白、このいずれともちがう独白体(反独白体)だから、独白といっても仕方がないのだが、また独白がはじめにあり、また最後にあるということでは、そう呼ぶほかはない。強いて意味づければ、じぶんに向って独白しているのでもなく、他の人間への関心で独白しているのでもない。〈物〉と〈事〉に向って〈物〉と〈事〉に入りこみ、それを内在化しようとして、独白している。
全体がゆるやかに迫りあがっているが、石のひとつひとつも迫りあがっている、といまさら感心した。石の頭が円くふくらむだけではなくて、見るからに迫りあげの力を受けて、たがいに抑えあっていた。小さな広場の端のようなところに、穴からわずかに頭を、額の高さほどに差し出した恰好になる。そのことは、やや上目づかいに、きょとんと見渡す顔つきからも分かった。しかしそのうちに、石畳の見え方をまた訝りはじめた。広場の中ほどへ向けて盛りあがっているはずなのが、今ではやはりゆるやかながら、中窪みに、反って見える。そしてその反りに合わせて、それに上から平行に寄り添わせるように、眺めるほうの身体も、ゆるい弓なりに反った。
この文体は収録されたぜんぶの作品に貫かれているものだ。対象は石畳であっても景物のなかの樹木の群れであっても、空襲のときの夜景の記憶のような〈事〉であってもおなじだ。特質はすぐにふたつ指摘できる。主格がヒトであり、一人称であってもほとんど〈物〉にちかい存在であって、これは描写されている対象が、この場合石畳のような〈物〉でありながらヒトにちかい位相で描かれているのとおなじになっている。これは『源氏物語』のような古典物語が、はじめから読者と黙契した文体であるために、人称が不明で、あいまいで、脈絡がたどりにくいというのとはまったくちがう。〈物〉とヒトを、また〈事〉とヒトを同一化しようとするこの著者の文体の特徴、その試みからきている。もっといえば物神志向からきている。石畳がどう存在していようと、存在自体には何の物語もないとかんがえる視点からは、退屈で無意味な描写なのだが、この本の著者の飽くなき〈物〉と〈事〉の存在にたいする描写の好奇心に周波数をあわせられる読者には、かつてこういう文学作品は存在しなかったし、しようとおもってもできなかった次元に、文体の領域を走らせているともいうことになる。
ほんとうをいえば、書評として和解の余地のない分岐点はここの問題につきるとおもう。ただこの著者にはいつも実験する意識があって作品を作品として読む人たちを遠ざけるとともに、作品を描写実験として読む人たちにとって魅力の源泉をもった作家だということもたしかなのだ。わたしはいつもそう感じるのだが、この本でもまた、和解のところでこの著者の作品を読みたいという気持を持ちつづける。この仮往生伝でいえば、老、病、死の説話を繋いで流れるエロスのたくらみのところで、〈物〉になった身体と〈事〉になった感性との結合する場面を重要におもいたい気がするのだ。
男に抱かれるうちに、軒が暮れてゆく。その時間を女は、眠りこんだ男を暗くなった部屋に置いて寒い台所で夕飯の仕度を続けるあいだも、肌に曳いていた。しあわせという気持にまして、いつかこの間がつくづくしあわせだったと思い返される時があるだろうなと感じた。土曜の夜ごとにくりかえされても、どこかたがいに人見知りのされる、人並みにさしむかいの夕飯のあと、女は男を銭湯にやると、この家に入った時からの習慣で、なにか先住者の、病人の鋭い嗅覚をはばかるような神経から、そそくさと汚れ物を始末して、男の帰りを待って居間に坐りこむ。
この情景は秋声や荷風のいた大正末から昭和はじめの風俗のなかに置いてみようとしても、それは成り立たない。男に抱かれるうちに、「軒」が暮れていく、という感性がその時代の女に存在できなかったからだ。逆に現在の風俗のなかに置こうとしても、この古めかしい感性の粘りに、女は耐えられないにきまっている。この本の著者はどこの風俗を描こうとしているのか。さまざまな幻想の階梯のどこからでも自在に言葉をとりだせるこの著者の想像力の次元でいえば、生、死、老の身体を流れる無意識が往生する場所というのが、この本の風俗が成り立つところのような気がする。
【文庫版】
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする