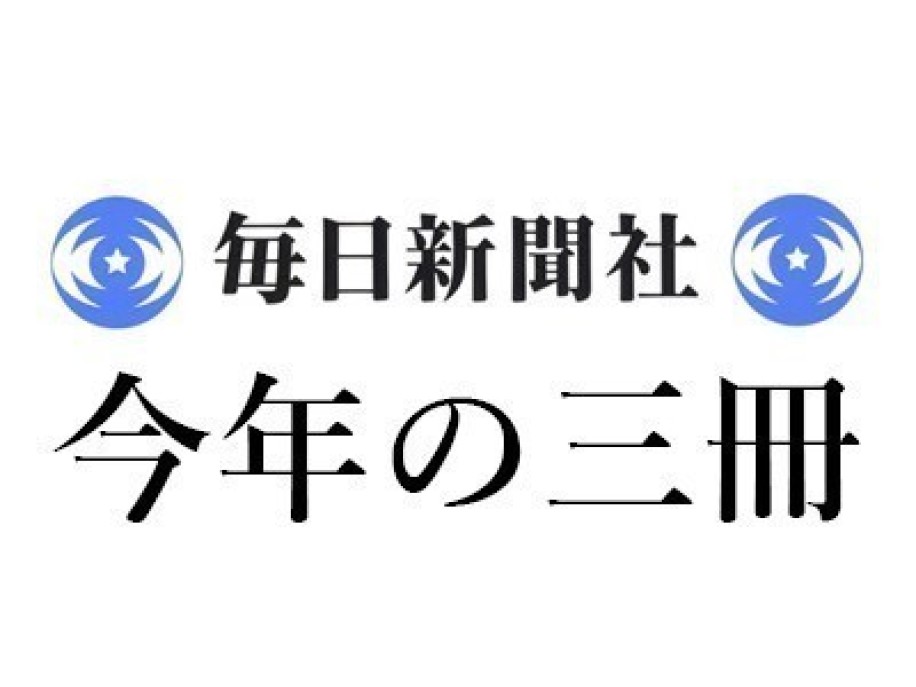解説
『奇想小説集』(講談社)
山田風太郎の小説を読むたび、いつも不思議に思っていたことがある。
山田風太郎の小説は、忍法ものをはじめとしてほとんどすべてが「奇想小説」と呼ぶべきジャンルのものである。奇想天外、荒唐無稽。「でたらめ」の楽しさを狙ったものである。
小説ばかりではなく映画でもそうなのだが、奇想天外とか荒唐無稽を志向した作品は、おうおうにして幼稚な感じのものが多く、しんからのめり込むことができない。作り手の社会性のなさや人間観や世界観の未熟さが透けて見えるようで、「そりゃあ確かにコドモの頭はファンタジーでいっぱいだろうよ」と皮肉の一つも言いたくなる。「あんまりかたいことは言いたくないが、しかし、やっぱり“子どもだまし”“こけおどし”でしかない作品というものはあるものだ」と思う。
ところが、山田風太郎の小説には、そういう幼稚な感じが全然ないのだ。大人が読んでも、と言うより大人が読んでこそ楽しい「でたらめ」話になっている。「稚気」はあっても、「幼稚」ではない。いったいどこがどう違うのだろう。そこが不思議だ。
唐突かもしれないが……「奇想小説」というのは、凧上げの風景に似ていると思う。凧上げというのは、凧ができるだけ天空高くあがっていて、しかもフラつくことなく安定している——つまり、はるかに悠然としている姿が美しいと思う。
きっと難しいのは、凧が強い風を受けて、凧と人間とを結ぶ糸がピーンと張りつめたときだろう。凧上げ名人は、地に足を踏ん張り、腰をグッと入れて、そして非常に微妙な指先のカンで糸を操ることだろう。足腰の力や指先のカンのない人間があげている凧は、たちまちバランスを失い、墜落したりフラついたり。見るからに頼りなく、あぶなかしい有様になるに違いない。
私は、山田風太郎は凧上げ名人で、「でたらめ」を扱いながら足腰の力と指先のカンが断然すぐれていることによって、幼稚さを免れたのだと思う。大人の「奇想小説」を書けたのだと思う。
足腰の強さというのは、たとえば山田風太郎のデビュー以前、二十歳(はたち)前後の頃の日記(『戦中派虫けら日記』『戦中派不戦日記』)を読めば、すぐに納得していただけると思う。二重三重に屈折した自意識、徹底した虚無主義、強い倫理観、醒めた観察眼——それらの壮絶なまでの葛藤のあげくに生まれた「でたらめ」の境地なのである。子どものひよわな「でたらめ」ではない、大人のたくましい「でたらめ」なのだ。
指先のカンがすぐれているということは、たとえば本書におさめられた短編が、がいして性および性器にまつわる奇想をもとにしているのにもかかわらず、けっして下劣に陥らず、ある品格を保っていることからも納得していただけると思う。
山田風太郎はもともとは医者をめざした人であるから、いかにもそれらしく、もっともらしく、医学的科学的説明をすることが多い。そういう即物的表現が、かえって「はるかに、悠然」といった品格と滑稽感を生み出しているのだ。
本書の中では、やはり『満員島』(ほとんど筒井康隆じゃない!?)が一番、濃い。聖書的レトリックを利用しているからだけではなく、黙示録的なハルマゲドン的な大きさを感じさせる小説だ。私がとくに笑ったのは、制欲帯の制限時間をためこんだ農民が都会人にそれを高い値段で売りつけるところで、「あの戦争中、都会の飢えにつけこんだ農民の慾の発揮ぶりが、その節度というものを知らず、米一升に箪笥ひと棹を要求するようなこともまれではなかったように、こんどのやりかたも豪快で野性にみちみちたものだった」と表現しているところである。
「豪快で野性にみちみちたもの」という、この表現が、いかにも山田風太郎らしい。諷刺とか皮肉というのではない、俗っぽい強欲にたいするある種のまぶしさと懐かしさとか畏れのようなものがこめられている表現だと思う。
そんなささいなところにも、私は「大人だなあ」と唸ってしまうのである。
(「大衆文学館」シリーズ『奇想小説集』巻末エッセイ)
【この解説が収録されている書籍】
山田風太郎の小説は、忍法ものをはじめとしてほとんどすべてが「奇想小説」と呼ぶべきジャンルのものである。奇想天外、荒唐無稽。「でたらめ」の楽しさを狙ったものである。
小説ばかりではなく映画でもそうなのだが、奇想天外とか荒唐無稽を志向した作品は、おうおうにして幼稚な感じのものが多く、しんからのめり込むことができない。作り手の社会性のなさや人間観や世界観の未熟さが透けて見えるようで、「そりゃあ確かにコドモの頭はファンタジーでいっぱいだろうよ」と皮肉の一つも言いたくなる。「あんまりかたいことは言いたくないが、しかし、やっぱり“子どもだまし”“こけおどし”でしかない作品というものはあるものだ」と思う。
ところが、山田風太郎の小説には、そういう幼稚な感じが全然ないのだ。大人が読んでも、と言うより大人が読んでこそ楽しい「でたらめ」話になっている。「稚気」はあっても、「幼稚」ではない。いったいどこがどう違うのだろう。そこが不思議だ。
唐突かもしれないが……「奇想小説」というのは、凧上げの風景に似ていると思う。凧上げというのは、凧ができるだけ天空高くあがっていて、しかもフラつくことなく安定している——つまり、はるかに悠然としている姿が美しいと思う。
きっと難しいのは、凧が強い風を受けて、凧と人間とを結ぶ糸がピーンと張りつめたときだろう。凧上げ名人は、地に足を踏ん張り、腰をグッと入れて、そして非常に微妙な指先のカンで糸を操ることだろう。足腰の力や指先のカンのない人間があげている凧は、たちまちバランスを失い、墜落したりフラついたり。見るからに頼りなく、あぶなかしい有様になるに違いない。
私は、山田風太郎は凧上げ名人で、「でたらめ」を扱いながら足腰の力と指先のカンが断然すぐれていることによって、幼稚さを免れたのだと思う。大人の「奇想小説」を書けたのだと思う。
足腰の強さというのは、たとえば山田風太郎のデビュー以前、二十歳(はたち)前後の頃の日記(『戦中派虫けら日記』『戦中派不戦日記』)を読めば、すぐに納得していただけると思う。二重三重に屈折した自意識、徹底した虚無主義、強い倫理観、醒めた観察眼——それらの壮絶なまでの葛藤のあげくに生まれた「でたらめ」の境地なのである。子どものひよわな「でたらめ」ではない、大人のたくましい「でたらめ」なのだ。
指先のカンがすぐれているということは、たとえば本書におさめられた短編が、がいして性および性器にまつわる奇想をもとにしているのにもかかわらず、けっして下劣に陥らず、ある品格を保っていることからも納得していただけると思う。
山田風太郎はもともとは医者をめざした人であるから、いかにもそれらしく、もっともらしく、医学的科学的説明をすることが多い。そういう即物的表現が、かえって「はるかに、悠然」といった品格と滑稽感を生み出しているのだ。
本書の中では、やはり『満員島』(ほとんど筒井康隆じゃない!?)が一番、濃い。聖書的レトリックを利用しているからだけではなく、黙示録的なハルマゲドン的な大きさを感じさせる小説だ。私がとくに笑ったのは、制欲帯の制限時間をためこんだ農民が都会人にそれを高い値段で売りつけるところで、「あの戦争中、都会の飢えにつけこんだ農民の慾の発揮ぶりが、その節度というものを知らず、米一升に箪笥ひと棹を要求するようなこともまれではなかったように、こんどのやりかたも豪快で野性にみちみちたものだった」と表現しているところである。
「豪快で野性にみちみちたもの」という、この表現が、いかにも山田風太郎らしい。諷刺とか皮肉というのではない、俗っぽい強欲にたいするある種のまぶしさと懐かしさとか畏れのようなものがこめられている表現だと思う。
そんなささいなところにも、私は「大人だなあ」と唸ってしまうのである。
(「大衆文学館」シリーズ『奇想小説集』巻末エッセイ)
【この解説が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする