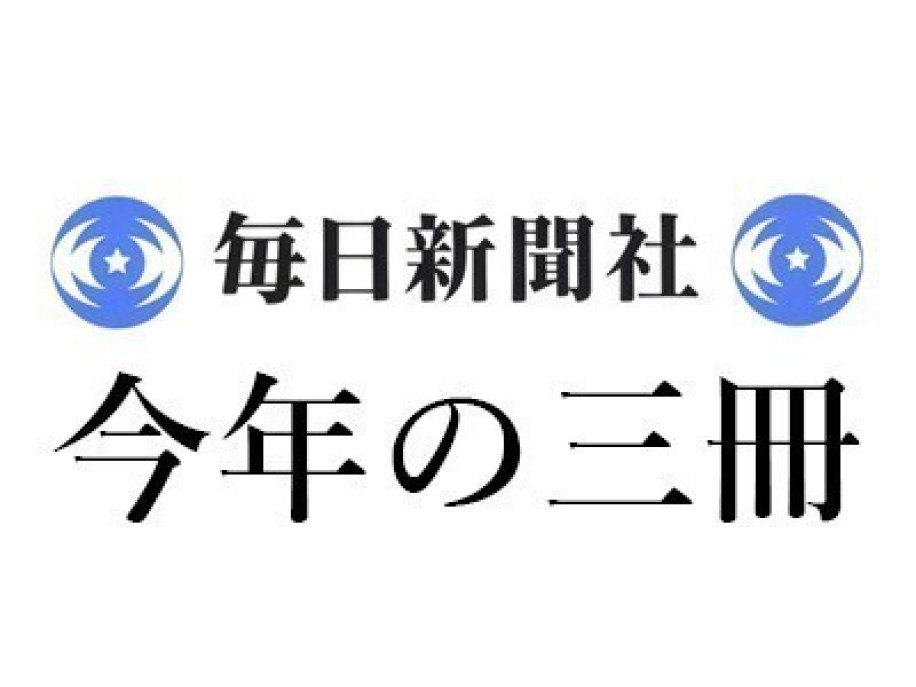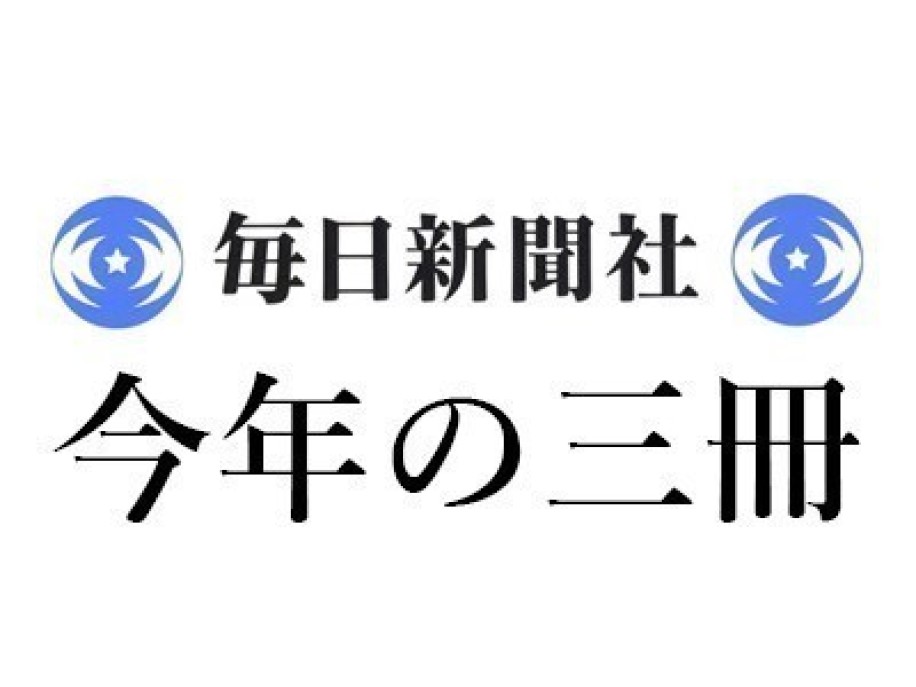書評
『日本エッセイ小史 人はなぜエッセイを書くのか』(講談社)
曖昧で融通無碍、だからこそ
ぼくは遠藤周作も北杜夫もエッセイから入った。「ぐうたら」シリーズや「どくとるマンボウ」シリーズである。だから小説『白い人・黄色い人』や『夜と霧の隅で』を読んだときはびっくりした。甘いお菓子だと思ってかぶりついたら堅くて苦くて辛かった、みたいな感じ。でもそれをきっかけに吉行淳之介や安岡章太郎ら、遠藤のエッセイに登場する作家たちのエッセイや小説を読むようになった。エッセイには文芸への入り口を広げる力がある。この本は人気エッセイストが書いた、エッセイにまつわるエッセイ。紀貫之の『土佐日記』や清少納言の『枕草子』から、石井哲代『102歳、一人暮らし。哲代おばあちゃんの心も体もさびない生き方』まで、千年以上にわたる日本のエッセイのあゆみが書かれている。学術的な論考ではなく、あくまでエッセイ。「そうそう、こんな人もいた。あんな本もあった」と、愉快な気持ちになってくる。
エッセイは文芸世界における雑草のような存在だと著者はいう。ジャンルの輪郭がはっきりせず、誰にでも書ける。だからこそ、エッセイにはそれが書かれた時代が映し出されている。
エッセイの近代史において重要だと思われるポイントがふたつ出てくる。ひとつは1965年、伊丹一三(のち十三)『ヨーロッパ退屈日記』の登場だ。若い俳優が、ニコラス・レイ監督「北京の55日」撮影のためにヨーロッパに滞在したときのことを書いた本。当時の若者に大きな衝撃を与えた。
「この人が『随筆』を『エッセイ』に変えた」は新潮文庫版の帯だそうだが、うまいことをいう。スパゲティをアルデンテで茹でるなんて、この本で知った人も多いだろう。伊丹十三以降、若者にとってエッセイとは「何となくカッコいいもの」になる。
ふたつめのポイントは1980年前後。新しいエッセイの書き手が次々と登場したのである。たとえば『さらば国分寺書店のオババ』の椎名誠、『ルンルンを買っておうちに帰ろう』の林真理子。少し後には泉麻人らコラムニストがブームになる。
椎名誠らによるちょっとふざけた感じの文体、昭和軽薄体が一瞬だけ流行したり、さまざまな職業におけるマル金(富裕層)とマルビ(貧困層)をイラストで解説した『金魂巻』がベストセラーになったりもした。エッセイ(コラム)がサブカルチャー化したともいえるし、サブカルチャーの文芸版がエッセイだともいえそう。
なるほど!と思ったのは、「『つるむ』という芸」という章。著者は尾辻克彦/赤瀬川原平の『東京路上探険記』を読んで、「この頃の男達は、よく群れている」と感じたのだという。赤瀬川の路上観察学会、野坂昭如の酔狂連、椎名誠のあやしい探検隊。さらに遡ると漱石一門や白樺派、阿佐ケ谷会。思えばぼくが中学生のころ夢中になって読んだ遠藤周作や安岡章太郎のエッセイも文壇交友について書かれていた。しかし今は男達もつるまなくなった。
エッセイとは何か、随筆とはどう違うのか、という疑問からスタートする本書だが、はっきりとした結論は出ない。その輪郭は曖昧で、融通無碍(ゆうづうむげ)だからこそ多くの人を惹きつける。
ALL REVIEWSをフォローする